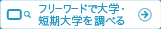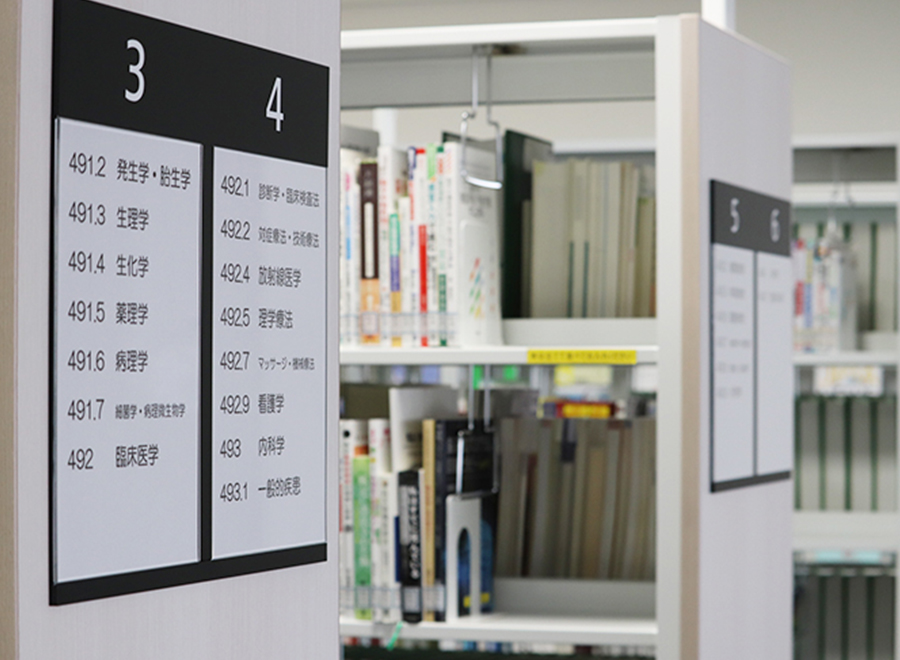名古屋学院大学
名古屋学院大学
リハビリテーション学部

外国人教員
- 外国人教員雇用・派遣受入?
-
 ●取り組みの内容リハビリテーション学部では、NGUスタンダード科目の語学科目を本学の任期制外国人教員が担当しています。
●取り組みの内容リハビリテーション学部では、NGUスタンダード科目の語学科目を本学の任期制外国人教員が担当しています。
連携活動
- 学校間連携?
-
 ●取り組みの内容名古屋学院大学リハビリテーション学部は、名古屋市立大学、名古屋工業大学と共に、住み慣れた土地で、豊かに老いを迎え、その人らしく暮らすことのできる社会作り(エイジング・イン・プレイス、AIP)を支える医療人材育成のために文部科学省からの助成金を得て、「なごやかモデル」プロジェクトに参画しています。
●取り組みの内容名古屋学院大学リハビリテーション学部は、名古屋市立大学、名古屋工業大学と共に、住み慣れた土地で、豊かに老いを迎え、その人らしく暮らすことのできる社会作り(エイジング・イン・プレイス、AIP)を支える医療人材育成のために文部科学省からの助成金を得て、「なごやかモデル」プロジェクトに参画しています。
また、「大学コンソーシアムせと」は、瀬戸市及び愛知工業大学、金城学院大学、名古屋学院大学、名古屋産業大学、南山大学によって構成され、瀬戸中心部にある「パルティせと」を拠点に大学と地域が連携し、学生はもとより市民が、まちづくりや生涯学習活動に参加することにより、新たな地域文化の創出や交流活動促進等を行い、もって瀬戸市及び加盟大学の相互の発展に寄与することを目的としています。 - 高大連携プログラム?
-
 ●取り組みの内容教員の専門分野(あるいは担当科目)をベースとして高等学校の総合的学習に適した分野に教員を派遣して講義を行っています。
●取り組みの内容教員の専門分野(あるいは担当科目)をベースとして高等学校の総合的学習に適した分野に教員を派遣して講義を行っています。
大学教員による授業を実際に受講することにより、高校生が進路決定をする際の一助となることを目的としています。 - 地域連携?
-
 ●取り組みの内容地域連携センターは2007年1月に設置され、公開講座「シティカレッジ」の実施、行政・企業・市民団体・NPOなどとの連携に関する事業(連携講座を含む)の推進、「大学コンソーシアムせと」事業の推進、公開講演会の開催などを担っています。
●取り組みの内容地域連携センターは2007年1月に設置され、公開講座「シティカレッジ」の実施、行政・企業・市民団体・NPOなどとの連携に関する事業(連携講座を含む)の推進、「大学コンソーシアムせと」事業の推進、公開講演会の開催などを担っています。
名古屋キャンパスについては、名古屋市と「名古屋学院大学と名古屋市との連携協力に関する協定」を締結し、商店街の振興、観光の推進、まちづくりなどを通じて、情報の交換や人の交流、事業の実施によって連携協力しています。
瀬戸キャンパスについては、2003年6月から瀬戸市及びその周辺に立地する大学と瀬戸市で「大学コンソーシアムせと」を発足し、学生や市民がまちづくりや生涯学習活動に参加することによって、新たな地域文化の創出や交流活動促進を図っています。
名古屋学院大学が平成25年度に文部科学省の地(知)の拠点整備事業の採択を受けたことから、名古屋市及び瀬戸市の行政、企業、市民団体等との連携が一層緊密となって様々なプロジェクトが展開されています。
生涯教育
- 科目等履修制度?
-

- 社会人教育?
-
 ●取り組みの内容社会人の学修意欲の向上を目的として、本学の入学試験要項(社会人スカラシップ入試プログラム)に定める社会人出願資格に該当する社会人が本学に入学した場合に各学期授業料の50%相当額を奨学金として給付します。
●取り組みの内容社会人の学修意欲の向上を目的として、本学の入学試験要項(社会人スカラシップ入試プログラム)に定める社会人出願資格に該当する社会人が本学に入学した場合に各学期授業料の50%相当額を奨学金として給付します。
給付期間は1年間ですが、再度の手続きにより、学修状況を勘案したうえで最短修業年限(4年)まで継続できます。毎年4月に手続きがあります。 - 生涯学習?
-
 ●取り組みの内容シティカレッジは、地域貢献活動の一つとして地域の皆さん、一般の方々を対象とした生涯学習講座で、毎年多くの方が受講され好評を博しています。
●取り組みの内容シティカレッジは、地域貢献活動の一つとして地域の皆さん、一般の方々を対象とした生涯学習講座で、毎年多くの方が受講され好評を博しています。
今まで受講いただいた方はもちろん、新しく受講する方も大歓迎!
趣味から教養まで様々な分野の講座を開講しています。
http://www.ngu.jp/extension/citycollege.html
社会貢献
- ボランティア活動?
-
 ●取り組みの内容事前学習と現地活動をとおして、ボランティアとは何か、それが社会でのどのような役割を持っているかを理解し、これを機会に地域でのニーズに合ったボランティアに積極的に参加できる市民になることを目指します。
●取り組みの内容事前学習と現地活動をとおして、ボランティアとは何か、それが社会でのどのような役割を持っているかを理解し、これを機会に地域でのニーズに合ったボランティアに積極的に参加できる市民になることを目指します。
この活動は正課にも取り入れられ、事前学習・事後学習を含めて「ボランティア演習」の単位認定の対象となります。
研究活動
- 多様な研究内容?
-
 ●取り組みの内容【教員合同研究会及び教員研究会】
●取り組みの内容【教員合同研究会及び教員研究会】
教員合同研究会は全教員を対象とした研究会として毎年度1回開催されており、教員研究会としての経済研究会は経済学部だけでなく全教員の研究交流の場として設定されています。
【共同研究】
1.NGUリハビリテーション研究会
本研究会はリハビリテーション医療に関わる専門職者を対象に、知識・技術の向上ならびに学術研究活動の支援を目的としています。本学リハビリテーション学部が主となって、近隣施設・病院医療従事者の方々とともに定例研究集会を運営していますが、2013度より、本学卒業生による「研究報告・症例検討会」も行われるようになりました。
2.「脳と行動の人間学」研究会
本研究会は、臨床リハビリテーション科学、運動学、および人間学(生態人類学)のそれぞれの分野に関わる研究者による能動行動に焦点を当てた研究アプローチを促進することを目的として活動しています。
また、学術研究助成基金助成金や外部機関からの研究助成、名古屋学院大学研究奨励金により様々な研究が行われています。
- 研究施設・設備の充実?
-
 ●取り組みの内容
●取り組みの内容
×
『外国人教員雇用・派遣受入』とは?
外国人教員を雇用したり、外国の学校と協定などを結んで派遣してもらった外国人教員を受け入れて、教育や研究活動をさせる取り組み。
×
『学校間連携』とは?
主に高等教育機関(大学、短期大学、高等専門学校、専門学校など)同士がより良い教育や充実した研究活動をすることを目的に連携協力する取り組み。
×
『高大連携プログラム』とは?
高校と大学の協力により、高校生が大学の学びを体感し、学びに対する意欲を向上させるため、大学の授業への参加や、大学教員の高校での出張講義などの教育プログラムを行う取り組み。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『地域連携』とは?
大学や短期大学が地域社会のニーズに応え、地域と積極的に関わることで、地域の活性化などに貢献し、地域の各市町村などと連携する取り組み。
×
『科目等履修制度』とは?
社会人などのその学校や学部などには在籍していない者に対し、特定の授業科目の履修を認め、正規の学生と同様に授業や試験を行い、単位を授与する制度。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『社会人教育』とは?
社会人を対象とした新たな知識や技術の修得や学び直しに対して、カリキュラムや授業の配慮をするなど学びを支援し、推進することで大学を活性化させることを目的とした取り組み。
×
『生涯学習』とは?
人が生涯にわたり学びや学習の活動を続けていく生涯学習について、大学や短期大学が学びの場や機会を提供するなどの取り組み。
×
『ボランティア活動』とは?
学生が自発的に行うボランティア活動に対して、大学や短期大学が活動の支援や単位認定などをすることにより、学生生活が活性化することを目的とした取り組み。
×
『多様な研究内容』とは?
大学の重要な目的である学生への教育と研究活動のうち、大学が行っている様々な研究活動についての取り組み。
×
『研究施設・設備の充実』とは?
大学の重要な目的である学生への教育と研究活動のうち、研究活動の推進のために建物などの研究施設を建てたり、研究機器などの設備を整備したりする取り組み。