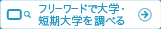東京都(所在地都道府県)/大学学部(部門種別)
上智大学
上智大学





上智大学
上智大学
国際教養学部

- ディプロマポリシー
-
詳細リンク(外部サイトへ)
- カリキュラムポリシー
-
詳細リンク(外部サイトへ)
カリキュラム
- 教養・リベラルアーツ教育?
-
 ●取り組みの内容国際教養学部では、1949年創立当初から70年以上にわたり、Liberal Artsをモデルとした教養教育を、全科目英語により行ってきました。
●取り組みの内容国際教養学部では、1949年創立当初から70年以上にわたり、Liberal Artsをモデルとした教養教育を、全科目英語により行ってきました。
2006年に国際教養学部に改組を行ってからは、Comparative Culture (Art History/Visual
Culture,Literature,Religion and Philosophy),International Business and Economics,Social
Studies (Anthropology and Sociology,History,Political Science)の3専攻7領域を有しています。学生は2年次後半で専攻を選びますが、自専攻のみならず他専攻の科目も一定数履修するカリキュラムであり、英語の高度な運用力に加え、幅広い教養を身につけることが意図されています。
学びの支援
- 学びの組織的な支援?
-
 ●取り組みの内容大学共通ページをご覧ください。
●取り組みの内容大学共通ページをご覧ください。 - 初年次教育?
-
 ●取り組みの内容入学後3セメスターで全員が履修するカリキュラムとして、「コア科目」を設けています。English
●取り組みの内容入学後3セメスターで全員が履修するカリキュラムとして、「コア科目」を設けています。English
Composition 1、English Composition 2、Thinking Processes、Public Speakingの4科目で構成され、どのレベルから履修するかは、入学直後の英語プレイスメントテストの結果により決定します。(ほとんどの学生はEnglish Composition 1から履修します。)
これらの科目を通じて、英語での思考力、筆記および口頭での表現力、プレゼンテーション力などを総合的に磨き上げ、2年次後半からの専攻科目の履修に耐えうる能力を育てるとともに、真に国際社会で活躍することのできる基礎力を育成しています。また、国際教養学部附属のライティング・センターでは、チューターによる個別チュートリアルを通して、授業のライティング課題やプレゼンテーション準備へのアドバイスを行っています。このチュートリアル制度を活用することで、授業に必要な英語のライティングスキルを着実に身につけることができます。
×
『教養・リベラルアーツ教育』とは?
幅広い分野の教養などを身につけ、専門知識に偏らない汎用的能力を育成するために大学・短期大学で行われる教育。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『学びの組織的な支援』とは?
学校側が組織的かつ恒常的に学びに対するサポート体制を用意し、授業に対する学生の不安を解消するなどの学びに対する様々な支援をすることで、より学習効果を高める取り組み。
×
『初年次教育』とは?
大学や短期大学の新入生を対象に、高校までの学びから、能動的な大学・短期大学での学びにスムーズに移行するための基本的なスキルなどを身につける教育プログラム。
用語辞典を開いて詳しく調べる
更新情報
2025/07/21 更新
イベント開催情報はこちらから
イベント開催情報はこちらから
2025/07/21 更新
地球市民講座を開講しています!
地球市民講座を開講しています!
2025/07/21 更新
大学の最新情報・ニュース・お知らせについてはこちらのURLをご覧ください。
大学の最新情報・ニュース・お知らせについてはこちらのURLをご覧ください。
2025/07/21 更新
入学試験に関する最新の情報は、こちらのURLをご覧ください。
入学試験に関する最新の情報は、こちらのURLをご覧ください。
学部・学科情報
- 文学部
- 経済学部
- 法学部
- 神学部
- 外国語学部
- 理工学部
- 総合人間科学部
- 国際教養学部
- 総合グローバル学部
- 神学研究科(修士)
- 経済学研究科(修士)
- 経済学研究科(博士)
- 神学研究科(博士)
- 理工学研究科(修士)
- 文学研究科(修士)
- 文学研究科(博士)
- 法学研究科(修士・専門職)
- 法学研究科(博士)
- 理工学研究科(博士)
- 言語科学研究科(修士)
- 言語科学研究科(博士)
- 地球環境学研究科(修士)
- 地球環境学研究科(博士)
- 総合人間科学研究科(修士)
- 総合人間科学研究科(博士)
- グローバル・スタディーズ研究科(修士)
- グローバル・スタディーズ研究科(博士)
- 実践宗教学研究科(修士)
- 実践宗教学研究科(博士)