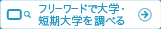東京農業大学
東京農業大学
生命科学部

- ディプロマポリシー
-
生命科学部は、本学の建学の精神「人物を畑に還す」のもと、生物、生命、化学を主たる教育研究の対象とし、汎用的な基礎力と専門的な応用力を磨いて、社会の発展に寄与する人材を輩出す るため、各学科の教育目標に基づいて設置した授業科目を履修して所定の単位数を修得し、卒業論文を提出することを学位授与の要件とするとともに、以下の能力を備えた学生に学位を授与し ます。
(1) 自然科学および教養的分野にわたる基礎的知識の修得と同時に、各学科の目的とする専門的・先進的な知識や技術、コミュニケーション能力などを身につけている。
(2) 卒業論文の作成を通して、課題探求力、情報収集力、知識の活用力、批判的・論理的思考力、問題解決力、数的処理、文章表現およびプレゼンテーション力などの能力を身につけ ている。
(3) 研究室における実験を中心とする諸活動および学会発表のような体験的・実践的活動などに基づき、広い視野、異なる分野への理解や関心、他者への柔軟性、自らの意志を適切に 表現できる表現力あるいは語学力を有し、国内外で活動しうる能力を身につけている。詳細リンク(外部サイトへ) - カリキュラムポリシー
-
生命科学部は、実験・実習や研究室活動を通じて、汎用的な基礎力と専門的な応用力を育む教 育を施し、ディプロマ・ポリシーに掲げた能力を身につけるため、以下の方針の下に各学科の教育課程を編成します。
(1) 基礎的知識の修得と生命科学に関わる実践的な専門科目を体系的に学ぶため、「総合教育科目」、「外国語科目」、「専門教育科目」の3つの科目区分により授業科目を配当する。また、効果的な学修を行うため、ナンバリングやカリキュラムツリーを用いて学修の順序等 を示すなど、各区分内において基礎から応用への段階的な科目配当を行う。
(2) 「総合教育科目」においては社会科学分野の科目も配当し、広い視野の育成を行う。
(3) 「専門教育科目」では、各学科の専門性を学修するための科目を配当し、専門的な基礎知識から先端的な知識にわたる学修を行う。また、学部共通科目を配当し、生命科学における異なる分野への理解や関心の育成と、将来の進路を考える上での助力とする。詳細リンク(外部サイトへ)
カリキュラム
- 教育内容の体系化とその充実?
-
 ●取り組みの内容総合教育科目として「導入科目」「スポーツ関係科目」「課題別科目」「就職準備科目「リメディアル教育科目」を開講し、学部・学科に関係なく、全学的に共通化された教育を受けることができます。
●取り組みの内容総合教育科目として「導入科目」「スポーツ関係科目」「課題別科目」「就職準備科目「リメディアル教育科目」を開講し、学部・学科に関係なく、全学的に共通化された教育を受けることができます。
外国語科目は「基盤英語科目」「実用英語科目」を開講し、英語力の向上及び外国語の能力を養成しています。
学科の専門教育科目については、「学科教養科目」と「学科専門科目」に大別され、教養科目は低学年で共通して修得していきます。
高学年になるにしたがって、各学部等で特色のある専門科目を数多く受講することになります。
最終学年である4年次には、全学部・全学科で「卒業論文」が、必修科目として開講されており、本学で勉学してきた内容の総合的な応用力を身に着けることができます。
- 教養・リベラルアーツ教育?
-
 ●取り組みの内容本学における教養教育は、生命、食料、環境、健康、エネルギー、地域創成にかかわる学問分野を学修する学生に、より鋭い視点と広い視野を与える機会を設け、柔軟で論理的な思考法を身につけさせることにより、専門教育の成果を社会において最大限に発揮し、かつ心豊かな人生を実現できるようにするための教育を行います。
●取り組みの内容本学における教養教育は、生命、食料、環境、健康、エネルギー、地域創成にかかわる学問分野を学修する学生に、より鋭い視点と広い視野を与える機会を設け、柔軟で論理的な思考法を身につけさせることにより、専門教育の成果を社会において最大限に発揮し、かつ心豊かな人生を実現できるようにするための教育を行います。
教育方法
- アクティブラーニング?
-
 ●取り組みの内容各学部・学科ごとに特色のあるアクティブラーニングを実施しています。
●取り組みの内容各学部・学科ごとに特色のあるアクティブラーニングを実施しています。
全学的に実験・実習科目や演習科目が豊富であるため、フィールドワークやグループ討議の機会が多く設定されています。卒業論文は全学部・学科において必修科目であり、3年次より、研究室での指導が行われています。
- 課題解決型学習(PBL)?
-
 ●取り組みの内容学部・学科ごとに「実験」や「演習」、さらには「フィールドワーク」や「卒業論文」など様々な科目を通して「課題解決型学習(PBL)」の教育を行っています。
●取り組みの内容学部・学科ごとに「実験」や「演習」、さらには「フィールドワーク」や「卒業論文」など様々な科目を通して「課題解決型学習(PBL)」の教育を行っています。
- サービスラーニング?
-
 ●取り組みの内容キャンパスや学部ごとに、地域貢献を兼ねた特色のあるサービスラーニングを展開しています。
●取り組みの内容キャンパスや学部ごとに、地域貢献を兼ねた特色のあるサービスラーニングを展開しています。 - 少人数教育?
-
 ●取り組みの内容科目の特性に応じた適切な授業形態を採用し、授業の性質によってクラス分けを行うなどの工夫を行っています。少人数教育については、主に必修科目である英語科目において、習熟度別のクラス編成を行い少人数による授業を実施しています。また、学部・学科ごとに「実験」や「演習」、さらには「フィールドワーク」や「卒業論文」など様々な科目を通して少人数教育を展開し、単なる座学ではなく本当の実力が身に付く教育を行っています。
●取り組みの内容科目の特性に応じた適切な授業形態を採用し、授業の性質によってクラス分けを行うなどの工夫を行っています。少人数教育については、主に必修科目である英語科目において、習熟度別のクラス編成を行い少人数による授業を実施しています。また、学部・学科ごとに「実験」や「演習」、さらには「フィールドワーク」や「卒業論文」など様々な科目を通して少人数教育を展開し、単なる座学ではなく本当の実力が身に付く教育を行っています。
学びの支援
- 学びの組織的な支援?
-
 ●取り組みの内容全学部・学科において「クラス担任制度」を設けており、1年次に開講される「フレッシュマンセミナー」「共通演習」を始めとして、学期ごとに開催される「成績相談」や「大学と保護者との教育懇談会」を介した保護者との面談など様々な施策を通じて、学生の学びを組織的に支援しています。
●取り組みの内容全学部・学科において「クラス担任制度」を設けており、1年次に開講される「フレッシュマンセミナー」「共通演習」を始めとして、学期ごとに開催される「成績相談」や「大学と保護者との教育懇談会」を介した保護者との面談など様々な施策を通じて、学生の学びを組織的に支援しています。
- 学修成果のフィードバック?
-
 ●取り組みの内容講義や実験・演習などの科目においては、小テストや定期テスト、あるいは実験レポートなどの結果を学生に返却することで、学生自らが学修の成果を把握できるようにしています。また、毎年6月に各科目の評価及びGPAの記載された成績表は保護者に郵送されます。このことにより、保護者も修得単位数やGPAなどの学修成果を具体的に把握できるようにしています。
●取り組みの内容講義や実験・演習などの科目においては、小テストや定期テスト、あるいは実験レポートなどの結果を学生に返却することで、学生自らが学修の成果を把握できるようにしています。また、毎年6月に各科目の評価及びGPAの記載された成績表は保護者に郵送されます。このことにより、保護者も修得単位数やGPAなどの学修成果を具体的に把握できるようにしています。
- 初年次教育?
-
 ●取り組みの内容全学部・学科共通で「東京農業大学入門」及び「共通演習」を開講しています。「東京農業大学入門」では、充実した大学生活を過ごすために必要な知識・心得の修得、ならびに大学で修学することの目的と意味を具体的に理解します。また、グループディスカッションやプレゼンテーションなどを通じて、大学での自主的な学習法を修得します。
●取り組みの内容全学部・学科共通で「東京農業大学入門」及び「共通演習」を開講しています。「東京農業大学入門」では、充実した大学生活を過ごすために必要な知識・心得の修得、ならびに大学で修学することの目的と意味を具体的に理解します。また、グループディスカッションやプレゼンテーションなどを通じて、大学での自主的な学習法を修得します。
また、高等学校レベルの学習内容の補習的な科目として「基礎数学」「基礎化学」「基礎生物」「基礎物理」「文書表現」など、学科ごとに必要な科目を配当しています。
- 卒後調査の活用?
-
 ●取り組みの内容本学では、平成26年度より卒業年次生(学士課程)を対象とした、「卒業生アンケート」を実施しています。アンケート内容は、教育内容・教育研究環境・学生生活等において、身に付いた能力や満足度など集計し、学生の修学等の状況及び環境の見直し等に活用しています。
●取り組みの内容本学では、平成26年度より卒業年次生(学士課程)を対象とした、「卒業生アンケート」を実施しています。アンケート内容は、教育内容・教育研究環境・学生生活等において、身に付いた能力や満足度など集計し、学生の修学等の状況及び環境の見直し等に活用しています。
各実施年度の回答数(回答率)はそれぞれ、「2014(平成26)年度2,556(84.8%)」、「2015(平成27)年度2,402(82.3%)」、「2016(平成28)年度2,513(87.1%)」、「2017(平成29)年度2,517(83.8%)」)」、「2018(平成30)年度2,540(85.7%)」、「2019(令和元)年度2,274(76.8%)」、「2020(令和2)年度2,286(78.6%)」、「2021(令和3)年度1,955(66.5%)」、「2022(令和4)年度1,670(57.6%)」、「2023(令和5)年度1,945(68.5%)」です。 - 中途退学防止?
-
 ●取り組みの内容クラス担任による学生との面談、大学と保護者との教育懇談会を通じた保護者との面談、さらには、必修科目における出席状況の共有化やゼミ、卒業論文などにおける指導教員による学生との個人面談など、様々な方策を講じて中途退学の防止に努めています。
●取り組みの内容クラス担任による学生との面談、大学と保護者との教育懇談会を通じた保護者との面談、さらには、必修科目における出席状況の共有化やゼミ、卒業論文などにおける指導教員による学生との個人面談など、様々な方策を講じて中途退学の防止に努めています。
- TA・RA・SA・メンターの活用?
-
 ●取り組みの内容TAのガイドラインに沿って、学部ごとに「実験」「実習」や「演習」、さらには「フィールドワーク」や「卒業論文」など様々な科目を通してTAを活用しています。
●取り組みの内容TAのガイドラインに沿って、学部ごとに「実験」「実習」や「演習」、さらには「フィールドワーク」や「卒業論文」など様々な科目を通してTAを活用しています。 - 入学前教育?
-
 ●取り組みの内容総合型選抜、学校推薦型選抜による入学予定者を対象として、入学後、大学の授業をスムーズに受講できるように準備し、基礎学力を確かなものにすることを目的とした「入学前準備教育」を実施しています。
●取り組みの内容総合型選抜、学校推薦型選抜による入学予定者を対象として、入学後、大学の授業をスムーズに受講できるように準備し、基礎学力を確かなものにすることを目的とした「入学前準備教育」を実施しています。 - 特色ある教育施設・設備の整備?
-

- ラーニングコモンズ?
-
 ●取り組みの内容各キャンパス、図書館・講義棟や研究実験棟、さらには食堂や学生会館のオープンスペースなどを利用して、学生がグループ学習を行っています。また、食堂や数多くの教室では無線LAN環境が整備されており、学生同士の学びの場として活用されています。
●取り組みの内容各キャンパス、図書館・講義棟や研究実験棟、さらには食堂や学生会館のオープンスペースなどを利用して、学生がグループ学習を行っています。また、食堂や数多くの教室では無線LAN環境が整備されており、学生同士の学びの場として活用されています。
- 学生アンケートの活用?
-
 ●取り組みの内容前学期及び後学期において「授業評価および学修時間アンケート」を実施しており、アンケート結果は教員本人にフィードバックするだけでなく、教学検討委員長に報告され、授業評価結果の活用として、必要項目の数値が基準を下回った場合は、授業の改善報告書を作成・提出して頂くなど、授業改善に努めています。
●取り組みの内容前学期及び後学期において「授業評価および学修時間アンケート」を実施しており、アンケート結果は教員本人にフィードバックするだけでなく、教学検討委員長に報告され、授業評価結果の活用として、必要項目の数値が基準を下回った場合は、授業の改善報告書を作成・提出して頂くなど、授業改善に努めています。
- キャリア教育?
-
 ●取り組みの内容全学部・学科ではキャリア教育に関連する科目として「キャリアデザイン(一)」「キャリアデザイン(二)」を開講しています。キャリア教育は単なる就職支援だけなく、大学生活を通じた人間形成の教育として捉え、大学における勉学意識の向上や、社会人生活の紹介なども行っています。
●取り組みの内容全学部・学科ではキャリア教育に関連する科目として「キャリアデザイン(一)」「キャリアデザイン(二)」を開講しています。キャリア教育は単なる就職支援だけなく、大学生活を通じた人間形成の教育として捉え、大学における勉学意識の向上や、社会人生活の紹介なども行っています。
- 資格取得(国家資格受験資格)?
-
 ●取り組みの内容教員免許状、司書・学芸員、栄養士、管理栄養士を始めとして、各学部・学科で様々な特色のある資格が取得できるようになっています。
●取り組みの内容教員免許状、司書・学芸員、栄養士、管理栄養士を始めとして、各学部・学科で様々な特色のある資格が取得できるようになっています。
学修についての評価
- アセスメントポリシー?
-

- 外部テストの活用?
-
 ●取り組みの内容英語科目では、「TOEIC」や「GTELP」などの外部テストを導入することで基礎学力の確認をし、能力別にクラス編成を行っています。また、「TOEIC」の受験を意識した英語科目も設けています。
●取り組みの内容英語科目では、「TOEIC」や「GTELP」などの外部テストを導入することで基礎学力の確認をし、能力別にクラス編成を行っています。また、「TOEIC」の受験を意識した英語科目も設けています。
- GPAの活用?
-
 ●取り組みの内容全学部・学科においてGPAによる成績評価指標を導入しており、成績の順位付けや面談時における学修意欲の向上などに活用しています。
●取り組みの内容全学部・学科においてGPAによる成績評価指標を導入しており、成績の順位付けや面談時における学修意欲の向上などに活用しています。
- 成績評価の厳格な運用?
-
 ●取り組みの内容全学部・学科のシラバスにおいて、成績評価方法を明示しており、明示された評価方法に従って成績を算出しています。ただし、現在における成績算出方法は基本的には科目担当者に任されており、第三者による評価の厳密な運用などは今後の課題となっています。
●取り組みの内容全学部・学科のシラバスにおいて、成績評価方法を明示しており、明示された評価方法に従って成績を算出しています。ただし、現在における成績算出方法は基本的には科目担当者に任されており、第三者による評価の厳密な運用などは今後の課題となっています。
- 学修成果のフィードバック?
-
 ●取り組みの内容講義や実験・演習などの科目においては、小テストや定期テスト、あるいは実験レポートなどの結果を学生に返却することで、学生自らが学修の成果を把握できるようにしています。また、毎年6月に各科目の評価及びGPAの記載された成績表は保護者に郵送されます。このことにより、保護者も修得単位数やGPAなどの学修成果を具体的に把握できるようにしています。
●取り組みの内容講義や実験・演習などの科目においては、小テストや定期テスト、あるいは実験レポートなどの結果を学生に返却することで、学生自らが学修の成果を把握できるようにしています。また、毎年6月に各科目の評価及びGPAの記載された成績表は保護者に郵送されます。このことにより、保護者も修得単位数やGPAなどの学修成果を具体的に把握できるようにしています。
×
『教育内容の体系化とその充実』とは?
教育の目的や成果を明確に設定し、その達成のため、各授業間の関連性を明確にするなど、体系的な学びを可能にすることで、教育内容の一層の充実を図る取り組み。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『教養・リベラルアーツ教育』とは?
幅広い分野の教養などを身につけ、専門知識に偏らない汎用的能力を育成するために大学・短期大学で行われる教育。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『アクティブラーニング』とは?
一方的に講義を聴くスタイルの授業ではなく、学生が積極的に学修に参加することを取り入れ、能動的(アクティブ)な学びを促すことで、知識をしっかり定着させることを目的とした学習方法。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『課題解決型学習(PBL)』とは?
プロジェクト活動を通じ、学生が自主的・自律的に課題を発見・解決する過程において、それまでに得た知識を実践的に活用することや、より学びを深くすることなどを目的とした学習方法。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『サービスラーニング』とは?
地域社会における社会貢献活動等を体験するなかで、学んだ知識を社会で実践的に活用し、社会に対する責任感を育むことなどを通じて、より学習効果を高める体験型の学習方法。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『少人数教育』とは?
学習効果を高めるために、1人の教員が教える学生の数を少なくして授業を行う学習方法。
×
『学びの組織的な支援』とは?
学校側が組織的かつ恒常的に学びに対するサポート体制を用意し、授業に対する学生の不安を解消するなどの学びに対する様々な支援をすることで、より学習効果を高める取り組み。
×
『学修成果のフィードバック』とは?
授業や講義などを通して学生が学んだ知識や技術や成績などの「学修成果」を、可視化するなどして学生にわかりやすく還元することで、学生自らの学びへの姿勢を支援する取り組み。
×
『初年次教育』とは?
大学や短期大学の新入生を対象に、高校までの学びから、能動的な大学・短期大学での学びにスムーズに移行するための基本的なスキルなどを身につける教育プログラム。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『卒後調査の活用』とは?
卒業生を対象に、就職や進学などの状況や、学修成果の活用状況など、大学での学びの充実度などを調査し、その結果を教育方法やプログラムの改善などに活用する取り組み。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『中途退学防止』とは?
学びに対する意欲の減少などを理由に修業期間の途中で学校を退学しようとする学生に対して、学びのサポートを行うことで、教育の問題解決を図り、学びの環境を改善し、中途退学を防ぐ取り組み。
×
『TA・RA・SA・メンターの活用』とは?
大学院生による教育補助(TA)、大学院生等による研究補助(RA)、学生による教育補助(SA)、後輩を多方面で支援する先輩(メンター)を教育研究活動などに活用する取り組み。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『入学前教育』とは?
入学予定者(主にAO入試や各種推薦入試などで、早期に入学が決定した入学予定者)に対して、入学後の学びの準備や学習意欲の維持などのために、入学前に行う教育。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『特色ある教育施設・設備の整備』とは?
特別な校舎や教室、実習室などの教育施設や教室等にある機器などの設備を整備し活用することで、教育内容やプログラムの充実などに活かす取り組み。
×
『ラーニングコモンズ』とは?
学生の自主的・自律的な学習のため、電子情報や印刷物など様々な情報資源を使って議論などができる共有の「学習の場」。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『学生アンケートの活用』とは?
新入生や在学している学生に対し、大学の授業やカリキュラム、学修状況などについてアンケートを行い、その結果を分析・活用して、教育方法やプログラムの改善などに活かす取り組み。
×
『キャリア教育』とは?
大学や短期大学の学修プログラムの一環として、カリキュラムに社会人・職業人として必要な能力などを身に付けるための科目等を組み入れ、学生のキャリア形成計画や目標設定を支援する教育。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『資格取得(国家資格受験資格)』とは?
カリキュラムの整備や授業内容の工夫などを行い、学生が正課の授業を受けることで国家資格試験を受験し、合格することを目的に支援する取り組み。
×
『アセスメントポリシー』とは?
学生の学修成果の評価(アセスメント)について、目的や達成するべき質的水準と具体的な評価の実施方法などについて定めた学内の方針を活用した取り組み。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『外部テストの活用』とは?
TOEICやTOEFLといった学校の外部で行われているテストを、大学や短期大学の入試や単位認定などに活用する取り組み。
×
『GPAの活用』とは?
科目の成績評価に応じてポイント(例:5段階評価A〜Eに対し4〜0点等)を付与し、その平均点(Grade Point Average)による学習成果の評価方法を大学や短期大学での教育に活用する取り組み。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『成績評価の厳格な運用』とは?
明確な成績評価の基準を定めて厳格に運用して、単位取得や進級などを判定することで、教育の「質の保証」を実現する取り組み。
×
『学修成果のフィードバック』とは?
授業や講義などを通して学生が学んだ知識や技術、成績などの「学修成果」を活用し、学生の学びの振り返りを促すことで、学びの定着を図ることを目的とした取り組み。
公開イベント情報はすべて大学ホームページで事前に配信します。
オープンキャンパス(北海道オホーツク6/22、7/21、7/27、8/24、3/22)(外部サイトへ)
オープンキャンパス(厚木・世田谷8/3、8/4)(外部サイトへ)