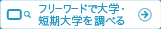東洋大学
東洋大学
生命科学研究科(博士)

- ディプロマポリシー
-
本学では、学部は各学科(又は専攻)ごとに、研究科は各専攻ごとに、ディプロマ・ポリシーを設定し、ホームページにて公表しています。
また、設定したディプロマ・ポリシーは、自己点検・評価により、定期的に見直しを行っています。詳細リンク(外部サイトへ) - カリキュラムポリシー
-
本学では、学部は各学科(又は専攻)ごとに、研究科は各専攻ごとに、カリキュラム・ポリシーを設定し、ホームページにて公表しています。
また、設定したカリキュラム・ポリシーは、自己点検・評価により、定期的に見直しを行っています。詳細リンク(外部サイトへ)
カリキュラム
- 教育内容の体系化とその充実?
-
 ●取り組みの内容本学は、「哲学教育」「国際化」「キャリア教育」を3つの柱とした「グローバル人財」の育成という目標に向けて、教養教育(基盤教育)と各学部・学科専門科目の教育課程を体系的に編成しています。また、各学部・学科では、カリキュラムの体系性を明らかにし、学生に適切な履修指導を行うために「主な科目の体系図」「カリキュラムの構造図」「履修モデル及び就職先」「科目展開図」「履修モデル」等を「履修要覧に掲載するとともに、シラバスにおいて、「関連分野・関連科目」の項目に、当該科目と他の授業科目との関係性を示すよう努めています。
●取り組みの内容本学は、「哲学教育」「国際化」「キャリア教育」を3つの柱とした「グローバル人財」の育成という目標に向けて、教養教育(基盤教育)と各学部・学科専門科目の教育課程を体系的に編成しています。また、各学部・学科では、カリキュラムの体系性を明らかにし、学生に適切な履修指導を行うために「主な科目の体系図」「カリキュラムの構造図」「履修モデル及び就職先」「科目展開図」「履修モデル」等を「履修要覧に掲載するとともに、シラバスにおいて、「関連分野・関連科目」の項目に、当該科目と他の授業科目との関係性を示すよう努めています。
大学院博士前期課程では、各研究科・専攻において、教育課程の中に、講義科目と研究指導(又は該当する演習科目)が位置づけられ、領域やコース等を設け、コースワークとリサーチワークを適切に組み合わせたカリキュラムを設けています。博士後期課程では、学位論文の作成等に対する指導(「研究指導」)にあたり、研究計画作成から、自らが決定した研究の課題・方法及び研究論文完成に至るまで、指導教員・副指導教員の研究指導体制で行われています。 - 教養・リベラルアーツ教育?
-
 ●取り組みの内容全学部の教養教育(基盤教育)の科目区分を、「哲学・思想」「自然・環境・生命」「日本と世界の文化・歴史」「現代・社会」「スポーツと健康」「総合」「社会人基礎科目」「留学支援科目」の8区分に統一し、本学が掲げる「哲学教育」「国際化」「キャリア教育」を3つの柱とした「グローバル人財」の育成という目標の実現を目指しています。
●取り組みの内容全学部の教養教育(基盤教育)の科目区分を、「哲学・思想」「自然・環境・生命」「日本と世界の文化・歴史」「現代・社会」「スポーツと健康」「総合」「社会人基礎科目」「留学支援科目」の8区分に統一し、本学が掲げる「哲学教育」「国際化」「キャリア教育」を3つの柱とした「グローバル人財」の育成という目標の実現を目指しています。
「哲学・思想」では自校教育科目「井上円了と東洋大学」を開設するほか、「自然・環境・生命」では自然科学系科目、「日本と世界の文化・歴史」「現代・社会」では、人文・社会科学系科目を開設しています。また、「総合」領域では、複数の学問視点から共通の課題について講義するなど、教養教育(基盤教育)を通して、思考力・判断力のための一般的知識の習得や知的能力を発展させる科目を開設しています。
また、2012年度より、白山キャンパスより約20分で移動が可能な板橋区清水町に、学生の運動・体育施設として総合スポーツセンターを設置し、各種スポーツの練習場や屋内プール、グラウンド等を有しており、「スポーツと健康」領域の充実にも力を注いでいます。
教育方法
- アクティブラーニング?
-
 ●取り組みの内容本学では、主に各学部・学科の専門科目内での少人数授業においてアクティブ・ラーニング形式の授業が展開されています。特にゼミナール形式の演習科目を中心に採用され、教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、能動的な学修への参加を取り入れた授業を行っています。大学院では、フィールドワーク、調査研究、グループ・ディスカッション、グループ・ワークを授業や研究指導を通じて実施しています。
●取り組みの内容本学では、主に各学部・学科の専門科目内での少人数授業においてアクティブ・ラーニング形式の授業が展開されています。特にゼミナール形式の演習科目を中心に採用され、教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、能動的な学修への参加を取り入れた授業を行っています。大学院では、フィールドワーク、調査研究、グループ・ディスカッション、グループ・ワークを授業や研究指導を通じて実施しています。
施設面の機能としては、学生の能動的な学修へのサポートとして、各キャンパスの図書館内にラーニング・コモンズもしくはグループ学習室を設置しています。インターネット環境と従来の図書館資料を有効に使い、学生同士がともに考え、ディスカッションをし、情報発信をする場としての学修空間を用意しています。また一部のPC教室でアクティブ・ラーニング形態を採用することができるよう、整備を行っています。
また、2014年7月に「教育改善シンポジウム」として、学修支援室の活用とアクティブ・ラーニングの実践事例発表のFD研修会を開催し、教員へのアクティブラーニングの教授法修得に向けて取り組みました。 - 課題解決型学習(PBL)?
-
 ●取り組みの内容本学での課題解決型学習は、正課内授業科目において、主に学部・学科の専門科目内に開設する演習科目や実習科目にて取り入れています。その内容は学部により異なりますが、グループで課題解決に向けて討議し、観察、対話、交渉、検証などを重ね、体験を通じて問題解決能力を身につけるよう取り組んでいます。
●取り組みの内容本学での課題解決型学習は、正課内授業科目において、主に学部・学科の専門科目内に開設する演習科目や実習科目にて取り入れています。その内容は学部により異なりますが、グループで課題解決に向けて討議し、観察、対話、交渉、検証などを重ね、体験を通じて問題解決能力を身につけるよう取り組んでいます。
正課外の取り組みとしては、グローバル・キャリア教育センター(GCC)によるキャリア形成支援として、企業や自治体および他大学と協働でPBL型講座を実施するなど、企業理解をきっかけに社会への興味関心を引き出しています。具体的には、企業の課題について課題解決や調査を行い、調査・分析・ディスカッションを中心にしたリサーチを実施した後、企業へ報告提案を行うものや、埼玉県の施策協力依頼を受け、立教大学・早稲田大学・東洋大学の3大学が埼玉県内の各企業や働く人々を取材し、広く埼玉県内の企業の魅力を伝える取り組みを実施しています。そのほか、2014年度には、「思考力向上プロジェクト」講座を実施しました。これらの活動は、経済産業省「社会人基礎力を育成する授業30選」にも採択されています。 - サービスラーニング?
-
 ●取り組みの内容本学のサービスラーニングは、主に正課内外の「ボランティア活動」による社会奉仕活動を体験することがメインとなっています。
●取り組みの内容本学のサービスラーニングは、主に正課内外の「ボランティア活動」による社会奉仕活動を体験することがメインとなっています。
一部の学部・学科・研究科のカリキュラムのなかに、ボランティア活動を正課科目として設けています。事前事後の指導のもと行われ、ボランティア活動を通して、専門科目の知識の修得に役立てるとともに、社会奉仕の精神を養うことを目的としています。
学部・研究科によっては、専門科目の授業内でサービスラーニングが取り入れられているほか、国連ユースボランティア、JICAボランティア(青年海外協力隊/シニア海外ボランティア)、その他海外ボランティアなどの取り組みを実施しています。
また、海外ボランティアを行う学生への奨学金制度も設けています。 - 少人数教育?
-
 ●取り組みの内容主に各学部・学科の専門科目の教育課程において、演習科目や外国語科目において少人数制(30名程度)が採用されています。そのほか必要に応じて、授業教室内に教育補助員(TA、SA)を配置しており、各科目の学修目標の到達に向けて、適した教育環境となるよう1クラスにおける学生数に配慮して取り組んでいます。
●取り組みの内容主に各学部・学科の専門科目の教育課程において、演習科目や外国語科目において少人数制(30名程度)が採用されています。そのほか必要に応じて、授業教室内に教育補助員(TA、SA)を配置しており、各科目の学修目標の到達に向けて、適した教育環境となるよう1クラスにおける学生数に配慮して取り組んでいます。
学びの支援
- 学びの組織的な支援?
-
 ●取り組みの内容各キャンパスに学修支援室等を整備しています。白山キャンパスでは、レポート・論文の書き方相談、文献・資料の調べ方相談をはじめ、語学系資格取得支援や基礎学力向上に係る支援などに取り組み、川越キャンパスでは、「基礎科目(数学・物理)」と「英語」のほか、基礎学力向上に係る内容についてもサポートしています。朝霞キャンパスでは、専任教員(助教)とボランティアの大学院学生が基礎科目から専門分野までの学修支援を行っており、大学の授業補習のほか、化学の計算問題を解く勉強会や国家試験の模擬試験、英語の特別授業なども行っています。朝霞キャンパスのラーニングサポートセンターでは、TOEICに関する相談など、英語学習のサポートを中心に行っています。大学院では、留学生に対する日本語指導、その他、支援に必要な事項(履修登録等)を行う、「大学院チューター制度」があります。
●取り組みの内容各キャンパスに学修支援室等を整備しています。白山キャンパスでは、レポート・論文の書き方相談、文献・資料の調べ方相談をはじめ、語学系資格取得支援や基礎学力向上に係る支援などに取り組み、川越キャンパスでは、「基礎科目(数学・物理)」と「英語」のほか、基礎学力向上に係る内容についてもサポートしています。朝霞キャンパスでは、専任教員(助教)とボランティアの大学院学生が基礎科目から専門分野までの学修支援を行っており、大学の授業補習のほか、化学の計算問題を解く勉強会や国家試験の模擬試験、英語の特別授業なども行っています。朝霞キャンパスのラーニングサポートセンターでは、TOEICに関する相談など、英語学習のサポートを中心に行っています。大学院では、留学生に対する日本語指導、その他、支援に必要な事項(履修登録等)を行う、「大学院チューター制度」があります。
また、学生の学修時間の確保に向けて、授業支援システムとしてToyoNet-ACEを構築しており、授業ごとに資料や動画のコンテンツ、ディスカッションする掲示板、小テストやレポートなどを課す機能により、学生の事前事後学修や主体的な学習に役立てています - 学修成果のフィードバック?
-
 ●取り組みの内容本学では、授業科目のシラバスに各教員が講義の目的・内容、到達目標(学習成果)、講義スケジュール(各回の授業内容)を、具体的に記載することを求めています。また、成績評価基準も明示し、到達目標の達成状況を成績評価へと反映させています。
●取り組みの内容本学では、授業科目のシラバスに各教員が講義の目的・内容、到達目標(学習成果)、講義スケジュール(各回の授業内容)を、具体的に記載することを求めています。また、成績評価基準も明示し、到達目標の達成状況を成績評価へと反映させています。
各学部・学科では、成績結果をもとに、単位修得僅少者や成績不振の学生や保護者に対して、面談等を行い、今後の学修計画の立て直しを行っています。さらに、各キャンパスに設けられている学修支援室等が学生個人の学修支援を行うなど、さまざまなサポート体制をとっています。
そのほか、科目の履修を通じた学修成果を測るものとして、卒業時アンケートを実施・公表しています。アンケート項目では、哲学的な思考、国際的な視野、日本の文化と歴史の理解、多文化・異文化に関する知識、人類の文化・社会と自然に関する知識、コミュニケーション・スキル、数字やデータによる把握・分析力、情報リテラシー、論理的思考力、問題解決力、自己管理力、チームワーク、リーダーシップ、倫理観、市民としての社会的責任、生涯学習力を、学生自身による自己評価を行い、学修成果を測定しています。 - 学修ポートフォリオ?
-
 ●取り組みの内容本学では、学生の学修過程ならびに各種の学修成果を長期にわたって収集し、記録したもの、いわゆる学修ポートフォリオを一部の学部・学科で採用しています。
●取り組みの内容本学では、学生の学修過程ならびに各種の学修成果を長期にわたって収集し、記録したもの、いわゆる学修ポートフォリオを一部の学部・学科で採用しています。
文学部教育学科初等教育専攻、国際地域学部がe-ポートフォリオを導入し、学修過程を含めて到達度を評価し、次に取り組むべき課題を見つけてステップアップを図ることで、学生自身の自己省察を可能とすることにより、自律的な学修を促しています。 - 初年次教育?
-
 ●取り組みの内容初年次教育については、各学部・学科ごとに4月から5月にかけて、オリエンテーションやフレッシャーズ・キャンプ等を通じて、学部学科の教育方針への共通理解を深め、一体感や大学への帰属意識を形成すること、また本学の哲学教育・国際化・キャリア教育等の方針についても学生に浸透するように、大学の教育目標への理解浸透を促しています。
●取り組みの内容初年次教育については、各学部・学科ごとに4月から5月にかけて、オリエンテーションやフレッシャーズ・キャンプ等を通じて、学部学科の教育方針への共通理解を深め、一体感や大学への帰属意識を形成すること、また本学の哲学教育・国際化・キャリア教育等の方針についても学生に浸透するように、大学の教育目標への理解浸透を促しています。 - 卒後調査の活用?
-
 ●取り組みの内容本学では、一定の社会経験を経た卒業生に大学教育を振り返って評価してもらうことを目的として、2007年度と2012年度に、外部団体により本学の卒業生を対象とした「大学の教育力に関するアンケート」を実施しました。
●取り組みの内容本学では、一定の社会経験を経た卒業生に大学教育を振り返って評価してもらうことを目的として、2007年度と2012年度に、外部団体により本学の卒業生を対象とした「大学の教育力に関するアンケート」を実施しました。
調査内容は「社会に出て、大学の教育の成果として役立った能力や知識」「大学での教育や生活で次のような能力や知識がどの程度修得できたか」などにより、卒業後の視点からの教育環境の評価を募り、その結果の分析を行いました。
アンケートの結果として、本学の教育は、首都圏主要大学と比較すると、「人間形成」「卒業後の仕事や生活に役立っている」などの点で高い数値が出ている反面、「海外留学制度が充実」「外国語学習に積極的である」「資格取得のサポートに積極的」などの点ではより充実した内容の見直しが求められる結果となっています。
このアンケートの結果について、卒業時アンケートと同様、本学の様々な会議での説明に加えて、教職員へ評価結果の説明会を開催するなど、大学の改革・改善に資するよう取り組んでいます。 - 中途退学防止?
-
 ●取り組みの内容本学では、学生の学修に支障がないよう、また意欲のある学生がさらに学習を進めていくことができるよう、各キャンパスに学修支援室等を整備し、その学生ニーズに応じた取り組みを進め、学生の成長及び学生満足度の向上と、卒業率の上昇、退学率・原級率の低下、授業運営の効率化を図っています。
●取り組みの内容本学では、学生の学修に支障がないよう、また意欲のある学生がさらに学習を進めていくことができるよう、各キャンパスに学修支援室等を整備し、その学生ニーズに応じた取り組みを進め、学生の成長及び学生満足度の向上と、卒業率の上昇、退学率・原級率の低下、授業運営の効率化を図っています。
また、各学期(春・秋)の成績表交付後に、成績不振者や保護者等に対して学部教員による面接を行い、学修計画の見直しを図っています。
留年(原級)・休学・退学者については、ゼミナール担当教員などの面接などを経て、休学・退学者の理由の把握に努めています。さらに、保護者等の保証人に対しても、成績表を送付する取り組みや、保護者会である「甫水会」の支部総会懇談会において、保護者と大学職員が、当該学生の成績表を基に個別面談を実施し、学生の修学を側面からも支援しています。 - TA・RA・SA・メンターの活用?
-
 ●取り組みの内容本学の教育支援体制として、「東洋大学における学部学生の教育指導の充実、向上と本学大学院学生の教育研究奨励の推進」を目的として、教育補助員(ティーチング・アシスタント、以下TA)を配置しています。TAは、学部において必要と認める授業科目の補助、学生に対する学習上の相談および指導、その他学部において特に必要と認める教育補助を中心に活動しています。
●取り組みの内容本学の教育支援体制として、「東洋大学における学部学生の教育指導の充実、向上と本学大学院学生の教育研究奨励の推進」を目的として、教育補助員(ティーチング・アシスタント、以下TA)を配置しています。TAは、学部において必要と認める授業科目の補助、学生に対する学習上の相談および指導、その他学部において特に必要と認める教育補助を中心に活動しています。
TAに対しては、その質の維持・向上のために、毎年4月に、FD推進センターにおいて、講演とワークショップによるTA研修会を実施するとともに、『TAハンドブック』を作成・配付し、教員と学生とをつなぐ教育補助員としてのTAの役割や責任について理解を深めてもらうことで、教育支援体制の充実に向けて取り組んでいます。
また、TAの他、教員の授業運営のサポートとして、学部学生をSA(スチューデント・アシスタント)として採用し、TAに準じた業務を行うほか、学部・学科の教育内容に応じて、実習指導助手及び技術員、機器利用支援スタッフ、教育研究支援職員等を配置しています。そのほか、一部の学部や研究科では、留学生の学修・生活を支援するチューター制度を採用しています。 - 入学前教育?
-
 ●取り組みの内容本学では、学部推薦入試合格者を中心に入学前教育を実施しています。
●取り組みの内容本学では、学部推薦入試合格者を中心に入学前教育を実施しています。
内容は、学部により、独自のe-learningシステム(インターネットを用いた課題学習)による学習、独自のレポート課題の提示、外部と提携した通信教育教材の紹介等を入学前の学生に課して、入学後の学習がスムーズに進められるよう支援しています。
なお、その効果を各学部で測定したり、2013年度には、経済学部が導入しているe-learningシステムを、希望する他学部にも展開したりするなど、逐次、その成果の検証や見直しを行っています。 - 特色ある教育施設・設備の整備?
-
 ●取り組みの内容4キャンパスにそれぞれ大・中・小の講義室や演習室、各種実験室、PC教室、図書館、体育施設のほか、さまざまな教育施設・設備を有しています。
●取り組みの内容4キャンパスにそれぞれ大・中・小の講義室や演習室、各種実験室、PC教室、図書館、体育施設のほか、さまざまな教育施設・設備を有しています。
白山キャンパスには、書道室やアクティブ・ラーニング型のPC教室、井上円了ホールや井上円了記念博物館、学部実習室、国際センターや研究センターなどが設置されています。
川越キャンパスには、学習支援室のある図書館・メディアセンター棟、一人ひとりデスクがある建築学科製図室(通称アトリエ)、物創り工房、スタジオやミニシアター、工業技術研究所、バイオ・ナノエレクトロニクス研究センターなどが設置されています。
朝霞キャンパスには、保育・介護実習室や、健康スポーツ学実験室、木工・金工・計測などの各種工房、製図・作業スタジオが設置された人間環境デザイン学科実験工房棟があります。
板倉キャンパスには、生命環境科学研究センター、実験データの集約・解析、学生同士が共同研究する場として18のコラボレーションスペースを有する実験棟があります。
総合スポーツセンター(東京都板橋区清水町)では、白山および板倉キャンパスの一部の体育授業や学生の課外活動に使用しています。 - ラーニングコモンズ?
-
 ●取り組みの内容白山キャンパスの図書館内に設置されたラーニング・コモンズには、学生の主体的または多様な学習を支援するため、人数や目的に合わせて自由にレイアウトして、会話やディスカッションすることができるラーニング・フォレストや、グループ学習室、学習PC室があります。
●取り組みの内容白山キャンパスの図書館内に設置されたラーニング・コモンズには、学生の主体的または多様な学習を支援するため、人数や目的に合わせて自由にレイアウトして、会話やディスカッションすることができるラーニング・フォレストや、グループ学習室、学習PC室があります。
この図書館内にあるラーニング・コモンズにより、図書館資料(冊子体・データベース)を有効に活用し、学習や研究内容を学生同士でディスカッションできる環境が整えられました。また、川越・朝霞キャンパス図書館内にも同様のラーニング・コモンズの設置や施設のリニューアルをしており、本学全体としてさらなる学びの支援を進めています。 - 学生アンケートの活用?
-
 ●取り組みの内容本学では、新入生アンケート、授業評価アンケート、卒業時アンケートを主として実施しており、教育・学生支援環境の改善および発展に役立てています。
●取り組みの内容本学では、新入生アンケート、授業評価アンケート、卒業時アンケートを主として実施しており、教育・学生支援環境の改善および発展に役立てています。
新入生アンケートと卒業時アンケートについては、建学の精神、学部・学科の教育目標への理解度、施設・設備、学修支援などの教育環境へのニーズ調査、授業履修に関する理解度など、入学時と卒業時に学生による自己評価を行い、大学全体および各学部・学科の教育環境の改善に役立てています。
授業評価アンケートについては、学部・研究科ごとにアンケート対象科目の計画を立てて、毎年実施しています。取りまとめられたアンケート結果は、教員個人へ返却し、結果を踏まえた所見を作成して提出するよう、教育改善に生かすことを義務付けています。さらに、一部の学部・研究科では教育改善レポートなどを提出し、公表するなど、より良い教育環境の構築へ向けて取り組んでいます。 - インターンシップ?
-
 ●取り組みの内容本学におけるインターンシップに関わる取り組みは、各学部・学科の専門科目の中にキャリア教育として、「インターンシップ」「地域活動実習」「国際活動実習」などの科目を設置しているほか、学部独自に体制を整備し、講演会や卒業生との交流プログラムなどを実施しています。正課内のインターンシップについては、所定の基準に達した場合、単位として認められます。
●取り組みの内容本学におけるインターンシップに関わる取り組みは、各学部・学科の専門科目の中にキャリア教育として、「インターンシップ」「地域活動実習」「国際活動実習」などの科目を設置しているほか、学部独自に体制を整備し、講演会や卒業生との交流プログラムなどを実施しています。正課内のインターンシップについては、所定の基準に達した場合、単位として認められます。 - キャリア教育?
-
 ●取り組みの内容本学では2012年度の創立125周年を契機に、「哲学教育」「国際化」「キャリア教育」を3つの柱とした「グローバル人財の育成」を目標に掲げており、柱のひとつとして位置付けられた「キャリア教育」は、正課内外に幅広く展開しています。正課内としては、教養教育(基盤教育)の科目区分のひとつとして「社会人基礎科目」を設定し、「キャリアディベロップメント論」「社会人基礎力入門講義」「社会人基礎力実践講義」「企業の仕組み」など、1年次からキャリアを考えさせる科目を体系的に配置しています。また、各学部・学科の専門科目として、インターンシップやボランティアを扱う科目も増加しています。
●取り組みの内容本学では2012年度の創立125周年を契機に、「哲学教育」「国際化」「キャリア教育」を3つの柱とした「グローバル人財の育成」を目標に掲げており、柱のひとつとして位置付けられた「キャリア教育」は、正課内外に幅広く展開しています。正課内としては、教養教育(基盤教育)の科目区分のひとつとして「社会人基礎科目」を設定し、「キャリアディベロップメント論」「社会人基礎力入門講義」「社会人基礎力実践講義」「企業の仕組み」など、1年次からキャリアを考えさせる科目を体系的に配置しています。また、各学部・学科の専門科目として、インターンシップやボランティアを扱う科目も増加しています。 - 資格取得(国家資格受験資格)?
-
 ●取り組みの内容本学では、教職課程や公務員、公認会計士や社会福祉士などの専門資格まで、幅広い分野における資格取得をフォローしています。
●取り組みの内容本学では、教職課程や公務員、公認会計士や社会福祉士などの専門資格まで、幅広い分野における資格取得をフォローしています。
所定の科目の単位を修得することで得られる資格や、上記に加えて卒業を要する資格、さらには、受験資格が得られるものなどがあります。学部・学科・専攻ごとに、取得可能な資格が異なりますので、本学WEBページにある、「取得可能資格一覧」を参照してください。
なお、教員採用試験対策などの支援体制として、各キャンパスに「教職支援室」が設けられています。面接や試験対策に向けてきめ細かい支援を行っています。
学修についての評価
- 外部テストの活用?
-
 ●取り組みの内容2012年度より、全学部生に対して最低年1回TOEICテストの無料受験の機会を提供しており、TOEICのスコアを基準とした「海外留学促進奨学金制度」の運用につなげており、スコア結果は、授業科目のクラス編成などに用いています。なお、TOEICテストで一定のスコアを獲得した学生には、希望制でTOEIC SWテストの割引の受験機会を提供しています。
●取り組みの内容2012年度より、全学部生に対して最低年1回TOEICテストの無料受験の機会を提供しており、TOEICのスコアを基準とした「海外留学促進奨学金制度」の運用につなげており、スコア結果は、授業科目のクラス編成などに用いています。なお、TOEICテストで一定のスコアを獲得した学生には、希望制でTOEIC SWテストの割引の受験機会を提供しています。
そのほか、TOEIC、TOEFL、IELTS、国連英検、ケンブリッジ英検等の語学試験の獲得スコアに準じて、学部規則に準じて単位認定を行っています。
英語等の語学試験以外においても、各学部の取り組みのなかで資格取得等に向けた外部テストを実施しています。
また、キャリア形成支援として、入学時に自己理解と可能性開発のためのアセスメントテスト(PROGテスト)や、学生が多様な選択肢から自分に合った進路を選択するための情報提供を目的に、アセスメントテスト(R-CAP適職診断テスト)を、全学部で実施しています。1年生アセスメントと同様にフォロー講座を実施しそれぞれの活用を図るとともに、学生指導にも役立てています。 - GPAの活用?
-
 ●取り組みの内容2013年度の入学生より、通学課程の全学部共通でGPA制度を導入しました。現在、第2学年に在籍する学生まで適用されています。
●取り組みの内容2013年度の入学生より、通学課程の全学部共通でGPA制度を導入しました。現在、第2学年に在籍する学生まで適用されています。
GPAの活用方法として、現在は、学生の成績表にGPA値を記載することや、給付型奨学金や成績優秀者への表彰金の審査基準に用いています。導入に際しては、教員への成績評価の厳正化に向けた理解向上のため、「GPAリーフレット」を配布し、学生には「履修要覧」にて、周知をしています。
また、全学として、学部・学科・学年別のGPA値のデータ構築や、成績分布の集計・分析を開始しており、GPAを活用した学生の学修に対する取り組みを進めています。 - 成績評価の厳格な運用?
-
 ●取り組みの内容授業科目の成績評価については、各教員が成績評価方法、評価基準をシラバスに記載し、学生に明示することを求めています。 また、2013年度の入学生より、全学部共通でGPA制度を導入しました。
●取り組みの内容授業科目の成績評価については、各教員が成績評価方法、評価基準をシラバスに記載し、学生に明示することを求めています。 また、2013年度の入学生より、全学部共通でGPA制度を導入しました。
成績発表後に学生がシラバスに記載されている成績評価基準を満たしているものの、成績評価が間違っていると思われるに十分な理由がある場合には、科目担当教員に成績評価に間違いがないか確認することができる「成績調査」の制度を全学的に設けており、現在は、学務システムであるToyoNet-G上で、学生が調査の依頼とその結果の確認をすることが可能となっています。 - 学修ポートフォリオ?
-
 ●取り組みの内容本学では、学生の学修過程ならびに各種の学修成果を長期にわたって収集し、記録したもの、いわゆる学修ポートフォリオを一部の学部・学科で採用されており、文学部教育学科初等教育専攻、国際地域学部ではe-ポートフォリオを導入しています。
●取り組みの内容本学では、学生の学修過程ならびに各種の学修成果を長期にわたって収集し、記録したもの、いわゆる学修ポートフォリオを一部の学部・学科で採用されており、文学部教育学科初等教育専攻、国際地域学部ではe-ポートフォリオを導入しています。
学修過程を含めて到達度を評価し、次に取り組むべき課題をみつけてステップアップを図ることで、学生自身の自己省察を可能とすることにより、自律的な学修を促しています。
×
『教育内容の体系化とその充実』とは?
教育の目的や成果を明確に設定し、その達成のため、各授業間の関連性を明確にするなど、体系的な学びを可能にすることで、教育内容の一層の充実を図る取り組み。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『教養・リベラルアーツ教育』とは?
幅広い分野の教養などを身につけ、専門知識に偏らない汎用的能力を育成するために大学・短期大学で行われる教育。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『アクティブラーニング』とは?
一方的に講義を聴くスタイルの授業ではなく、学生が積極的に学修に参加することを取り入れ、能動的(アクティブ)な学びを促すことで、知識をしっかり定着させることを目的とした学習方法。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『課題解決型学習(PBL)』とは?
プロジェクト活動を通じ、学生が自主的・自律的に課題を発見・解決する過程において、それまでに得た知識を実践的に活用することや、より学びを深くすることなどを目的とした学習方法。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『サービスラーニング』とは?
地域社会における社会貢献活動等を体験するなかで、学んだ知識を社会で実践的に活用し、社会に対する責任感を育むことなどを通じて、より学習効果を高める体験型の学習方法。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『少人数教育』とは?
学習効果を高めるために、1人の教員が教える学生の数を少なくして授業を行う学習方法。
×
『学びの組織的な支援』とは?
学校側が組織的かつ恒常的に学びに対するサポート体制を用意し、授業に対する学生の不安を解消するなどの学びに対する様々な支援をすることで、より学習効果を高める取り組み。
×
『学修成果のフィードバック』とは?
授業や講義などを通して学生が学んだ知識や技術や成績などの「学修成果」を、可視化するなどして学生にわかりやすく還元することで、学生自らの学びへの姿勢を支援する取り組み。
×
『学修ポートフォリオ』とは?
授業を通じた学生の学びの過程や成果(学習計画表やレポート・成績表など)を記録し、それらを評価することで学びの振り返りを行い、学生が自ら学ぶことを支援する取り組み。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『初年次教育』とは?
大学や短期大学の新入生を対象に、高校までの学びから、能動的な大学・短期大学での学びにスムーズに移行するための基本的なスキルなどを身につける教育プログラム。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『卒後調査の活用』とは?
卒業生を対象に、就職や進学などの状況や、学修成果の活用状況など、大学での学びの充実度などを調査し、その結果を教育方法やプログラムの改善などに活用する取り組み。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『中途退学防止』とは?
学びに対する意欲の減少などを理由に修業期間の途中で学校を退学しようとする学生に対して、学びのサポートを行うことで、教育の問題解決を図り、学びの環境を改善し、中途退学を防ぐ取り組み。
×
『TA・RA・SA・メンターの活用』とは?
大学院生による教育補助(TA)、大学院生等による研究補助(RA)、学生による教育補助(SA)、後輩を多方面で支援する先輩(メンター)を教育研究活動などに活用する取り組み。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『入学前教育』とは?
入学予定者(主にAO入試や各種推薦入試などで、早期に入学が決定した入学予定者)に対して、入学後の学びの準備や学習意欲の維持などのために、入学前に行う教育。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『特色ある教育施設・設備の整備』とは?
特別な校舎や教室、実習室などの教育施設や教室等にある機器などの設備を整備し活用することで、教育内容やプログラムの充実などに活かす取り組み。
×
『ラーニングコモンズ』とは?
学生の自主的・自律的な学習のため、電子情報や印刷物など様々な情報資源を使って議論などができる共有の「学習の場」。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『学生アンケートの活用』とは?
新入生や在学している学生に対し、大学の授業やカリキュラム、学修状況などについてアンケートを行い、その結果を分析・活用して、教育方法やプログラムの改善などに活かす取り組み。
×
『インターンシップ』とは?
自らの専攻や将来のキャリアに関連した就業体験や社会貢献活動に参加する制度を授業やカリキュラムに取り込むことで、学生が学問や研究分野への理解をより深めるための取り組み。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『キャリア教育』とは?
大学や短期大学の学修プログラムの一環として、カリキュラムに社会人・職業人として必要な能力などを身に付けるための科目等を組み入れ、学生のキャリア形成計画や目標設定を支援する教育。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『資格取得(国家資格受験資格)』とは?
カリキュラムの整備や授業内容の工夫などを行い、学生が正課の授業を受けることで国家資格試験を受験し、合格することを目的に支援する取り組み。
×
『外部テストの活用』とは?
TOEICやTOEFLといった学校の外部で行われているテストを、大学や短期大学の入試や単位認定などに活用する取り組み。
×
『GPAの活用』とは?
科目の成績評価に応じてポイント(例:5段階評価A〜Eに対し4〜0点等)を付与し、その平均点(Grade Point Average)による学習成果の評価方法を大学や短期大学での教育に活用する取り組み。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『成績評価の厳格な運用』とは?
明確な成績評価の基準を定めて厳格に運用して、単位取得や進級などを判定することで、教育の「質の保証」を実現する取り組み。
×
『学修ポートフォリオ』とは?
学生が授業を通じた学びの過程や成果(学習計画表や成績表など)を記録し、それらを評価に活用し、成果だけでなく過程も含めた学修の評価を行うことで、一層の学びの定着を図る取り組み。
用語辞典を開いて詳しく調べる
東洋大学イベントカレンダー
東洋大学公開講座詳細ページ
生命科学研究科に関する新着情報はこちらからご覧いただけます。
「2013年度 材料技術研究協会討論会」で東洋大学生命科学研究科の2名がゴールドポスター賞を受賞しました
栄養飢餓ストレスによって活性化する神経保護機構を発見しました。
生命科学研究科で3Dプリンターを導入しました。
第10回国際極限環境微生物会議にて生命科学研究科の学生が若手ポスター賞を受賞しました。
11月26日に東洋大学生命環境科学研究センター開設記念シンポジウムを開催します。
- 文学部
- 経済学部
- 文学部(二)
- 法学部
- 法学部(二)
- 経済学部(二)
- 社会学部
- 社会学部(二)
- 理工学部
- 経営学部(二)
- 経営学部
- 生命科学部
- 総合情報学部
- 食環境科学部
- 国際学部
- 国際観光学部
- 情報連携学部
- 福祉社会デザイン学部
- 健康スポーツ科学部
- ライフデザイン学部
- 法学部(通)(募集停止)
- 文学部(通)(募集停止)
- 国際地域学部(募集停止)
- 文学研究科(修士)
- 文学研究科(博士)
- 社会学研究科(修士)
- 社会学研究科(博士)
- 法学研究科(修士)
- 法学研究科(博士)
- 経営学研究科(修士)
- 経済学研究科(修士)
- 経済学研究科(博士)
- 経営学研究科(博士)
- 生命科学研究科(修士)
- 生命科学研究科(博士)
- 経営学研究科(修士)(二)
- 経営学研究科(博士)(二)
- 理工学研究科(修士)
- 理工学研究科(博士)
- 総合情報学研究科(修士)
- 食環境科学研究科(修士)
- 情報連携学研究科(修士)
- 国際学研究科(修士)
- 国際観光学研究科(修士)
- 社会福祉学研究科(修士)
- ライフデザイン学研究科(修士)
- ライフデザイン学研究科(博士)
- 総合情報学研究科(博士)
- 国際学研究科(博士)
- 国際観光学研究科(博士)
- 社会福祉学研究科(博士)
- 食環境科学研究科(博士)
- 情報連携学研究科(博士)
- 健康スポーツ科学研究科(修士)
- 健康スポーツ科学研究科(博士)
- 国際地域学研究科(博士)(募集停止)
- 福祉社会デザイン研究科(修士)(募集停止)
- 福祉社会デザイン研究科(博士)(募集停止)