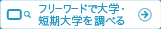�����
�����
ʸ����

������������
- ��������������
-
 ������Ȥߤ�����ʸ�����Ǥϸ��ߡ�����������α���������Ҥ��Ƥ��ޤ������̤Ǥ����ȴڹ�Ǥ������Τۤ�����ǯ�������ζ��깻��ꡢ��α�������������Ƥ��ޤ���
������Ȥߤ�����ʸ�����Ǥϸ��ߡ�����������α���������Ҥ��Ƥ��ޤ������̤Ǥ����ȴڹ�Ǥ������Τۤ�����ǯ�������ζ��깻��ꡢ��α�������������Ƥ��ޤ���
α�ػٱ�
- ����α�ء������ǥ������֥�������
-
 ������Ȥߤ����������θ���ϸ�������Ǥʤ�����ʸ��������ݴ��Ф��������뤳�Ȥ���Ū�ˡ����������ϰ��û����Ĺ����α�إץ�������»ܤ��Ƥ��ޤ������������оݤȤ����ץ������Σ�������ǯ�٤μ»ܳ����ϰʲ����̤�Ǥ���
������Ȥߤ����������θ���ϸ�������Ǥʤ�����ʸ��������ݴ��Ф��������뤳�Ȥ���Ū�ˡ����������ϰ��û����Ĺ����α�إץ�������»ܤ��Ƥ��ޤ������������оݤȤ����ץ������Σ�������ǯ�٤μ»ܳ����ϰʲ����̤�Ǥ���
��Ĺ��α�ء�����˴�Ť��������������ϰ裳����ؤȤθ�α�ء��ɸ���α����������̾��������α����������̾��
��û��α�ء�������ǤΡ�����֤�û��α�ءʻ��ó���������̾�ˤϡ������ʲҤˤ��������ߤˤʤ�ޤ�����
Ĺ��α�ءʸ�α�ءˤǤϡ�α�س��ϸ��������Ū��Ϣ�����ꡢ����Ȥ��Ƥ�����̤����Ƥ��ޤ���
û��α�ؤˤ����Ƥϡ�����Ϥθ���Ȱ�ʸ���������Ȥ���ץ�������»ܤ��Ƥ��ޤ����ޤ����ץ�����೫�ϸ�콵�����١�������Ʊ�Ԥ������Ϥ˽���������Ȥ��Ƥ��ޤ���
�����ʲҤˤ�곤���Ȥα��褬���¤���Ƥ��뤿�ᡢ���깻���»ܤ��륪��饤��ץ���������Ǥ���������̤��Ƹ���Ϥθ��塢���ü�Ʊ�Τΰ�ʸ����ή�ڤӤ��ι��ʸ���θ����Ǥ��뵡����������ޤ�������������ǯ�٤ϡ��Ѹ졦�ڹ��Σ����졢����ؤǼ»ܤ��ޤ����ʻ��ó�����������̾�ˡ�
Ϣ�ȳ�ư
- �ع���Ϣ����
-
 ������Ȥߤ���������ñ�̸ߴ����١ʼ��Է��������ñ�̸ߴ�������
������Ȥߤ���������ñ�̸ߴ����١ʼ��Է��������ñ�̸ߴ�������
�����Է��������ñ�̸ߴ���������뤷�Ƥ�����ؤˤ����ơ���̣�Τ�����Ȥ�¾��إ����ѥ����������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ�����������ñ�̤ϡ���°��ؤ�ǧ�ꤵ��ޤ���������ؤ��ÿ��Τ�����Ȥ��ˡ����ʼ��Ȥ��������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
��������ë6��إ���������Ϣ�Ȼ���
������ë����ءʹ�δܡ����������½��ҡ����롦����Իԡ�������ȡ˥�����������Ȥϼ���ؤ��ÿ���褫�����������Ƥ�¾�ζ�����ؤˤ��������ݶ���μ��Ȳ��ܤȤ�����ߤ�����Ȥ������ϡ�Ϣ�Ȥˤ�ꡢ���顦����θ�ή�ˤ����ߤη�ȯ�ȶ���μ��θ���˻뤳�Ȥ���Ū�Ȥ��Ƥ��ޤ��� - ����Ϣ�ȥץ��������
-
 ������Ȥߤ�������Ϣ�ȹ�����ߤζ����ή���̤�������λ��������ϩ���Ф���ؽ����ߤ����ȤȤ�ˡ���ؤε������������Ӷ������Ƥ�����������γ�������ޤ뤿�ᡢ�����ع���Ϣ�ȶ�������뤷�Ƥ��ޤ���
������Ȥߤ�������Ϣ�ȹ�����ߤζ����ή���̤�������λ��������ϩ���Ф���ؽ����ߤ����ȤȤ�ˡ���ؤε������������Ӷ������Ƥ�����������γ�������ޤ뤿�ᡢ�����ع���Ϣ�ȶ�������뤷�Ƥ��ޤ���
�����£�ǯ(2023)ǯ�ٸ��ߡ���δܹ����ع��������Ω������������ع�����Ω��Į�����ع��ڤ����ܽ����ΰ������°��Ʋ���ҹ����ع���4����Ϣ�ȶ�������뤷�Ƥ��ꡢ�ƹ����ع������̤���ؤμ��Ȥ���֤Ǥ������٤��ߤ��Ƥ��ޤ��� - �ϰ�Ϣ����
-
 ������Ȥߤ��������ڶ��鸦���ư�۹�δ���ؤ�����ë�趵��Ѱ���Ȥζ������˴�Ť�������θ�Ω����ع������ձ�Ǥζ���ٱ�ܥ��ƥ�����ư�ʼ���������ؽ��ٱ硢����ؽ���������ɤ�ʹ�����ʤɡˤ�»ܤ��Ƥ��ޤ���
������Ȥߤ��������ڶ��鸦���ư�۹�δ���ؤ�����ë�趵��Ѱ���Ȥζ������˴�Ť�������θ�Ω����ع������ձ�Ǥζ���ٱ�ܥ��ƥ�����ư�ʼ���������ؽ��ٱ硢����ؽ���������ɤ�ʹ�����ʤɡˤ�»ܤ��Ƥ��ޤ���
���ڳؽ��ٱ硢����ư��Ƴ����۽�ë��Ω���ɳ�����ع��������ǹԤäƤ��롣
����ʸ�����Ĵ������۹�δ���ؤȰ�븩���ԤȤζ���˴�Ť����ųؼ½��ˤ����ƻ����ʸ�����Ĵ�������ݸ���ѤˤĤ���Ϣ�Ȥ��Ƽ»ܤ��Ƥ��롣
�����ϰ衦�Ҳ�ؤι����ܳ��ϰ�Ϣ�ȡ��Ҳ���������������������ֻդ�������ɸ�����������e-����å��ؤΥ���ƥ�Ĥ����ۿ���ԤäƤ��ޤ���
��������
- ����������������
-
 ������Ȥߤ���������ؤ˺��Ҥ��Ƥ��ʤ����Ǥ⡢�������������Ȥ��ơ��ܳؤ����ߤ��Ƥ�����Ȳ��ܡʶ������ܴޤ�ˤ��������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ����������ܤμ��֤�λ���������ɾ�����ɹ��ʾ��ϡ�ñ��ǧ�ꤵ��ޤ���
������Ȥߤ���������ؤ˺��Ҥ��Ƥ��ʤ����Ǥ⡢�������������Ȥ��ơ��ܳؤ����ߤ��Ƥ�����Ȳ��ܡʶ������ܴޤ�ˤ��������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ����������ܤμ��֤�λ���������ɾ�����ɹ��ʾ��ϡ�ñ��ǧ�ꤵ��ޤ���
�������������Ȥ����ܳؤ����ߤ��Ƥ�����Ȳ��ܤ��������˾�����硢���ȳ��ֳ����������ش�����Ф��Ƥ����������������������ͤξ塢�����β����γؽ���˸���ʤ��ϰϤ����ؤ���Ĥ��ޤ����ʤ����������֤ϣ�ǯ����Ȥ��ޤ��� - �Ҳ�Ͷ�����
-
 ������Ȥߤ��������Ҳ�Ͷ���˴ؤ���Ҳ�Ū�����˱����뤿�ᡢ�Ҳ�ͤ����ؤ���ͤ��Ƥ��ޤ����ޤ�����������ر��Ȥ�Ҳ�ͤ��ò������������٤��ߤ��Ƥ��ޤ��ʰ����γ���������ʤΤߡˡ�
������Ȥߤ��������Ҳ�Ͷ���˴ؤ���Ҳ�Ū�����˱����뤿�ᡢ�Ҳ�ͤ����ؤ���ͤ��Ƥ��ޤ����ޤ�����������ر��Ȥ�Ҳ�ͤ��ò������������٤��ߤ��Ƥ��ޤ��ʰ����γ���������ʤΤߡˡ� - �����ؽ���
-
 ������Ȥߤ��������ϰ�Ϣ�ȡ��Ҳ����ʥ����Ǥϡ��ܳؤθ������̤ȶ��鵡ǽ���Ҳ���������顢�ؽѡ�ʸ����ȯŸ�˹�������Ū�ǡ����������ؽ���»ܤ��Ƥ��ޤ���
������Ȥߤ��������ϰ�Ϣ�ȡ��Ҳ����ʥ����Ǥϡ��ܳؤθ������̤ȶ��鵡ǽ���Ҳ���������顢�ؽѡ�ʸ����ȯŸ�˹�������Ū�ǡ����������ؽ���»ܤ��Ƥ��ޤ���
���������ֺ¤μ»�
���������ѥ����ϰ轻̱���оݤˡ����ܡ���ء���ˡ��ݽѡ�����ˡ����汿ư������դΥ��ƥ���ǡ���ǯ��70�ֺ¤�ͭ���dz��ߤ��Ƥ��ޤ����������ˤϿ�ۤ䡢�����ΰ���ߤγ�����Ԥ����ؽ�������ʤΰ���Ȥ��Ƥ��ޤ���
������������e����å��ؤλ���
���ܳؤ�ޤ����ë����Σ���ؤ�����ë�趵��Ѱ���Ȥ�Ϣ�Ȥˤ�롢e�顼�˥������Ρ֤�������e����å��ס�̵���ˤˡ��ܳض���������ʬ���褫��������ƥ�Ĥ����Ƥ��ޤ���
�����֥ӥ��ͥ������ǥ�����ֺ¡פؤλ���
������ë�ץ�åȥե�������Ȥΰ�ĤȤ��ơ��ܳؤ�ޤ����ë����Σ���ؤ�Ϣ�Ȥ������ӥ��ͥ��ѡ����������̵������ǥޥ�ɹֺ¤��ܳض����Υ���ƥ�Ĥ����Ƥ��ޤ���
��������ë�襷�˥���������ؤιֻ�
���ɸ���������ؤ��ÿ�����������¿�̤ʸ���ʬ��ιֵ����Ǥ���褦���Ƴ������鶵����ֻդȤ����ɸ����Ƥ��ޤ���
�Ҳ��
- �ܥ��ƥ�����ư��
-
 ������Ȥߤ�������δ���ؤ�����ë�趵��Ѱ���Ȥζ������˴�Ť��ơ�����θ�Ω����ع��Ǥζ���ٱ�ܥ��ƥ�����ư��ԤäƤ��ޤ�������Ū�ˤϡ��ƶ��ʤμ��������Ϥ���Ȥ��ơ����̤˻ٱ��ɬ�פȤ����Ƹ���̤ؤγؽ��ٱ硢���ݸ�Ҥɤ�ͷ�Ӥλ�Ƴ�����ؽ�������ʤɡ�¿���ˤ錄���ư��»ܤ��Ƥ��ޤ���
������Ȥߤ�������δ���ؤ�����ë�趵��Ѱ���Ȥζ������˴�Ť��ơ�����θ�Ω����ع��Ǥζ���ٱ�ܥ��ƥ�����ư��ԤäƤ��ޤ�������Ū�ˤϡ��ƶ��ʤμ��������Ϥ���Ȥ��ơ����̤˻ٱ��ɬ�פȤ����Ƹ���̤ؤγؽ��ٱ硢���ݸ�Ҥɤ�ͷ�Ӥλ�Ƴ�����ؽ�������ʤɡ�¿���ˤ錄���ư��»ܤ��Ƥ��ޤ���
�����ư
- ¿�ͤʸ���������
-
 ������Ȥߤ�����ʸ�����ˤϡ�����إ��������������饳�������š����ܻ˳إ��������������Ķ�������������ʸ�ء�ʸ���������Ȥ���5�ĤΥ������������줾��������ΰ�˴ؤ���¤�¿�ͤʸ����ư��Ÿ�����Ƥ��ޤ�������Ū�ˤϡ��ع�����˴ؤ��븦�桢���������˴ؤ��븦�桢�ųؤ˴ؤ��븦�桢���ܤ���ˤ�ʸ����ʸ�ؤ˴ؤ��븦�桢�����濴�Ȥ����쥢��������ˤ�ʸ���˴ؤ��븦�����������ޤ���
������Ȥߤ�����ʸ�����ˤϡ�����إ��������������饳�������š����ܻ˳إ��������������Ķ�������������ʸ�ء�ʸ���������Ȥ���5�ĤΥ������������줾��������ΰ�˴ؤ���¤�¿�ͤʸ����ư��Ÿ�����Ƥ��ޤ�������Ū�ˤϡ��ع�����˴ؤ��븦�桢���������˴ؤ��븦�桢�ųؤ˴ؤ��븦�桢���ܤ���ˤ�ʸ����ʸ�ؤ˴ؤ��븦�桢�����濴�Ȥ����쥢��������ˤ�ʸ���˴ؤ��븦�����������ޤ���
��
�س����α���������٤Ȥϡ�
��ݸ�ή�γ������䶵��γ�������ޤ뤳�Ȥ���Ū�Ȥ��ơ�����Ū�˳��������α���������ܤ���ء�û��������˼�����������Ȥߡ�
��
�س���α�ء������ǥ������֥����ɡ٤Ȥϡ�
���ܤγ����������γع��dzؤ֤Ȥ��ˡ�û���֤Υץ�����फ�飱�ش��䣱ǯ�ְʾ��Ĺ���ץ�������α�����٤����ꤹ��ʤɤ��ơ�������Ȥ���α�ؤ�ٱ礹�����Ȥߡ�
��
�سع���Ϣ�ȡ٤Ȥϡ�
��˹������鵡�ء���ء�û����ء���������ع�������ع��ʤɡ�Ʊ�Τ�����ɤ�����佼�¤��������ư�뤳�Ȥ���Ū��Ϣ�ȶ��Ϥ������Ȥߡ�
��
�ع���Ϣ�ȥץ������٤Ȥϡ�
�����ؤζ��Ϥˤ�ꡢ�������ؤγؤӤ��δ������ؤӤ��Ф�����ߤ���夵���뤿�ᡢ��ؤμ��Ȥؤλ��ä䡢��ض����ι�Ǥν�ĥ�ֵ��ʤɤζ���ץ�������Ԥ�����Ȥߡ�
�Ѹ켭ŵ���ƾܤ���Ĵ�٤�
��
���ϰ�Ϣ�ȡ٤Ȥϡ�
��ؤ�û����ؤ��ϰ�Ҳ�Υˡ����˱������ϰ���Ѷ�Ū�˴ؤ�뤳�Ȥǡ��ϰ�γ������ʤɤ˹������ϰ�γƻ�Į¼�ʤɤ�Ϣ�Ȥ������Ȥߡ�
��
�ز������������١٤Ȥϡ�
�Ҳ�ͤʤɤΤ��γع�������ʤɤˤϺ��Ҥ��Ƥ��ʤ��Ԥ��Ф�������μ��Ȳ��ܤ�������ǧ�ᡢ�����γ�����Ʊ�ͤ˼��Ȥ���Ԥ���ñ�̤��Ϳ�������١�
�Ѹ켭ŵ���ƾܤ���Ĵ�٤�
��
�ؼҲ�Ͷ���٤Ȥϡ�
�Ҳ�ͤ��оݤȤ����������μ��䵻�Ѥν�����ؤ�ľ�����Ф��ơ����ꥭ�������Ȥ���θ��ʤɳؤӤ�ٱ礷����ʤ��뤳�Ȥ���ؤ�����������뤳�Ȥ���Ū�Ȥ�������Ȥߡ�
��
�������ؽ��٤Ȥϡ�
�ͤ������ˤ錄��ؤӤ�ؽ��γ�ư��³���Ƥ��������ؽ��ˤĤ��ơ���ؤ�û����ؤ��ؤӤξ�䵡�������ʤɤμ���Ȥߡ�
��
�إܥ��ƥ�����ư�٤Ȥϡ�
��������ȯŪ�˹Ԥ��ܥ��ƥ�����ư���Ф��ơ���ؤ�û����ؤ���ư�λٱ��ñ��ǧ��ʤɤ뤳�Ȥˤ�ꡢ�������褬���������뤳�Ȥ���Ū�Ȥ�������Ȥߡ�
��
��¿�ͤʸ������ơ٤Ȥϡ�
��ؤν��פ���Ū�Ǥ�������ؤζ���ȸ����ư�Τ�������ؤ��ԤäƤ����͡��ʸ����ư�ˤĤ��Ƥμ���Ȥߡ�
��δ���ؤκǿ����٥�Ⱦ���Ϥ����餫�餴����������
��δ���ؤκǿ��ȥԥå����Ϥ����餫�餴����������
- ����
- �����
- ʸ����
- ˡ����
- ������������������
- ��������
- �бij���
- �����ظ���ʡʽ��Ρ�
- �����ظ���ʡ���Ρ�
- �кѳظ���ʡʽ��Ρ�
- �кѳظ���ʡ���Ρ�
- ���ظ���ʡʽ��Ρ�
- ˡ�ظ���ʡʽ��Ρ�
- �бijظ���ʡʽ��Ρ�
- ���ظ���ʡ���Ρ�
- ˡ�ظ���ʡ���Ρ�
- �бijظ���ʡ���Ρ�
- ��ʸ�ʳظ���ʡʽ��Ρ�
- ���ݡ��ġ������ƥฦ��ʡʽ��Ρ�
- ���ݡ��ġ������ƥฦ��ʡ���Ρ�
- ��ʸ�ʳظ���ʡ���Ρ�
- ������Ū�ˡ�ظ���ʡʽ��Ρ�
- �������Х륢��������ʡʽ��Ρ�
- �������Х륢��������ʡ���Ρ�
- �ߵޥ����ƥฦ��ʡʽ��Ρ�
- �ߵޥ����ƥฦ��ʡ���Ρ�