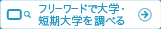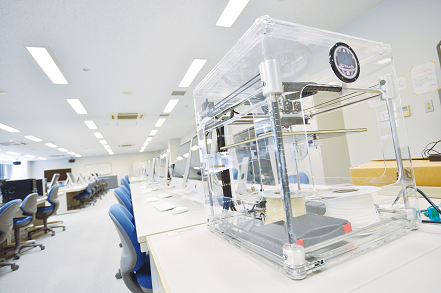東京電機大学
東京電機大学
理工学部

- ディプロマポリシー
-
理工学部に所定の期間在学し(※)、卒業に必要な単位を修得して、次の学修成果を上げた者に対して、学士の学位を授与します。
※標準修業年限 4年
(1) 実学尊重を旨として、理学、生命科学、情報学、機械工学、電子情報・生体医工学、建築・都市環境学の理工学6分野のうち、主となる専門分野(主コース)と副となる専門分野(副コース)の科学技術の知識・技術をもつこと。
(2) 自立した発想のもとに解くべき課題を見つけ出す能力をもつとともに、専門的知識と技術を活用してその課題を解決するための実践力、コミュニケーション能力をもつこと。
(3) 科学技術社会の永続的発展に寄与することができる理工学の幅広い基礎知識をもつこと。
(4)「技術は人なり」の精神のもと、倫理観のある科学技術者および人間性豊かな社会人として必要な素養を身につけること。
(5) グローバルな環境でコミュニケーションをとることができる基本的な語学力と広い教養を身につけること。詳細リンク(外部サイトへ) - カリキュラムポリシー
-
理工学部は、「未来型科学技術者」を養成するために、1年次に専門基礎科目および学系共通科目を履修させたのち、2年次になるときに主コースおよび副コースを各々1つずつ選択させます。自主的な学びのために副コースは他学系からも選択できるようにします。
また、理工学部の「学位授与の方針」を実現するために、以下のように教育課程を編成し、実施します。
詳細は以下のリンクをご参照ください。
詳細リンク(外部サイトへ)
カリキュラム
- 教育内容の体系化とその充実?
-
 ●取り組みの内容理工学部は、「学系・コース制」、「主コース・副コース制」を導入しています。学系は6つの分野(理学、生命科学、情報学、機械工学、電子情報・生体医工学、建築・都市環境学)を軸に編成しており、その下に学問の最小ユニットとして16のコースを設置しています。学生は学系単位で入学し、初年次教育・専門基礎教育等を1年間学んだ後、専門分野を深く学ぶ主コースを選択するとともに、別の分野を副コースとして選択します。主コース・副コースの組み合わせにより、専門性を高めることも、多様な領域に亘る視野と見識を養成することも可能とする学際性に富んだ教育・研究が可能となり、多様化する科学技術分野に柔軟に対応できる学生の個性的な学びの場を提供していることが特徴です。 カリキュラムは、豊かな教養と確かな基礎学力、体系的な専門知識の修得を基本とし、さらには、単一の学問体系にとらわれない柔軟な思考力、多様な問題に対処できる能力の育成を目指し、「英語科目」「人間形成科目」「専門基礎科目」「学系共通科目」及び「コース専門科目」を配当し、卒業所要単位数124単位を満たすこととなっています。
●取り組みの内容理工学部は、「学系・コース制」、「主コース・副コース制」を導入しています。学系は6つの分野(理学、生命科学、情報学、機械工学、電子情報・生体医工学、建築・都市環境学)を軸に編成しており、その下に学問の最小ユニットとして16のコースを設置しています。学生は学系単位で入学し、初年次教育・専門基礎教育等を1年間学んだ後、専門分野を深く学ぶ主コースを選択するとともに、別の分野を副コースとして選択します。主コース・副コースの組み合わせにより、専門性を高めることも、多様な領域に亘る視野と見識を養成することも可能とする学際性に富んだ教育・研究が可能となり、多様化する科学技術分野に柔軟に対応できる学生の個性的な学びの場を提供していることが特徴です。 カリキュラムは、豊かな教養と確かな基礎学力、体系的な専門知識の修得を基本とし、さらには、単一の学問体系にとらわれない柔軟な思考力、多様な問題に対処できる能力の育成を目指し、「英語科目」「人間形成科目」「専門基礎科目」「学系共通科目」及び「コース専門科目」を配当し、卒業所要単位数124単位を満たすこととなっています。 - 教養・リベラルアーツ教育?
-
 ●取り組みの内容大学で学ぶ以上は、単に有能な「職業人」となるにとどまらず、高い見識を持った「教養人」となることが期待されます。本学の教育・研究理念「技術は人なり」は、技術は、単に職に就いたり収入を得るためのものではなく、技術という文化の習得そのものを通じて「人間性が磨かれる」ということの重要性を示しています。理工学部では、「人間性・教養を磨く」「学のある人間になる」に応えるため、「人間形成科目」の授業科目を用意しています。「人間形成科目」は、人類が面白いと考え、大事だと思って、開拓・発展させてきた様々な学問分野、学生自身の興味や関心の広がり・深まりに応じて学べるように学年にとらわれず自由な履修を可能としています。また、人間性豊かな社会人として必要な素養を身につけるため、専門教育科目と並行して履修することができます。卒業までに16単位以上の修得が必要ですが、必修科目はありませんので、自由に履修計画を立てることができます。
●取り組みの内容大学で学ぶ以上は、単に有能な「職業人」となるにとどまらず、高い見識を持った「教養人」となることが期待されます。本学の教育・研究理念「技術は人なり」は、技術は、単に職に就いたり収入を得るためのものではなく、技術という文化の習得そのものを通じて「人間性が磨かれる」ということの重要性を示しています。理工学部では、「人間性・教養を磨く」「学のある人間になる」に応えるため、「人間形成科目」の授業科目を用意しています。「人間形成科目」は、人類が面白いと考え、大事だと思って、開拓・発展させてきた様々な学問分野、学生自身の興味や関心の広がり・深まりに応じて学べるように学年にとらわれず自由な履修を可能としています。また、人間性豊かな社会人として必要な素養を身につけるため、専門教育科目と並行して履修することができます。卒業までに16単位以上の修得が必要ですが、必修科目はありませんので、自由に履修計画を立てることができます。
教育方法
- アクティブラーニング?
-
 ●取り組みの内容全学共通科目の「東京電機大学で学ぶ」は、修学基礎科目として、全新入生が取り組む科目になっています。本科目は、本学の新入生の皆さんに、工学やものづくりの面白さに触れ、工学の社会的意義を理解し、エンジニアの卵として自分の将来をイメージするとともに、大学での学びの意義に気づき、これからの大学での様々な学習に、目的意識を持って主体的に向かうマインドを育むことを目的として設置されています。また、単なる講義(講演)の受動的学習ではなく、構造化された能動的学習(アクティブラーニング)を行い、これからの社会人に求められる批判的思考力、コミュニケーション力、文章表現力などの汎用的スキルの基礎を養成することも目的としています。
●取り組みの内容全学共通科目の「東京電機大学で学ぶ」は、修学基礎科目として、全新入生が取り組む科目になっています。本科目は、本学の新入生の皆さんに、工学やものづくりの面白さに触れ、工学の社会的意義を理解し、エンジニアの卵として自分の将来をイメージするとともに、大学での学びの意義に気づき、これからの大学での様々な学習に、目的意識を持って主体的に向かうマインドを育むことを目的として設置されています。また、単なる講義(講演)の受動的学習ではなく、構造化された能動的学習(アクティブラーニング)を行い、これからの社会人に求められる批判的思考力、コミュニケーション力、文章表現力などの汎用的スキルの基礎を養成することも目的としています。 - 課題解決型学習(PBL)?
-
 ●取り組みの内容社会で求められるのは技術や知識だけではなく、チームで仕事を成し遂げる時に重要となるコミュニケーション能力や課題発見・解決能力です。これらの能力を身につけるために、理工学部ではPBL(Problem-Based-Learning)型の授業が開講されています。PBL型の授業では教員はファシリテーター役となり、あくまでも「学生が主体」となって自ら学び、チームで取り組むなかで自分の考えを発表し、また意見を聴くことでコミュニケーション能力が高まり、さらには協調性やリーダーシップが養われます。
●取り組みの内容社会で求められるのは技術や知識だけではなく、チームで仕事を成し遂げる時に重要となるコミュニケーション能力や課題発見・解決能力です。これらの能力を身につけるために、理工学部ではPBL(Problem-Based-Learning)型の授業が開講されています。PBL型の授業では教員はファシリテーター役となり、あくまでも「学生が主体」となって自ら学び、チームで取り組むなかで自分の考えを発表し、また意見を聴くことでコミュニケーション能力が高まり、さらには協調性やリーダーシップが養われます。 - 少人数教育?
-
 ●取り組みの内容理工学部では、1年次には専門科目の土台となる数学・物理学・化学の専門基礎科目が開講されています。これは4月の入学当初に行うプレースメントテストの結果によってクラス分けされ、習熟度別に少人数クラスによる講義を行います。高等学校での学習内容の復習を兼ねた講義内容となっていますので、しっかりと基礎を学ぶことができます。
●取り組みの内容理工学部では、1年次には専門科目の土台となる数学・物理学・化学の専門基礎科目が開講されています。これは4月の入学当初に行うプレースメントテストの結果によってクラス分けされ、習熟度別に少人数クラスによる講義を行います。高等学校での学習内容の復習を兼ねた講義内容となっていますので、しっかりと基礎を学ぶことができます。
また、本学の特色である「実学教育」を担う「実験」や「実習」においても、少人数のグループを編成し、チームで課題に取り組みます。
4年次で取り組む卒業研究は研究室単位の少人数で学生が主体的に課題に取り組み卒業論文として成果をまとめます。このほかにも少人数のゼミナールや輪講形式の講義も用意されています。
学びの支援
- 学びの組織的な支援?
-
 ●取り組みの内容大学で授業を受ける上では、高等学校までに学んできた数学、物理学、化学、英語が基礎となり重要となります。これらの科目の教育充実を支援する場として、学習サポートセンターを設置しています。学習サポートセンターの指導スタッフは、高等学校で長年授業を行ってきたベテランの教員です。学生の希望により個別、グループどちらの相談にも親切丁寧に対応しています。
●取り組みの内容大学で授業を受ける上では、高等学校までに学んできた数学、物理学、化学、英語が基礎となり重要となります。これらの科目の教育充実を支援する場として、学習サポートセンターを設置しています。学習サポートセンターの指導スタッフは、高等学校で長年授業を行ってきたベテランの教員です。学生の希望により個別、グループどちらの相談にも親切丁寧に対応しています。
苦手科目の不安解消はもちろんのこと、学修する科目の理解力を高めるためにも、1〜4年次まで幅広い学生が利用しています。 - 初年次教育?
-
 ●取り組みの内容入学後の授業に不安がないよう、実験器具の使い方など基礎から学んでいく初年次教育が実施されています。例えば、「日本語リテラシー」では、レポートの作成方法など大学生活を送る上での基本的なテクニックを学ぶことができます。また、1年次科目の「東京電機大学で学ぶ」は工学やものづくりの面白さに触れ、工学の社会学的意義を理解し、エンジニアの卵として自分の将来をイメージするとともに、大学での学びの意義に気づき、これからの大学での様々な学習に、目的意識を持って主体的に向かうマインドを育むことを目的として設置されています。
●取り組みの内容入学後の授業に不安がないよう、実験器具の使い方など基礎から学んでいく初年次教育が実施されています。例えば、「日本語リテラシー」では、レポートの作成方法など大学生活を送る上での基本的なテクニックを学ぶことができます。また、1年次科目の「東京電機大学で学ぶ」は工学やものづくりの面白さに触れ、工学の社会学的意義を理解し、エンジニアの卵として自分の将来をイメージするとともに、大学での学びの意義に気づき、これからの大学での様々な学習に、目的意識を持って主体的に向かうマインドを育むことを目的として設置されています。 - 中途退学防止?
-
 ●取り組みの内容学生生活を支える各種サポートがあります。
●取り組みの内容学生生活を支える各種サポートがあります。
東京電機大学では、学生一人ひとりが充実した学生生活を送れるように、学習面だけでなく生活面へのサポートにも力を入れています。進路や生活面の悩みや学生の健康維持管理に対応することはもちろん、精神衛生上の問題にも心を配っています。
また、卒業生の校友会や、在学生のご父母で構成される後援会では、経済面の支援や情報提供、就職の支援など、学生の生活をサポートしています。
また、成績不良者に対する学生アドバイザーによる学修指導を併せて実施しております。 - TA・RA・SA・メンターの活用?
-
 ●取り組みの内容自らの学力も磨かれる学生職員とスチューデント・アシスタント(SA)・副手(TA)制度
●取り組みの内容自らの学力も磨かれる学生職員とスチューデント・アシスタント(SA)・副手(TA)制度
東京電機大学では、実験室での実習機材等の準備を行い、学生が働きながら学ぶ「学生職員」制度を設けています。
また、高学年次の学生を中心に低学年次生へ授業補助を行うSA(スチューデント・アシスタント)制度、大学院生が学部生の授業補助を行う副手(TA)制度を設けています。
学生にとっては、自らが教える立場に立つことで学習の理解度をより深め、基礎学力を向上させるとともに、経済的支援にもなっています。 - 入学前教育?
-
 ●取り組みの内容学校推薦型選抜(指定校・公募)、総合型選抜(AO)などの合格者を対象に「入学前準備教育」を実施しています。実施内容としては、1月から3月にかけて、数学、英語、物理学、化学の4科目について「Web・DVD」による講義を受講します。映像教材をもとに自宅で学習し、課題を提出し理解度を高めていただきます。
●取り組みの内容学校推薦型選抜(指定校・公募)、総合型選抜(AO)などの合格者を対象に「入学前準備教育」を実施しています。実施内容としては、1月から3月にかけて、数学、英語、物理学、化学の4科目について「Web・DVD」による講義を受講します。映像教材をもとに自宅で学習し、課題を提出し理解度を高めていただきます。 - ラーニングコモンズ?
-
 ●取り組みの内容埼玉鳩山キャンパスの総合メディアセンターの図書閲覧室・アクティブラーニングゾーンでは目的に合わせた学習が可能です。
●取り組みの内容埼玉鳩山キャンパスの総合メディアセンターの図書閲覧室・アクティブラーニングゾーンでは目的に合わせた学習が可能です。
図書・学術雑誌がある3階エリアは、メディアゾーンとして個人からグループまで幅広く利用が可能なスペースを用意しています。個人学習が可能な個室を備えた静粛閲覧エリア、グループ学習に適した可動式の机・椅子・ホワイトボードがあるグループスタディエリア、新聞等が閲覧できるブラウジングエリアもあります。
2階エリアは、リーディングゾーンとしてグループディスカッションが実現できるように4〜6名で利用可能な机を配置しています。
1階エリアは、アクティブラーニングゾーンとして学生がノートパソコンを持ち込んで活用できるように可動式の机・椅子やホワイトボードを設置し、グループ学習を支援しています。 - 学生アンケートの活用?
-
 ●取り組みの内容理工学部では、学生による「授業アンケート」を毎学期末に行い、集計結果を学内限定のホームページに公開して科目担当教員へフィードバックしており、教員自身が教育効果を把握しています。また、授業アンケートの集計結果を踏まえ、全ての授業において主担当の教員は所見(授業改善や今後の工夫、計画など)を作成しています。理工学部では授業アンケートの結果を学内の自己評価委員会にて検証し、その集計結果が一定の基準を満たさない場合は、必要に応じて該当科目の主担当教員が指定された授業(アンケート評価が高かった授業科目担当者の授業など)に授業参観(クラスビジット)することとしています。
●取り組みの内容理工学部では、学生による「授業アンケート」を毎学期末に行い、集計結果を学内限定のホームページに公開して科目担当教員へフィードバックしており、教員自身が教育効果を把握しています。また、授業アンケートの集計結果を踏まえ、全ての授業において主担当の教員は所見(授業改善や今後の工夫、計画など)を作成しています。理工学部では授業アンケートの結果を学内の自己評価委員会にて検証し、その集計結果が一定の基準を満たさない場合は、必要に応じて該当科目の主担当教員が指定された授業(アンケート評価が高かった授業科目担当者の授業など)に授業参観(クラスビジット)することとしています。 - インターンシップ?
-
 ●取り組みの内容学生が自らの専攻やキャリアに関連した就業体験を行うことによって、将来のキャリアについて深く考える機会を持ち、社会人基礎力を養うことを目的として「インターンシップ」を積極的に推進しています。学生は所定の手続きによる選考等を経て、長期休業期間等を利用して2週間〜1ヶ月程度、受け入れ先企業において就業体験を行います。学生が安心してインターンシップに参加することができるよう、先輩の体験談や企業の人事担当者の話を聴くガイダンス等も実施しています。
●取り組みの内容学生が自らの専攻やキャリアに関連した就業体験を行うことによって、将来のキャリアについて深く考える機会を持ち、社会人基礎力を養うことを目的として「インターンシップ」を積極的に推進しています。学生は所定の手続きによる選考等を経て、長期休業期間等を利用して2週間〜1ヶ月程度、受け入れ先企業において就業体験を行います。学生が安心してインターンシップに参加することができるよう、先輩の体験談や企業の人事担当者の話を聴くガイダンス等も実施しています。 - 資格取得(国家資格受験資格)?
-
 ●取り組みの内容●教員免許状
●取り組みの内容●教員免許状
教科及び教職に関する授業科目を修得することで以下の教員免許状の取得が可能です。
・中学校教諭一種免許状(数学、理科)
・高等学校教諭一種免許状(数学、理科、情報、工業)
●建築士
定められた科目の修得条件を満たして卒業した場合は、「建築士プログラム」を修了したものとして認定されます。「建築士プログラム」を修了した場合、建築士の受験資格が得られます。ただし、資格によって必要な修得単位数と実務経験年数が異なります。
・一級建築士
・二級建築士
・木造建築士
●技術士補
建築・都市環境学系でJABEEプログラムを修了すると登録により資格を得ることができます。他の学系でも卒業後に試験科目のうち共通科目が免除されます。
●測量士補
建築・都市環境学系を主・副コースで卒業し、定められた科目および単位数を修得している場合は、申請により測量士補の資格が得られます。
●建設系資格
建築・都市環境学系を主・副コースとして卒業し、定められた科目及び単位数を修得すると、定められた実務経験の後に建設系資格の受験資格が得られます。
学修についての評価
- アセスメントポリシー?
-
 ●取り組みの内容理工学部は、学部のディプロマ・ポリシー【(1)実学尊重を旨として、理学、生命科学、情報学、機械工学、電子工学、建築・都市環境学の理工学6分野のうち、主となる専門分野(主コース)と副となる専門分野(副コース)の科学技術の知識・技術をもつこと。(2)自立した発想のもとに解くべき課題を見つけ出す能力をもつとともに、専門的知識と技術を活用してその課題を解決するための実践力、コミュニケーション能力をもつこと。(3)科学技術社会の永続的発展に寄与することができる理工学の幅広い基礎知識をもつこと。(4)「技術は人なり」の精神のもと、倫理観のある科学技術者および人間性豊かな社会人として必要な素養を身につけること。(5)グローバルな環境でコミュニケーションをとることができる基本的な語学力と広い教養を身につけること。】に沿って、学生の入学時から卒業時までの成長を視野に入れ、機関・プログラム・授業科目の各レベルおよび課外活動において、アセスメントを実施し、教育改善に活用していきます。
●取り組みの内容理工学部は、学部のディプロマ・ポリシー【(1)実学尊重を旨として、理学、生命科学、情報学、機械工学、電子工学、建築・都市環境学の理工学6分野のうち、主となる専門分野(主コース)と副となる専門分野(副コース)の科学技術の知識・技術をもつこと。(2)自立した発想のもとに解くべき課題を見つけ出す能力をもつとともに、専門的知識と技術を活用してその課題を解決するための実践力、コミュニケーション能力をもつこと。(3)科学技術社会の永続的発展に寄与することができる理工学の幅広い基礎知識をもつこと。(4)「技術は人なり」の精神のもと、倫理観のある科学技術者および人間性豊かな社会人として必要な素養を身につけること。(5)グローバルな環境でコミュニケーションをとることができる基本的な語学力と広い教養を身につけること。】に沿って、学生の入学時から卒業時までの成長を視野に入れ、機関・プログラム・授業科目の各レベルおよび課外活動において、アセスメントを実施し、教育改善に活用していきます。
詳細は以下URLをご覧ください。 - 外部テストの活用?
-
 ●取り組みの内容理工学部が定める資格を学生が取得した場合、学生の申請により、資格に対応する授業科目として単位認定を受けることができます。1月〜6月に申請の場合は前期成績表に、7月〜12月に申請の場合は後期成績表に表記されます。
●取り組みの内容理工学部が定める資格を学生が取得した場合、学生の申請により、資格に対応する授業科目として単位認定を受けることができます。1月〜6月に申請の場合は前期成績表に、7月〜12月に申請の場合は後期成績表に表記されます。 - GPAの活用?
-
 ●取り組みの内容理工学部では、成績の総合評価の指標としてGPA(Grade Point Average)を採用しています。GPAとは、最終的に与えられたS・A・B・C・D・−の評価(Grade)に4〜0のポイント(Point)を配当しそれに単位数を掛け、修得したポイントの合計と単位数をもとに算出する平均値(Average)です。GPAは、3年以上の在学での卒業における基準、履修上限単位数を超えての履修基準及び学生アドバイザーによる面談指導条件、退学予備勧告・退学勧告を視野に入れた学修指導・特別学修指導の条件などに活用しています。また、本学大学院推薦入試の被推薦資格の成績順位算出にも利用しています。
●取り組みの内容理工学部では、成績の総合評価の指標としてGPA(Grade Point Average)を採用しています。GPAとは、最終的に与えられたS・A・B・C・D・−の評価(Grade)に4〜0のポイント(Point)を配当しそれに単位数を掛け、修得したポイントの合計と単位数をもとに算出する平均値(Average)です。GPAは、3年以上の在学での卒業における基準、履修上限単位数を超えての履修基準及び学生アドバイザーによる面談指導条件、退学予備勧告・退学勧告を視野に入れた学修指導・特別学修指導の条件などに活用しています。また、本学大学院推薦入試の被推薦資格の成績順位算出にも利用しています。 - 成績評価の厳格な運用?
-
 ●取り組みの内容理工学部では、原則として、前期末及び後期末に実施される学期末試験を用いて成績評価を行っています。他にも、学期間中の中間試験、小テスト、レポート、平常点等を踏まえ、担当教員が最適の教育効果を考えることにより、総合的な成績評価を行っています。なお、病気、忌引き、災害等のやむを得ない理由により学期末試験を受験できなかった学生に対し、追試験制度を設けています。
●取り組みの内容理工学部では、原則として、前期末及び後期末に実施される学期末試験を用いて成績評価を行っています。他にも、学期間中の中間試験、小テスト、レポート、平常点等を踏まえ、担当教員が最適の教育効果を考えることにより、総合的な成績評価を行っています。なお、病気、忌引き、災害等のやむを得ない理由により学期末試験を受験できなかった学生に対し、追試験制度を設けています。
成績評価はS(90〜100点)、A(80〜89点)、B(70〜79点)、C(60〜69点)、D(0〜59点)、−(放棄)となっており、D、−は不合格となります。
厳格な成績評価方法として、GPA(Grade Point Average)を導入し、学生ポータルサイトへGPA値を表示して、学生自身が自分の学修の達成度を把握できるようにしています。また、計画的な履修をさせることにより、学生の学習意欲の向上を目指しています。本学部のGPAは、成績評価S:4ポイント、A:3ポイント、B:2ポイント、C:1ポイントとし、修得した科目の単位数にポイントを乗じた合計と履修単位数をもとに算出しています。
×
『教育内容の体系化とその充実』とは?
教育の目的や成果を明確に設定し、その達成のため、各授業間の関連性を明確にするなど、体系的な学びを可能にすることで、教育内容の一層の充実を図る取り組み。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『教養・リベラルアーツ教育』とは?
幅広い分野の教養などを身につけ、専門知識に偏らない汎用的能力を育成するために大学・短期大学で行われる教育。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『アクティブラーニング』とは?
一方的に講義を聴くスタイルの授業ではなく、学生が積極的に学修に参加することを取り入れ、能動的(アクティブ)な学びを促すことで、知識をしっかり定着させることを目的とした学習方法。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『課題解決型学習(PBL)』とは?
プロジェクト活動を通じ、学生が自主的・自律的に課題を発見・解決する過程において、それまでに得た知識を実践的に活用することや、より学びを深くすることなどを目的とした学習方法。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『少人数教育』とは?
学習効果を高めるために、1人の教員が教える学生の数を少なくして授業を行う学習方法。
×
『学びの組織的な支援』とは?
学校側が組織的かつ恒常的に学びに対するサポート体制を用意し、授業に対する学生の不安を解消するなどの学びに対する様々な支援をすることで、より学習効果を高める取り組み。
×
『初年次教育』とは?
大学や短期大学の新入生を対象に、高校までの学びから、能動的な大学・短期大学での学びにスムーズに移行するための基本的なスキルなどを身につける教育プログラム。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『中途退学防止』とは?
学びに対する意欲の減少などを理由に修業期間の途中で学校を退学しようとする学生に対して、学びのサポートを行うことで、教育の問題解決を図り、学びの環境を改善し、中途退学を防ぐ取り組み。
×
『TA・RA・SA・メンターの活用』とは?
大学院生による教育補助(TA)、大学院生等による研究補助(RA)、学生による教育補助(SA)、後輩を多方面で支援する先輩(メンター)を教育研究活動などに活用する取り組み。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『入学前教育』とは?
入学予定者(主にAO入試や各種推薦入試などで、早期に入学が決定した入学予定者)に対して、入学後の学びの準備や学習意欲の維持などのために、入学前に行う教育。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『ラーニングコモンズ』とは?
学生の自主的・自律的な学習のため、電子情報や印刷物など様々な情報資源を使って議論などができる共有の「学習の場」。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『学生アンケートの活用』とは?
新入生や在学している学生に対し、大学の授業やカリキュラム、学修状況などについてアンケートを行い、その結果を分析・活用して、教育方法やプログラムの改善などに活かす取り組み。
×
『インターンシップ』とは?
自らの専攻や将来のキャリアに関連した就業体験や社会貢献活動に参加する制度を授業やカリキュラムに取り込むことで、学生が学問や研究分野への理解をより深めるための取り組み。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『資格取得(国家資格受験資格)』とは?
カリキュラムの整備や授業内容の工夫などを行い、学生が正課の授業を受けることで国家資格試験を受験し、合格することを目的に支援する取り組み。
×
『アセスメントポリシー』とは?
学生の学修成果の評価(アセスメント)について、目的や達成するべき質的水準と具体的な評価の実施方法などについて定めた学内の方針を活用した取り組み。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『外部テストの活用』とは?
TOEICやTOEFLといった学校の外部で行われているテストを、大学や短期大学の入試や単位認定などに活用する取り組み。
×
『GPAの活用』とは?
科目の成績評価に応じてポイント(例:5段階評価A〜Eに対し4〜0点等)を付与し、その平均点(Grade Point Average)による学習成果の評価方法を大学や短期大学での教育に活用する取り組み。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『成績評価の厳格な運用』とは?
明確な成績評価の基準を定めて厳格に運用して、単位取得や進級などを判定することで、教育の「質の保証」を実現する取り組み。
令和6年度の財務情報を公表しました