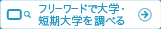東京理科大学
東京理科大学
経営学研究科(専門職)

- ディプロマポリシー
-
本学の3つの方針は各学部・学科、研究科・専攻ごとに定めています。詳しくは、本学ホームページ(下記の詳細リンク(外部サイトへ))からご希望の学部・研究科等を選び、それぞれのページをご覧ください。詳細リンク(外部サイトへ)
- カリキュラムポリシー
-
本学の3つの方針は各学部・学科、研究科・専攻ごとに定めています。詳しくは、本学ホームページ(下記の詳細リンク(外部サイトへ))からご希望の学部・研究科等を選び、それぞれのページをご覧ください。詳細リンク(外部サイトへ)
カリキュラム
- 教育内容の体系化とその充実?
-
 ●取り組みの内容教育内容の体系化への取り組みとして、「科目系統図」、「履修モデル」を作成し、ホームページで公表しています。
●取り組みの内容教育内容の体系化への取り組みとして、「科目系統図」、「履修モデル」を作成し、ホームページで公表しています。
「科目系統図」は、授業科目間の繋がりやカリキュラム・ポリシーとの関係等を学生にわかりやすく明示することで、学生が身に付ける知識・能力と授業科目との間の対応関係を示し、学習の段階や順序を表しています。
「履修モデル」は、各学科における人材育成の目的やカリキュラム・ポリシーをもとにして、学生が目指す進路と授業科目との関連性等を明確にしています。
また、シラバスに当該科目を履修するための条件(前もって履修しておくべき科目等)を明示することで、科目間の体系性を、学生自身が認識することができます。
教育方法
- アクティブラーニング?
-
 ●取り組みの内容技術経営専攻においては、個々の授業ごとに、その授業の形態や履修者数、教育内容等に適した形で、学生に能動的・主体的に学ぶ姿勢を促すアクティブラーニングを導入しています。具体的には、グループディスカッション、ディベート、グループワーク、プレゼンテーション等が授業の中で展開されています。
●取り組みの内容技術経営専攻においては、個々の授業ごとに、その授業の形態や履修者数、教育内容等に適した形で、学生に能動的・主体的に学ぶ姿勢を促すアクティブラーニングを導入しています。具体的には、グループディスカッション、ディベート、グループワーク、プレゼンテーション等が授業の中で展開されています。
また、シラバスに「準備学習・復習」欄を設け、授業を受けるにあたって望まれる準備学習の内容を明示することにより、学生に教室外での主体的な自習を促しています。
- 課題解決型学習(PBL)?
-
 ●取り組みの内容個々の授業の中で、それぞれの授業の形態、規模、教育内容等に応じたPBL(Problem Based Learning:課題解決型授業)方式を取り入れています。
●取り組みの内容個々の授業の中で、それぞれの授業の形態、規模、教育内容等に応じたPBL(Problem Based Learning:課題解決型授業)方式を取り入れています。
- 少人数教育?
-
 ●取り組みの内容技術経営専攻では、演習指導を行う教員に対しての学生数を、演習指導に支障がないよう設定しており、個々の演習指導教員が指導対象の学生をきめ細かに指導できる環境となるように努めています。
●取り組みの内容技術経営専攻では、演習指導を行う教員に対しての学生数を、演習指導に支障がないよう設定しており、個々の演習指導教員が指導対象の学生をきめ細かに指導できる環境となるように努めています。
学びの支援
- 学びの組織的な支援?
-
 ●取り組みの内容本学では、全学的な教育施策を企画するとともに、教育活動の継続的な改善の推進及び支援を行うことにより、教育の充実及び高度化に資することを目的に、「教育DX推進センター」を設置して種々の取り組みを行っています。
●取り組みの内容本学では、全学的な教育施策を企画するとともに、教育活動の継続的な改善の推進及び支援を行うことにより、教育の充実及び高度化に資することを目的に、「教育DX推進センター」を設置して種々の取り組みを行っています。
- 学修成果のフィードバック?
-
 ●取り組みの内容技術経営専攻では、授業科目について担当教員が採点した結果を、学内ポータルサイト(CLASS)にて各学生が確認することが可能になっております。また、成績評価に関する問い合わせに対しては、必要に応じて再調査を実施する体制を整えています。
●取り組みの内容技術経営専攻では、授業科目について担当教員が採点した結果を、学内ポータルサイト(CLASS)にて各学生が確認することが可能になっております。また、成績評価に関する問い合わせに対しては、必要に応じて再調査を実施する体制を整えています。
- 中途退学防止?
-
 ●取り組みの内容技術経営専攻の経済的支援の取組みとして、各種奨学金を入学前から案内している。日本学生支援機構奨学金を取り扱っており、さらに入学手続時納付金の支払いに利用できる本学との提携会社による特別レートの教育ローンを紹介しています。
●取り組みの内容技術経営専攻の経済的支援の取組みとして、各種奨学金を入学前から案内している。日本学生支援機構奨学金を取り扱っており、さらに入学手続時納付金の支払いに利用できる本学との提携会社による特別レートの教育ローンを紹介しています。
修学上の配慮としては、社会人学生の通学しやすい環境を整えるため、授業は平日夜間と土曜日に開講するとともに、遠隔地からも授業を受講することができるようハイフレックス型授業を実施しています。
- 学生アンケートの活用?
-
 ●取り組みの内容技術経営専攻では、学生からの授業評価については、各授業科目の終了後、学内ポータルサイトを利用した授業アンケートを実施しています。アンケートの結果については授業担当教員が個別に随時確認することが可能になっており、教員の授業内容の向上に活用されております。
●取り組みの内容技術経営専攻では、学生からの授業評価については、各授業科目の終了後、学内ポータルサイトを利用した授業アンケートを実施しています。アンケートの結果については授業担当教員が個別に随時確認することが可能になっており、教員の授業内容の向上に活用されております。
学修についての評価
- アセスメントポリシー?
-
 ●取り組みの内容本学では学修成果の評価に関する方針(アセスメント・ポリシー)を制定しています。詳細リンク(大学ポートレートの東京理科大学のページ内 本学での学び−学修についての評価−アセスメントポリシーの項目)をご覧ください。
●取り組みの内容本学では学修成果の評価に関する方針(アセスメント・ポリシー)を制定しています。詳細リンク(大学ポートレートの東京理科大学のページ内 本学での学び−学修についての評価−アセスメントポリシーの項目)をご覧ください。 - 成績評価の厳格な運用?
-
 ●取り組みの内容授業科目を履修し、試験等に基づく学修成果の評価が合格と判定された場合、当該授業科目所定の単位が与えられます。成績評価の基準は、全学で統一された基準に沿って作成されており、シラバス上の「学修成果の評価」欄に明記されています。「学修成果の評価」欄では、当該授業科目を修得することが「シラバスの到達目標とどのような関連をもっているか」、「各評価(S,A,B,C,D)ごとにどのようなレベルまで到達するのか」などの「学修の質」を明示しています。
●取り組みの内容授業科目を履修し、試験等に基づく学修成果の評価が合格と判定された場合、当該授業科目所定の単位が与えられます。成績評価の基準は、全学で統一された基準に沿って作成されており、シラバス上の「学修成果の評価」欄に明記されています。「学修成果の評価」欄では、当該授業科目を修得することが「シラバスの到達目標とどのような関連をもっているか」、「各評価(S,A,B,C,D)ごとにどのようなレベルまで到達するのか」などの「学修の質」を明示しています。
また、シラバスの「成績評価方法」欄で、試験、レポート等、各授業の特性に合わせた到達目標に対する成績評価方法を記載しています。
学生は自身の成績をCLASSシステム(WEBによる就学支援システム)にて閲覧することができます。
×
『教育内容の体系化とその充実』とは?
教育の目的や成果を明確に設定し、その達成のため、各授業間の関連性を明確にするなど、体系的な学びを可能にすることで、教育内容の一層の充実を図る取り組み。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『アクティブラーニング』とは?
一方的に講義を聴くスタイルの授業ではなく、学生が積極的に学修に参加することを取り入れ、能動的(アクティブ)な学びを促すことで、知識をしっかり定着させることを目的とした学習方法。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『課題解決型学習(PBL)』とは?
プロジェクト活動を通じ、学生が自主的・自律的に課題を発見・解決する過程において、それまでに得た知識を実践的に活用することや、より学びを深くすることなどを目的とした学習方法。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『少人数教育』とは?
学習効果を高めるために、1人の教員が教える学生の数を少なくして授業を行う学習方法。
×
『学びの組織的な支援』とは?
学校側が組織的かつ恒常的に学びに対するサポート体制を用意し、授業に対する学生の不安を解消するなどの学びに対する様々な支援をすることで、より学習効果を高める取り組み。
×
『学修成果のフィードバック』とは?
授業や講義などを通して学生が学んだ知識や技術や成績などの「学修成果」を、可視化するなどして学生にわかりやすく還元することで、学生自らの学びへの姿勢を支援する取り組み。
×
『中途退学防止』とは?
学びに対する意欲の減少などを理由に修業期間の途中で学校を退学しようとする学生に対して、学びのサポートを行うことで、教育の問題解決を図り、学びの環境を改善し、中途退学を防ぐ取り組み。
×
『学生アンケートの活用』とは?
新入生や在学している学生に対し、大学の授業やカリキュラム、学修状況などについてアンケートを行い、その結果を分析・活用して、教育方法やプログラムの改善などに活かす取り組み。
×
『アセスメントポリシー』とは?
学生の学修成果の評価(アセスメント)について、目的や達成するべき質的水準と具体的な評価の実施方法などについて定めた学内の方針を活用した取り組み。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『成績評価の厳格な運用』とは?
明確な成績評価の基準を定めて厳格に運用して、単位取得や進級などを判定することで、教育の「質の保証」を実現する取り組み。