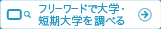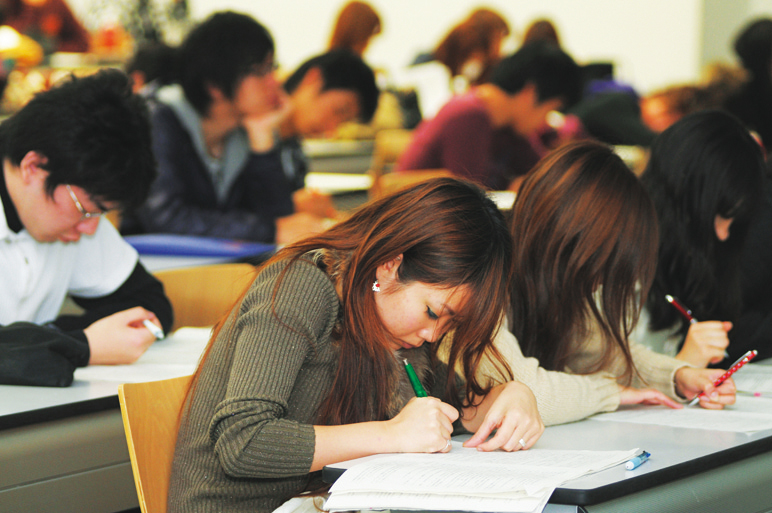法政大学
法政大学
法学部

- ディプロマポリシー
-
詳細リンク(外部サイトへ)
- カリキュラムポリシー
-
詳細リンク(外部サイトへ)
カリキュラム
- 教育内容の体系化とその充実?
-
 ●取り組みの内容法律学科では、より実務的な法学教育を意識して、1・2年次で、基礎となる法律学教育の充実や学問的な視野を広げる科目群を拡充し、3・4年次には、各志望に適合的な科目群に配慮しています。ガイドライン型のコース制を採用し、各コースのアドバイスに従って履修すれば、系統的でバランスの取れた勉強ができる編成になっています。また2020年度に法曹コースを設置しました。法曹コース所属生は独自のカリキュラムで、3年次での早期卒業と法科大学院への進学、その後の法曹三者を目指すコースです。
●取り組みの内容法律学科では、より実務的な法学教育を意識して、1・2年次で、基礎となる法律学教育の充実や学問的な視野を広げる科目群を拡充し、3・4年次には、各志望に適合的な科目群に配慮しています。ガイドライン型のコース制を採用し、各コースのアドバイスに従って履修すれば、系統的でバランスの取れた勉強ができる編成になっています。また2020年度に法曹コースを設置しました。法曹コース所属生は独自のカリキュラムで、3年次での早期卒業と法科大学院への進学、その後の法曹三者を目指すコースです。
政治学科では、多くの選択科目を提供しつつ、新たに選択必修科目(学科基礎科目群・政治学基礎科目群・展開科目群で構成)を設けるなど、学生の自主性を重視し最大限自由に組むことができるような、また、科目履修が偏ることなく、履修から得られる知見が綜合化されるような科目配置をしています。
国際政治学科では、1・2年次は、少人数制で集中的に英語力を鍛えます。専門科目の履修は2年次から本格化し、「アジア国際政治コース」「グローバル・ガバナンスコース」に分かれ体系的に学んでいきます。 - 教養・リベラルアーツ教育?
-
 ●取り組みの内容リベラルアーツセンターを設置し、法学部を含む市ケ谷キャンパスの各学部で行われている教養教育全体の基本理念・目的やカリキュラムの再設計をはじめとして、初年次教育、外国語教育、ICT教育、建学の精神の教育、キャリア教育などの在り方を再検討し、学士課程教育の重要な柱の1つを構成する教養教育に関する共通カリキュラムの開発支援を行っています。また、国際政治学科では、国際政治学科生用の英語クラスを設け、独自のカリキュラムでの英語教育を行っています。
●取り組みの内容リベラルアーツセンターを設置し、法学部を含む市ケ谷キャンパスの各学部で行われている教養教育全体の基本理念・目的やカリキュラムの再設計をはじめとして、初年次教育、外国語教育、ICT教育、建学の精神の教育、キャリア教育などの在り方を再検討し、学士課程教育の重要な柱の1つを構成する教養教育に関する共通カリキュラムの開発支援を行っています。また、国際政治学科では、国際政治学科生用の英語クラスを設け、独自のカリキュラムでの英語教育を行っています。
教育方法
- アクティブラーニング?
-
 ●取り組みの内容1年次の「法学入門演習」「政治学入門演習」は、教員の指導の下、学生が自己の意見を論理的に表明し、ほかの人の議論を理解する演習形式の授業です。また、国際政治学科専門科目の「実践講座科目」では、英語によるプレゼンテーションやディベートの科目を開講し、講義型ではなく双方向の授業を行っています。
●取り組みの内容1年次の「法学入門演習」「政治学入門演習」は、教員の指導の下、学生が自己の意見を論理的に表明し、ほかの人の議論を理解する演習形式の授業です。また、国際政治学科専門科目の「実践講座科目」では、英語によるプレゼンテーションやディベートの科目を開講し、講義型ではなく双方向の授業を行っています。
3学科とも専門科目の「演習」では、少人数で専門研究を自主的に行っています。 - 課題解決型学習(PBL)?
-
 ●取り組みの内容専門科目の「演習」では、判例、時事問題、国際問題等を素材として課題解決型学習(PBL)を実施しているものがあります。
●取り組みの内容専門科目の「演習」では、判例、時事問題、国際問題等を素材として課題解決型学習(PBL)を実施しているものがあります。 - 少人数教育?
-
 ●取り組みの内容1年次から演習の他に、講義でも演習形式の双方向教育で少人数教育を行っている科目があります。
●取り組みの内容1年次から演習の他に、講義でも演習形式の双方向教育で少人数教育を行っている科目があります。
学びの支援
- 学びの組織的な支援?
-
 ●取り組みの内容各学科とも基礎的な知識や考え方を身につけることができるように、1年次には入門的な科目を開講しています。
●取り組みの内容各学科とも基礎的な知識や考え方を身につけることができるように、1年次には入門的な科目を開講しています。
また、オフィスアワーを設定し、学部教員が授業時間外でも授業に関する質問・相談に応じています。 - 学修成果のフィードバック?
-
 ●取り組みの内容3学科とも専門科目の「演習」では、論文集の作成や報告会などを実施しています。
●取り組みの内容3学科とも専門科目の「演習」では、論文集の作成や報告会などを実施しています。 - 初年次教育?
-
 ●取り組みの内容各学科とも基礎的な知識や考え方を身につけることができるように、1年次には入門的な基礎科目や演習科目を開講しています。
●取り組みの内容各学科とも基礎的な知識や考え方を身につけることができるように、1年次には入門的な基礎科目や演習科目を開講しています。
「読む力」を身につけ、レジュメ・レポートの書き方、資料の収集方法など、大学での学習に必要となる基本的な能力を習得するための導入教育を行っています。 - 中途退学防止?
-
 ●取り組みの内容4月のガイダンス時に、再履修が必要な学生のためのガイダンスを実施しています(語学・体育のみ)。履修登録の結果、必要単位不足等のエラーメッセージの出た学生には、窓口で履修相談・指導を行っています。また、成績不振者には学部教員が個別に面談を行います。なお、保証人には前年度までの成績を郵送し、学生の学習到達度をお知らせしています。
●取り組みの内容4月のガイダンス時に、再履修が必要な学生のためのガイダンスを実施しています(語学・体育のみ)。履修登録の結果、必要単位不足等のエラーメッセージの出た学生には、窓口で履修相談・指導を行っています。また、成績不振者には学部教員が個別に面談を行います。なお、保証人には前年度までの成績を郵送し、学生の学習到達度をお知らせしています。 - TA・RA・SA・メンターの活用?
-
 ●取り組みの内容授業運営の改善を目的として、TA(Teaching Assistant)やSA(Student Assistant)を活用しています。また、授業外での勉学支援でも2020年度から「ラーニング・サポーター」制度が導入されました。
●取り組みの内容授業運営の改善を目的として、TA(Teaching Assistant)やSA(Student Assistant)を活用しています。また、授業外での勉学支援でも2020年度から「ラーニング・サポーター」制度が導入されました。 - 学生アンケートの活用?
-
 ●取り組みの内容全学的な取り組みとして、教育および学びの質を向上するためにFD推進センターを設置し、その活動の一環として「学生による授業改善アンケート」を実施しています。アンケートは、授業ごとに集計され、担当教員にその結果が通知されます。シラバスには、授業改善アンケートによる気づきの欄が設けられており、授業の担当者がどのような改善の努力を行っているかがわかるようになっています。
●取り組みの内容全学的な取り組みとして、教育および学びの質を向上するためにFD推進センターを設置し、その活動の一環として「学生による授業改善アンケート」を実施しています。アンケートは、授業ごとに集計され、担当教員にその結果が通知されます。シラバスには、授業改善アンケートによる気づきの欄が設けられており、授業の担当者がどのような改善の努力を行っているかがわかるようになっています。 - インターンシップ?
-
 ●取り組みの内容専門科目に「Global Internship」を設置しています。この科目では、前期における教員および外部講師による講義に引き続き、夏休み期間中に公共政策関連機関(福祉施設、NGO/NPOなど)で1週間程度の自習を体験し、後期にその体験内容をプレゼンテーションとレポート発表を行い、各政策分野への理解を深めます。
●取り組みの内容専門科目に「Global Internship」を設置しています。この科目では、前期における教員および外部講師による講義に引き続き、夏休み期間中に公共政策関連機関(福祉施設、NGO/NPOなど)で1週間程度の自習を体験し、後期にその体験内容をプレゼンテーションとレポート発表を行い、各政策分野への理解を深めます。 - キャリア教育?
-
 ●取り組みの内容「法律実務入門」「法律学特講(企業法務への案内)」「外交総合講座」「国際協力講座」において実務家による講義と意見交換を行い現場の最前線を身近に体験することができます。また、キャリア教育に役に立つ寄付講座もあります。
●取り組みの内容「法律実務入門」「法律学特講(企業法務への案内)」「外交総合講座」「国際協力講座」において実務家による講義と意見交換を行い現場の最前線を身近に体験することができます。また、キャリア教育に役に立つ寄付講座もあります。 - 資格取得(国家資格受験資格)?
-

学修についての評価
- アセスメントポリシー?
-

- 外部テストの活用?
-
 ●取り組みの内容入学時に実施するELPAのスコアをもとに、英語クラスを習熟度別で編成しています。これにより、学生個人のレベルに合わせた授業の実施が可能になっています。
●取り組みの内容入学時に実施するELPAのスコアをもとに、英語クラスを習熟度別で編成しています。これにより、学生個人のレベルに合わせた授業の実施が可能になっています。
毎年6月と10月にTOEIC(R)-IPを学内で無料で受験できます。国際政治学科の「Intensive English」、「Debate」、「Essay Writing」、「Negotiation and Mediation Communication Skills」、「海外メディア分析実習」は、TOEICの成績に応じてクラス編成します。 - GPAの活用?
-
 ●取り組みの内容GPAをもとに学生の成績状況を随時把握し、学習指導に活用しています。年間GPA上位5%の学生を対象に、他学部公開科目を年間履修上限を超えて履修できる「成績優秀者他学部公開科目制度」を設けています。また、奨学金の受給資格としても活用していて、前年度の成績優秀者には奨学金を給付するとともに、表彰も行います。その他、派遣留学生の選抜や成績不振者に対する教員サポートにもGPAを活用しています。
●取り組みの内容GPAをもとに学生の成績状況を随時把握し、学習指導に活用しています。年間GPA上位5%の学生を対象に、他学部公開科目を年間履修上限を超えて履修できる「成績優秀者他学部公開科目制度」を設けています。また、奨学金の受給資格としても活用していて、前年度の成績優秀者には奨学金を給付するとともに、表彰も行います。その他、派遣留学生の選抜や成績不振者に対する教員サポートにもGPAを活用しています。 - 学修成果のフィードバック?
-
 ●取り組みの内容3学科とも専門科目の「演習」では、論文集の作成や報告会などを実施しています。
●取り組みの内容3学科とも専門科目の「演習」では、論文集の作成や報告会などを実施しています。
×
『教育内容の体系化とその充実』とは?
教育の目的や成果を明確に設定し、その達成のため、各授業間の関連性を明確にするなど、体系的な学びを可能にすることで、教育内容の一層の充実を図る取り組み。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『教養・リベラルアーツ教育』とは?
幅広い分野の教養などを身につけ、専門知識に偏らない汎用的能力を育成するために大学・短期大学で行われる教育。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『アクティブラーニング』とは?
一方的に講義を聴くスタイルの授業ではなく、学生が積極的に学修に参加することを取り入れ、能動的(アクティブ)な学びを促すことで、知識をしっかり定着させることを目的とした学習方法。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『課題解決型学習(PBL)』とは?
プロジェクト活動を通じ、学生が自主的・自律的に課題を発見・解決する過程において、それまでに得た知識を実践的に活用することや、より学びを深くすることなどを目的とした学習方法。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『少人数教育』とは?
学習効果を高めるために、1人の教員が教える学生の数を少なくして授業を行う学習方法。
×
『学びの組織的な支援』とは?
学校側が組織的かつ恒常的に学びに対するサポート体制を用意し、授業に対する学生の不安を解消するなどの学びに対する様々な支援をすることで、より学習効果を高める取り組み。
×
『学修成果のフィードバック』とは?
授業や講義などを通して学生が学んだ知識や技術や成績などの「学修成果」を、可視化するなどして学生にわかりやすく還元することで、学生自らの学びへの姿勢を支援する取り組み。
×
『初年次教育』とは?
大学や短期大学の新入生を対象に、高校までの学びから、能動的な大学・短期大学での学びにスムーズに移行するための基本的なスキルなどを身につける教育プログラム。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『中途退学防止』とは?
学びに対する意欲の減少などを理由に修業期間の途中で学校を退学しようとする学生に対して、学びのサポートを行うことで、教育の問題解決を図り、学びの環境を改善し、中途退学を防ぐ取り組み。
×
『TA・RA・SA・メンターの活用』とは?
大学院生による教育補助(TA)、大学院生等による研究補助(RA)、学生による教育補助(SA)、後輩を多方面で支援する先輩(メンター)を教育研究活動などに活用する取り組み。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『学生アンケートの活用』とは?
新入生や在学している学生に対し、大学の授業やカリキュラム、学修状況などについてアンケートを行い、その結果を分析・活用して、教育方法やプログラムの改善などに活かす取り組み。
×
『インターンシップ』とは?
自らの専攻や将来のキャリアに関連した就業体験や社会貢献活動に参加する制度を授業やカリキュラムに取り込むことで、学生が学問や研究分野への理解をより深めるための取り組み。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『キャリア教育』とは?
大学や短期大学の学修プログラムの一環として、カリキュラムに社会人・職業人として必要な能力などを身に付けるための科目等を組み入れ、学生のキャリア形成計画や目標設定を支援する教育。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『資格取得(国家資格受験資格)』とは?
カリキュラムの整備や授業内容の工夫などを行い、学生が正課の授業を受けることで国家資格試験を受験し、合格することを目的に支援する取り組み。
×
『アセスメントポリシー』とは?
学生の学修成果の評価(アセスメント)について、目的や達成するべき質的水準と具体的な評価の実施方法などについて定めた学内の方針を活用した取り組み。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『外部テストの活用』とは?
TOEICやTOEFLといった学校の外部で行われているテストを、大学や短期大学の入試や単位認定などに活用する取り組み。
×
『GPAの活用』とは?
科目の成績評価に応じてポイント(例:5段階評価A〜Eに対し4〜0点等)を付与し、その平均点(Grade Point Average)による学習成果の評価方法を大学や短期大学での教育に活用する取り組み。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『学修成果のフィードバック』とは?
授業や講義などを通して学生が学んだ知識や技術、成績などの「学修成果」を活用し、学生の学びの振り返りを促すことで、学びの定着を図ることを目的とした取り組み。
新着一覧
- 法学部(通)
- 文学部(通)
- 経済学部(通)
- 文学部
- 法学部
- 経済学部
- 社会学部
- 経営学部
- 人間環境学部
- 国際文化学部
- 現代福祉学部
- 情報科学部
- キャリアデザイン学部
- デザイン工学部
- 理工学部
- 生命科学部
- グローバル教養学部
- スポーツ健康学部
- 人文科学研究科(修士)
- 人文科学研究科(博士)
- 人間社会研究科(修士)
- 人間社会研究科(博士)
- 情報科学研究科(修士)
- 情報科学研究科(博士)
- 経済学研究科(修士)
- 経済学研究科(博士)
- 法学研究科(修士)
- 法学研究科(博士)
- 政治学研究科(修士)
- 政治学研究科(博士)
- 社会学研究科(修士)
- 社会学研究科(博士)
- 経営学研究科(修士)
- 経営学研究科(博士)
- 法務研究科(専門職学位)
- イノベーション・マネジメント研究科(専門職学位)
- 国際文化研究科(修士)
- 国際文化研究科(博士)
- デザイン工学研究科(修士)
- デザイン工学研究科(博士)
- 公共政策研究科(修士)
- 公共政策研究科(博士)
- 理工学研究科(修士)
- 理工学研究科(博士)
- キャリアデザイン学研究科(修士)
- スポーツ健康学研究科(修士)
- スポーツ健康学研究科(博士)
- 政策創造研究科(修士)
- 政策創造研究科(博士)