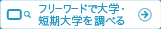大分県(所在地都道府県)/大学学部(部門種別)

別府大学
別府大学


別府大学
別府大学
食物栄養科学部

- インターンシップ?
-
 ●取り組みの内容食物栄養学科は、管理栄養士養成施設カリキュラムに定められた臨地実習を必修とし、実践力を十分に習得した管理栄養士の養成を目指している。発酵食品学科は、3単位の企業実習(インターンシップ)を選択必修として社会で役立つ実践力を備えた人材育成を目指しており、実際に就職内定に繋がることもしばしばで一定の成果を上げている。●取り組みの目標インターンシップを通して、現実の社会の中の企業ほかインターンシップ先の職場の役割やそこで働く人びとの役割を理解し、社会の一員としての心構えや、他人を理解し、恊働していくために必要なことなどを知り、就職活動に活かすことを目標とする。
●取り組みの内容食物栄養学科は、管理栄養士養成施設カリキュラムに定められた臨地実習を必修とし、実践力を十分に習得した管理栄養士の養成を目指している。発酵食品学科は、3単位の企業実習(インターンシップ)を選択必修として社会で役立つ実践力を備えた人材育成を目指しており、実際に就職内定に繋がることもしばしばで一定の成果を上げている。●取り組みの目標インターンシップを通して、現実の社会の中の企業ほかインターンシップ先の職場の役割やそこで働く人びとの役割を理解し、社会の一員としての心構えや、他人を理解し、恊働していくために必要なことなどを知り、就職活動に活かすことを目標とする。 - キャリア教育?
-
 ●取り組みの内容食物栄養学科、発酵食品学科共に、就職率の高い学科を目指し、キャリア教育に力を入れている。毎年、新入生を対象に行うオリエンテーションでは就職に向けて1年次から取り組まなければならない重要な事項についての講義を行ったり、また、工場見学を実施して実地の仕事に関して理解を深める取り組みを行っている。初年次教育(導入演習、基礎演習)においてもたびたび将来の目標を立てることの大切さや目標実現のための方法の紹介、職務の内容の紹介,履歴書の書き方などの指導を行っている。学年進行とともに,食物栄養学科はそれぞれの職域で活躍する管理栄養士による授業をオムニバスで組み、仕事内容への理解を深めさせるとともに就きたい仕事について考えさせる取り組みを行っている。専門演習に本学部卒業生を招聘し、在学生に日ごろの業務や就職活動について話してもらい交流する取り組みを行っている。
●取り組みの内容食物栄養学科、発酵食品学科共に、就職率の高い学科を目指し、キャリア教育に力を入れている。毎年、新入生を対象に行うオリエンテーションでは就職に向けて1年次から取り組まなければならない重要な事項についての講義を行ったり、また、工場見学を実施して実地の仕事に関して理解を深める取り組みを行っている。初年次教育(導入演習、基礎演習)においてもたびたび将来の目標を立てることの大切さや目標実現のための方法の紹介、職務の内容の紹介,履歴書の書き方などの指導を行っている。学年進行とともに,食物栄養学科はそれぞれの職域で活躍する管理栄養士による授業をオムニバスで組み、仕事内容への理解を深めさせるとともに就きたい仕事について考えさせる取り組みを行っている。専門演習に本学部卒業生を招聘し、在学生に日ごろの業務や就職活動について話してもらい交流する取り組みを行っている。 - 資格取得(国家資格受験資格)?
-
 ●取り組みの内容【食物栄養学科】
●取り組みの内容【食物栄養学科】
・管理栄養士国家試験受験資格 ・栄養教諭1種免許 ・栄養士免許 ・食品衛生管理者
・食品衛生監視員任用資格 ・フードスペシャリスト資格認定試験受験資格 ・司書
【発酵食品学科】
・高等学校教諭1種免許状(理科) ・中学校教諭1種免許状(理科) ・学芸員
・食品衛生管理者 ・食品衛生監視員 ・フードサイエンティスト受験資格 ・司書 ・司書教諭 ・バイオ技術者(中級・上級)受験資格 - 卒後調査の活用?
-
 ●取り組みの内容食物栄養科学部では、卒業時アンケート調査を実施しており、卒業生の意見を参考にカリキュラムの改正等に活用している。
●取り組みの内容食物栄養科学部では、卒業時アンケート調査を実施しており、卒業生の意見を参考にカリキュラムの改正等に活用している。
進路選択教育の取り組み
取得可能な資格
(令和07年07月24日時点)-
●卒業時取得可能な資格食物栄養科学部 文中の( )内の数字は令和5年度卒業生の取得件数
教育職員免許状
食物栄養学科 栄養教諭1種免許状(7)
発酵食品学科 中学校教諭1種免許状理科(3)、高等学校教諭1種免許状理科(4)
栄養士免許証取得資格 (食物栄養学科:61)
各課程の科目の履修によって取得できる資格
学芸員(1)、司書(2)、司書教諭(1)
・学芸員とは(発酵食品学科で取得可能)
博物館法で学芸員は、「博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる」としています。学芸員の資格を取得するには、博物館法に定められた科目を大学等で履修して単位を修得することが一般的です。
・司書とは
図書館に置かれる専門的職員(専門職)のことを司書といい、その職に就くための国家資格のことです。司書の資格を取得するには、図書館法に定められた科目を大学等で履修し、単位を修得することが一般的です。
・司書教諭とは(発酵食品学科で取得可能)
学校図書館(図書室などを含む)に置かれる教員のことをいい。その職に就くための国家資格のことです。司書教諭に就くには、司書資格にあわせて教育職員免許状を取得しなければなりません。
栄養教諭1種中学校教諭1種 理科高等学校教諭1種 理科栄養士司書・学校図書館司書教諭・学芸員●受験資格獲得の国家試験専門科目の履修によって取得できる国家試験等受験資格
食物栄養学科 管理栄養士国家試験(受験者54:内試験合格者数39)
・管理栄養士とは
管理栄養士(英: registered dietitian)は、栄養士法に定められる資格のこと。昭和37年の栄養士法の一部改正時に設けられた。名称独占資格の一つです。管理栄養士国家試験に合格し取得することができます。管理栄養士の定義は、「厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行う者」とされています。
管理栄養士●その他の取得可能な資格教養科目・専門科目を履修して取得できる資格
食品衛生監視員任用資格及び食品衛生管理者任用資格
・食品衛生監視員とは
行政警察活動として、食品衛生法に規定された職務及び食品衛生に関する指導を行う技術系公務員。主に国の検疫所と地方自治体の保健所に所属し、食品の検査や食中毒の調査、食品製造業や飲食店の監視(英語:inspectionの訳語)、指導及び教育を行っている。
・食品衛生管理者とは
食品衛生法により食品衛生法施行令に指定のある食肉製品製造業など製造又は加工の過程において、特に衛生上の考慮を必要とする一定の食品又は食品添加物の製造又は加工を行う営業者が、その施設ごとに必置の義務がある有資格者です。
専門科目の履修によって取得できる国家試験等受験資格
食物栄養学科 フードスペシャリスト認定証(8)
発酵食品学科 フードサイエンティスト認定証(20)
・フードスペシャリストとは
フードスペシャリストの資格名称を使用するためには、本学のフードスペシャリスト養成課程を履修し、日本フードスペシャリスト協会が実施する認定試験に合格する必要があります。
・フードサイエンティスト(食品科学技術認定証)とは
フードサイエンティストの資格名称を使用するためには、本学のフードサイエンティスト養成課程を履修し、食品科学教育協議会が実施する資格認定研修を受講し、認定証の交付を受ける必要があります。
卒業後の進路
- 主な進学・就職先
-
食物栄養学科については栄養士・管理栄養士業務が大部分を占め、給食受託会社、病院、福祉施設、企業の給食部門がほぼ同数で、公務員、一般の業務に就くものは毎年数名以下である。進学は毎年1〜2名で、地元の大学院や専門学校である。発酵食品学科についてはほとんどの就職先が食品関連の企業であり、中でも発酵・醸造企業、食品製造企業の技術部門、研究開発部門、品質管理部門、流通部門である。進学は毎年2〜3名で、主に本学大学院や国立の農学系大学院である。
卒業生の声
-
【食物栄養学科】
(R.3.3月卒業、17期生)私は一次予防に魅力を感じその中で子どもから高齢者まで幅広い世代と直接接することのできる市町村の栄養士として勤務しています。栄養食事指導の対象者本人だけでなく、その方を通じて家族へ、そこから町全体が健康になるような働きかけがしたいと思っています。
【発酵食品学科】
(H30年度卒)私は大学を卒業後、大分市役所へ就職しました。市役所へは、化学という専門職で入り、今は環境対策課に所属しています。仕事内容としては、主に大気・騒音・悪臭・水質等の法律を基に工場、事業場の取り締まりを行っています。現在の職場では、発酵食品学科で学んだ水処理(生物化学的酸素要求量BODや化学的酸素要求量COD)の知識が役立っています。化学職は行く部署が決まっていて、今後は保健所の衛生課や水道局へ行くこととなります。就職して1年数ヶ月ですが、今後保健所の衛生課へ行き、学科で学んだ食品衛生についての知識を活かしていきたいです。
進路データ集
- 卒業者
-
>>>>
卒業者 2022年4月〜2023年3月 114 2023年4月〜2024年3月 115 2024年4月〜2025年3月 86 - 進路別
-
>>>>
男 女 計 進学者 大学院研究科 0 1 1 大学学部 0 0 0 短期大学本科 0 0 0 専攻科 0 0 0 別科 0 0 0 就職者 正規の職員、自営業主等 20 60 80 正規の職員等でない者 0 2 2 臨床研修医(予定者を含む) 0 0 0 専修学校・外国の学校等の入学者 0 0 0 一時的な仕事に就いた者 0 2 2 上記以外の者 進学準備中の者 0 0 0 就職準備中の者 0 0 0 その他 1 0 1 不詳等 0 0 0 計 21 65 86 上記進学者のうち就職している者 0 0 0
卒業者数
×
『インターンシップ』とは?
進路指導として学生の就業体験や社会貢献活動への参加を制度化し、学生が自らの適性や将来のキャリア、業種や職種等に対する理解を深めたうえでの進路選択を実現するための取り組み。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『キャリア教育』とは?
学生に勤労観・職業観及び職業に関する知識や技能を身につけるための教育を行い、自らの個性や適性を理解し、主体的に進路を選択する能力を育てるための教育。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『資格取得(国家資格受験資格)』とは?
国家資格試験を受験し合格することを目的に、学校が資格取得講座などを用意し、学生が望む進路を実現するための支援をする取り組み。
×
『卒後調査の活用』とは?
卒業生を対象に、在学中の進路選択のための教育内容が就職や進学にどのように役立ったなどについて調査し、その結果を在学生の進路選択の教育に活用する取り組み。
用語辞典を開いて詳しく調べる
進路・就職情報目次