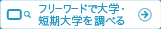奈良県(所在地都道府県)/大学院研究科(部門種別)

帝塚山大学
帝塚山大学

















帝塚山大学
帝塚山大学
心理科学研究科(博士後期課程)

外国人留学生受入
- 外国人留学生受入?
-
 ●取り組みの内容外国人留学生の受入は行っていますが、外国人を対象とした入学試験の実施は行っていません。
●取り組みの内容外国人留学生の受入は行っていますが、外国人を対象とした入学試験の実施は行っていません。
外国人教員・留学生データ集
大学院の教員数は、調査を行っていないため表示されません。(大学院大学を除く)
修業期間の多様化
- 飛び入学・早期卒業・長期履修?
-
 ●取り組みの内容早期修了については、通常、博士後期課程において3年以上の在学年数が必要となりますが、課程の定める授業科目の所定単位を修得し、かつ、優れた研究業績を挙げた者で心理科学研究科委員会において認められた場合は、2年の在学年数で修了することができます。
●取り組みの内容早期修了については、通常、博士後期課程において3年以上の在学年数が必要となりますが、課程の定める授業科目の所定単位を修得し、かつ、優れた研究業績を挙げた者で心理科学研究科委員会において認められた場合は、2年の在学年数で修了することができます。
連携活動
- 学校間連携?
-
 ●取り組みの内容2011年(平成23年)より他大学院と合同心理学研究会を開催し、教員や大学院生が研究発表を行っています。また、教員および大学院生の研修、相互研究、出版物の刊行などについて相互の協力関係を保つようにしています。
●取り組みの内容2011年(平成23年)より他大学院と合同心理学研究会を開催し、教員や大学院生が研究発表を行っています。また、教員および大学院生の研修、相互研究、出版物の刊行などについて相互の協力関係を保つようにしています。 - 地域連携?
-
 ●取り組みの内容地元奈良、大阪を中心とする外部の行政機関や小学校、中学校、高等学校、大学、大学院や教育委員会等の教育機関、民間産業組織体、NPO団体との連携を年々強めています。奈良県内の小中学校における心理ボランティア活動や発達障害者支援センターとの連携によるペアレントトレーニング研修会、幼稚園児や保護者への支援、幼稚園教員のスキルアップへの支援等を行う幼稚園キンダーカウンセリング事業などに参加させることにより、地域支援活動を行っています。また、「心のケアセンター」では、子どもの行動や発達・育児に関すること、学校生活上の諸問題、思春期・青年期の心の問題、成人の家庭生活・職業生活に関わる問題、発達障害に関わる問題、家庭内暴力・被害者支援の問題、老後の生き方や不安に関する問題など、年間2,000人を超える方々の相談に応じています。相談には公認心理師や臨床心理士の資格をもつ教員、相談員のほか、それらの資格の取得をめざす研修生、大学院生も相談に応じています。また、学外組織と連携して安全な交通環境の構築、特に高齢者ドライバーや子どもの交通安全をめざした研究にも取り組んでいます。
●取り組みの内容地元奈良、大阪を中心とする外部の行政機関や小学校、中学校、高等学校、大学、大学院や教育委員会等の教育機関、民間産業組織体、NPO団体との連携を年々強めています。奈良県内の小中学校における心理ボランティア活動や発達障害者支援センターとの連携によるペアレントトレーニング研修会、幼稚園児や保護者への支援、幼稚園教員のスキルアップへの支援等を行う幼稚園キンダーカウンセリング事業などに参加させることにより、地域支援活動を行っています。また、「心のケアセンター」では、子どもの行動や発達・育児に関すること、学校生活上の諸問題、思春期・青年期の心の問題、成人の家庭生活・職業生活に関わる問題、発達障害に関わる問題、家庭内暴力・被害者支援の問題、老後の生き方や不安に関する問題など、年間2,000人を超える方々の相談に応じています。相談には公認心理師や臨床心理士の資格をもつ教員、相談員のほか、それらの資格の取得をめざす研修生、大学院生も相談に応じています。また、学外組織と連携して安全な交通環境の構築、特に高齢者ドライバーや子どもの交通安全をめざした研究にも取り組んでいます。
社会貢献
- ボランティア活動?
-
 ●取り組みの内容現在、心理学部心理学科、大学院心理科学研究科全体でボランティア活動を勧めています。一例として、心のケアセンターで行っている「きらきらプラネット」では、対人面や社会的場面において困難を抱える子どもたちへのグループ支援とその保護者へのサポートを実施します。大学院生が主体的にこの運営にかかわり、地域で特別なニーズのある方々への支援に貢献しています。
●取り組みの内容現在、心理学部心理学科、大学院心理科学研究科全体でボランティア活動を勧めています。一例として、心のケアセンターで行っている「きらきらプラネット」では、対人面や社会的場面において困難を抱える子どもたちへのグループ支援とその保護者へのサポートを実施します。大学院生が主体的にこの運営にかかわり、地域で特別なニーズのある方々への支援に貢献しています。
×
『外国人留学生受入』とは?
国際交流の活性化や教育の活性化を図ることを目的として、制度的に海外からの留学生を日本の大学・短期大学等に受け入れる取り組み。
×
『飛び入学・早期卒業・長期履修』とは?
より効果的な教育を行うことなどを目的として、通常よりも早い大学への入学や卒業を許可したり、通常の修業期間(大学であれば4年)よりも長い修業期間の制度を作る取り組み。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『学校間連携』とは?
主に高等教育機関(大学、短期大学、高等専門学校、専門学校など)同士がより良い教育や充実した研究活動をすることを目的に連携協力する取り組み。
×
『地域連携』とは?
大学や短期大学が地域社会のニーズに応え、地域と積極的に関わることで、地域の活性化などに貢献し、地域の各市町村などと連携する取り組み。
×
『ボランティア活動』とは?
学生が自発的に行うボランティア活動に対して、大学や短期大学が活動の支援や単位認定などをすることにより、学生生活が活性化することを目的とした取り組み。
更新情報
2025/07/14 更新
今年度の財務情報を公表しました。
今年度の財務情報を公表しました。
2025/07/10 更新
社会人や地域の方々を対象に様々な公開講座を開講しています
社会人や地域の方々を対象に様々な公開講座を開講しています
2025/07/10 更新
今年度の入試情報をご案内します。
今年度の入試情報をご案内します。
2025/07/10 更新
今年度のオープンキャンパス情報はこちらから!
今年度のオープンキャンパス情報はこちらから!
2024/07/13 更新
今年度の入試情報をご案内します。
今年度の入試情報をご案内します。
2024/07/13 更新
今年度のオープンキャンパス情報はこちらから!
今年度のオープンキャンパス情報はこちらから!
2024/07/11 更新
7月20日(土)大学院心理科学研究科 入試説明会・相談会 開催
7月20日(土)大学院心理科学研究科 入試説明会・相談会 開催
2024/06/12 更新
今年度の財務情報を公表しました。
今年度の財務情報を公表しました。
2023/07/11 更新
今年度のオープンキャンパス情報はこちらから!
今年度のオープンキャンパス情報はこちらから!
2023/07/11 更新
今年度の入試情報をご案内します。
今年度の入試情報をご案内します。
2023/07/11 更新
今年度の財務情報を公表しました。
今年度の財務情報を公表しました。
2023/06/12 更新
7月8日(土)大学院心理科学研究科 入試説明会・相談会 開催
7月8日(土)大学院心理科学研究科 入試説明会・相談会 開催
2022/06/22 更新
7月9日(土)大学院心理科学研究科 入試説明会・相談会 開催
7月9日(土)大学院心理科学研究科 入試説明会・相談会 開催
2020/07/10 更新
7月25日(土) 大学院入試個別説明会 開催
7月25日(土) 大学院入試個別説明会 開催
2018/04/23 更新
大学院 心理科学研究科 学術イベント開催
大学院 心理科学研究科 学術イベント開催
様々な取組目次