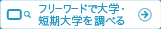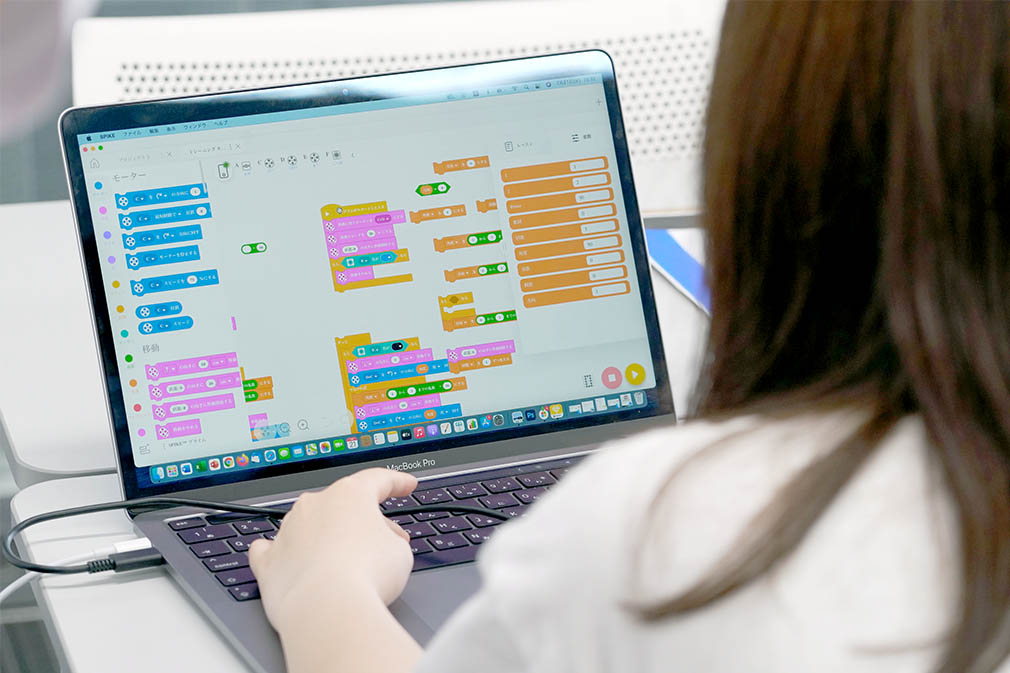京都精華大学

外国人教員
- 外国人教員雇用・派遣受入?
-
 ●取り組みの内容本学ではダイバーシティ推進宣言を表明し、ダイバーシティ推進の視点に立った教育・研究・就業環境の整備を推進しております。教員公募においても女性及び海外研究者の応募を歓迎します。詳細リンク(外部サイトへ)
●取り組みの内容本学ではダイバーシティ推進宣言を表明し、ダイバーシティ推進の視点に立った教育・研究・就業環境の整備を推進しております。教員公募においても女性及び海外研究者の応募を歓迎します。詳細リンク(外部サイトへ)
- 外国人留学生受入?
-
 ●取り組みの内容京都精華大学では、現在、在学生の約30%である1,173人が外国人留学生です。
●取り組みの内容京都精華大学では、現在、在学生の約30%である1,173人が外国人留学生です。
世界へ学生を送り出すだけでなく、正規留学、交換留学、短期プログラムなど様々な形で世界各国からの留学生を積極的に受け入れています。授業や作品制作の場など、学内においてもお互いに異なる文化や表現に触れ合う機会が多くあります。
留学生を対象とした日本語学修支援室では、留学生の自主的な日本語学習をサポートしています。日本語が分からず困っていることがある、学習方法がわからないなど、日本語学習に関することなら何でも相談できます。文化の違いや学生生活での困りごとなど、学習以外のことでも相談することが可能です。
iC-Cube(Inter-Cultural Communication Commons)は、多文化交流や異文化理解のために開設された、留学生と国内学生の共同学習スペースです。英語をはじめとする各国言語の言語交換、講演会、ワークショップなどの国際交流イベントを開催しています。 - 海外留学、スタディ・アブロード?
-
 ●取り組みの内容京都精華大学は、京都精華大学では、アメリカやヨーロッパだけでなく、中東、アジアなど多様な地域の31大学と協定を結んでいます。
●取り組みの内容京都精華大学は、京都精華大学では、アメリカやヨーロッパだけでなく、中東、アジアなど多様な地域の31大学と協定を結んでいます。
先進的な制作・研究を行う教員・学生との交流は、語学力の向上に加え、帰国後の創作活動を飛躍的に発展させてきました。毎年多くの学生が世界各地へと学びの舞台を拡げています。
■海外ショートプログラム
夏季休暇、春季休暇中に行う短期間の海外研修プログラムです。このプログラムには、教員が引率する「教員引率型」、学生の皆さんが個々の趣向や目的に合わせ自主性をもって参加する「スタディツアー参加型」、語学を修得するという目的に特化した「語学特化型」の3種があります。
■交換留学プログラム
交換留学は、本学に在籍したまま協定を結んでいる大学へ1学期間留学できる制度です。留学先協定校での授業料は免除され、現地で取得した単位は卒業要件単位として認定されるので4年間での卒業が可能です。
外国人留学生受入
留学支援
- 学年別
-
男 女 計 1年 100 187 287 2年 123 193 316 3年 119 186 305 4年 118 147 265 大学院 29 55 84 計 489 768 1,257
外国人留学生
- 学校間連携?
-
 ●取り組みの内容1.大学コンソーシアム京都
●取り組みの内容1.大学コンソーシアム京都
大学コンソーシアム京都とは、京都に所在する大学・短期大学が共同で運営する大学・短期大学の共同体で、1994年度に発足しました。大学コンソーシアム京都は、以下に記載する単位互換制度をはじめとした大学間の教育研究交流に関する事業、学生交流に関する事業、地域社会と大学の交流・連携に関する事業、教職員交流に関する事業などを行っています。
2.単位互換協定
単位互換制度とは、学生のみなさんが他大学・短期大学の授業を受講し、その単位を所属する大学(本学)の[卒業に要する単位]として利用できる制度です。この制度の対象となる学生は、大学コンソーシアム京都「単位互換包括協定」に参加する大学に所属する学生で、本学はこの協定を締結しています。本学の学生のみなさんが大学コンソーシアム京都の開講授業を履修する場合、その受講料は無料です。授業は、授業を開講する大学もしくは、キャンパスプラザ京都(京都駅前)で行われます。 - 高大連携プログラム?
-
 ●取り組みの内容高等学校からの依頼に応じ、国際、人文、メディア表現、芸術、デザイン、マンガの幅広い領域で連携授業を実施しています。教員を高校等に派遣し授業を行うだけでなく、高校生を招いて大学の設備を活用した専門教育を行っています。
●取り組みの内容高等学校からの依頼に応じ、国際、人文、メディア表現、芸術、デザイン、マンガの幅広い領域で連携授業を実施しています。教員を高校等に派遣し授業を行うだけでなく、高校生を招いて大学の設備を活用した専門教育を行っています。
また、2019年度より、高校生の自由な創作活動の応援と、新しい才能の発見を目的とした京都精華大学主催のコンペティション「セイカアワード」を開催しています。
美術に限定されることなく開かれた表現の発表機会として、美術・工芸、デザイン、マンガ、メディア、文章などの多様な表現部門からオリジナル作品を公募し、毎年1000件ほどの応募があります。 - 産官学連携?
-
 ●取り組みの内容本学では、企業や自治体と連携して取り組む「産学連携プロジェクト」を積極的に行っています。メーカーと協力して、これからの社会に必要な商品を開発するプロジェクトや、学生ならではの視点を活かして、すでにあるものの新しい使い方やデザインを考えるプロジェクトなどさまざま。学生のアイデアや作品が高く評価され、商品化に結びつくことも少なくありません。プロジェクトへの参加を通して、社会のニーズを理解し、アイデアを生み出し、かたちにしていくといった実際の仕事と同じプロセスを体験することで、ビジネスの現場で求められる実践力を身につけることができます。
●取り組みの内容本学では、企業や自治体と連携して取り組む「産学連携プロジェクト」を積極的に行っています。メーカーと協力して、これからの社会に必要な商品を開発するプロジェクトや、学生ならではの視点を活かして、すでにあるものの新しい使い方やデザインを考えるプロジェクトなどさまざま。学生のアイデアや作品が高く評価され、商品化に結びつくことも少なくありません。プロジェクトへの参加を通して、社会のニーズを理解し、アイデアを生み出し、かたちにしていくといった実際の仕事と同じプロセスを体験することで、ビジネスの現場で求められる実践力を身につけることができます。
また、大学と社会とのつながりの中で本学の活動を社会に発信し、同時に社会の活動を本学に導引することにより、教育・研究活動の向上と発展に寄与することを目的に、社会連携センターが設置されています。「本学における社会との連携プログラムの推進」、「公開講座等社会に向けた各種プログラムの推進」、「産官学連携事業の推進」を主な取り組みの柱として、積極的に大学の資源を社会に発信しています。 - 地域連携?
-
 ●取り組みの内容本学は、京都府との連携・協力に関する包括協定を締結しており、本学の研究成果や資材を活かし、府民啓発・府民運動、文化・観光の振興、まちづくり・地域福祉などについて、京都府と連携・協力しながら協働事業に取り組んでいます。京都府にとっては、府民サービスの充実や府内全域の地域活性化。本学にとっては、教育研究の成果発信、フィールド学習や研究を通じた学生の成長、大学と地域の交流の充実につながることが期待されています。
●取り組みの内容本学は、京都府との連携・協力に関する包括協定を締結しており、本学の研究成果や資材を活かし、府民啓発・府民運動、文化・観光の振興、まちづくり・地域福祉などについて、京都府と連携・協力しながら協働事業に取り組んでいます。京都府にとっては、府民サービスの充実や府内全域の地域活性化。本学にとっては、教育研究の成果発信、フィールド学習や研究を通じた学生の成長、大学と地域の交流の充実につながることが期待されています。
その他、公開講座、地元商店街のまちづくりへの協力、交通機関との連携イベント、情報館の利用解放など、多角的な連携強化に取り組んでいます。 - 科目等履修制度?
-
 ●取り組みの内容本学卒業生で教職課程の単位未修得者に対して、科目等履修を認めています。
●取り組みの内容本学卒業生で教職課程の単位未修得者に対して、科目等履修を認めています。 - 社会人教育?
-
 ●取り組みの内容京都精華大学は、国際文化、メディア表現、芸術、デザイン、マンガの5つの特色ある学部を有し、表現を通じて社会に貢献する人間を育成してきました。その教育・研究の資源を社会に提供すべく2018年に「リカレント教育プログラム」を開設。本プログラムでは、仕事に活かせる知識やスキルを高める学習の機会を提供することで社会の要請が高まる「学び直し(リカレント学習)」のニーズに応え、多様な働き方を支援します
●取り組みの内容京都精華大学は、国際文化、メディア表現、芸術、デザイン、マンガの5つの特色ある学部を有し、表現を通じて社会に貢献する人間を育成してきました。その教育・研究の資源を社会に提供すべく2018年に「リカレント教育プログラム」を開設。本プログラムでは、仕事に活かせる知識やスキルを高める学習の機会を提供することで社会の要請が高まる「学び直し(リカレント学習)」のニーズに応え、多様な働き方を支援します - 生涯学習?
-
 ●取り組みの内容京都精華大学公開講座ガーデンは、京都精華大学の〈知〉や〈技〉をさまざまな形で提供する生涯学習プログラムです。
●取り組みの内容京都精華大学公開講座ガーデンは、京都精華大学の〈知〉や〈技〉をさまざまな形で提供する生涯学習プログラムです。
キャンパスの充実した設備で取り組む造形、本格的な伝統工芸の体験、刺激的なレクチャーなど、本学ならではの講座をそろえています。 - 多様な研究内容?
-
 ●取り組みの内容本学における研究活動の推進および活動成果の発信を担う全学研究機構および同機構内に3つの研究センターを設置し、先進的な取り組みを行っています。
●取り組みの内容本学における研究活動の推進および活動成果の発信を担う全学研究機構および同機構内に3つの研究センターを設置し、先進的な取り組みを行っています。
■ 国際マンガ研究センター
国内外のネットワークを構築する一方、マンガやその原画などのアーカイブを行い、研究を進めています。研究知見は大学の教育に反映されるとともに、展覧会やイベントなどの形で公開することで、マンガ文化の価値そのものを創出し続けています。
■ 伝統産業イノベーションセンター
本学では、学生が伝統産業の工房に通い手仕事の技やその精神性を学ぶ学外実習を1979年から継続しています。当センターはその知見を集約し、より活発な教育・研究活動に還元するため2017年に設立。研究・教育・社会連携活動を大きな軸として、さまざまな国や地域の手仕事との連携をめざします。
■ アフリカ・ アジア現代文化研究センター
アフリカ・アジアの現代文化を考察し、新しい世界のあり方を探ることを目的に2020年4月に設立。アフリカやアジアをフィールドとする研究者やアーティストを積極的に受け入れ、学部の教育研究活動ともリンクする研究拠点をめざします。 - 研究施設・設備の充実?
-
 ●取り組みの内容本学では講義室や最新のソフトウェアを完備したPCルーム、すべての学生が使用できる写真スタジオ、つくるものに応じた専門の工房やスタジオを夜22時まで使用できます。警備は24時間体制で、夜間も見まわりを行っています。22万冊の蔵書に、DVDやCDも所蔵する「情報館」には、映像や音響編集のための機器を備えた「メディアセンター」もあり、授業課題や作品制作に活用できます。また、約30万点のマンガ関連資料を所蔵する「京都国際マンガミュージアム」が無料で利用できます。
●取り組みの内容本学では講義室や最新のソフトウェアを完備したPCルーム、すべての学生が使用できる写真スタジオ、つくるものに応じた専門の工房やスタジオを夜22時まで使用できます。警備は24時間体制で、夜間も見まわりを行っています。22万冊の蔵書に、DVDやCDも所蔵する「情報館」には、映像や音響編集のための機器を備えた「メディアセンター」もあり、授業課題や作品制作に活用できます。また、約30万点のマンガ関連資料を所蔵する「京都国際マンガミュージアム」が無料で利用できます。
さらに、学生はすべて、下記のソフトフェアを無償で個人のパソコンにインストールして使用できます。
●Adobe社ソフトウェア最新バージョン「After Effects」「Flash」「Illustrator」「InDesign」「Photoshop」など
●Microsoft社「Microsoft Office」最新バージョン「Word」「Excel」「PowerPoint」「Access」など
このように本学では、研究設備の充実にハードウェアならびにソフトウェアの両面から取り組み学びの支援を行っています。
連携活動
生涯教育
研究活動
×
『外国人教員雇用・派遣受入』とは?
外国人教員を雇用したり、外国の学校と協定などを結んで派遣してもらった外国人教員を受け入れて、教育や研究活動をさせる取り組み。
×
『外国人留学生受入』とは?
国際交流の活性化や教育の活性化を図ることを目的として、制度的に海外からの留学生を日本の大学・短期大学等に受け入れる取り組み。
×
『海外留学、スタディ・アブロード』とは?
日本の学生が海外の学校で学ぶときに、短期間のプログラムから1学期や1年間以上の長期プログラムの留学制度を設定するなどして、大学等として留学を支援する取り組み。
×
『学校間連携』とは?
主に高等教育機関(大学、短期大学、高等専門学校、専門学校など)同士がより良い教育や充実した研究活動をすることを目的に連携協力する取り組み。
×
『高大連携プログラム』とは?
高校と大学の協力により、高校生が大学の学びを体感し、学びに対する意欲を向上させるため、大学の授業への参加や、大学教員の高校での出張講義などの教育プログラムを行う取り組み。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『産官学連携』とは?
大学や短期大学が、産(産業界・民間企業等)、官(政府・地方公共団体等)、あるいはその二者と連携することで、効果的な研究や教育などを行う取り組み。
×
『地域連携』とは?
大学や短期大学が地域社会のニーズに応え、地域と積極的に関わることで、地域の活性化などに貢献し、地域の各市町村などと連携する取り組み。
×
『科目等履修制度』とは?
社会人などのその学校や学部などには在籍していない者に対し、特定の授業科目の履修を認め、正規の学生と同様に授業や試験を行い、単位を授与する制度。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『社会人教育』とは?
社会人を対象とした新たな知識や技術の修得や学び直しに対して、カリキュラムや授業の配慮をするなど学びを支援し、推進することで大学を活性化させることを目的とした取り組み。
×
『生涯学習』とは?
人が生涯にわたり学びや学習の活動を続けていく生涯学習について、大学や短期大学が学びの場や機会を提供するなどの取り組み。
×
『多様な研究内容』とは?
大学の重要な目的である学生への教育と研究活動のうち、大学が行っている様々な研究活動についての取り組み。
×
『研究施設・設備の充実』とは?
大学の重要な目的である学生への教育と研究活動のうち、研究活動の推進のために建物などの研究施設を建てたり、研究機器などの設備を整備したりする取り組み。
2025年度オープンキャンパス・オンラインイベント情報
2026年度 入試&高校生・受験生向け情報
オープンキャンパス日程
大学院入試情報
2024年度オープンキャンパス・オンラインイベント情報
2025年度 入試&高校生・受験生向け情報
2023年度オープンキャンパス・オンラインイベント情報
2024年度 入試&高校生・受験生向け情報
芸術学部ニュース
デザイン学部関連ニュース
入試&高校生・受験生向け情報
入試&高校生・受験生向け情報
マンガ学部関連ニュース
メディア表現学部関連ニュース
入試&高校生・受験生向け情報
大学院入試情報
大学院入試情報