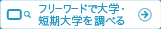関西福祉大学
関西福祉大学
看護学部

- ディプロマポリシー
-
■看護学部
次に示す4項目の能力・素養を身につけ、かつ所定の単位を修得した学生に卒業を認定し、学位を授与する。
(1)豊かな人間性を育み、ヒューマンケアリングが実践できる能力。
(2)看護の独自性を発揮し、保健・医療・福祉チームで連携・協働できる能力。
(3)国際社会及び地域社会の健康に対する多様なニーズに貢献できる能力。
(4)ヒューマンケアに対する科学的探究心や創造性をもち、生涯学習へ主体的に取り組む姿勢。詳細リンク(外部サイトへ) - カリキュラムポリシー
-
■看護学部
教育目的を踏まえ、看護学部のカリキュラムを「一般教養」「看護実践の基盤」「看護の発展」の枠組みで構成する。
「一般教養」では、人文・社会・自然に関する諸科学を基盤として、豊かな人間性と国際的な視野・教養を深める。「看護実践の基盤」では、看護の理論的枠組みを理解する。「看護の発展」では、あらゆる健康レベルに対応する看護の知識・応用技術を学修する。
これらのカリキュラム構成により、各学年で次の内容を身につける
1年次:豊かな人間性と社会的マナーをしっかり身につけ、看護を理解し、看護に対する興味・関心をもつ。
2年次:人の身体と心と社会に関心をもち、専門知識を用いて対象の状況に応じた看護を考える。
3年次:演習及び実習を通して得た知識・技術を活用し、看護の役割と関連職種との連携について関心を深め、基礎的な看護を実践できる。
4年次:看護学習の集大成として、対象となるすべての人々のニーズを尊重し、看護の担い手としての責任と主体的に研鑽する姿勢を身につけ、看護専門職者としての自覚をもつ。
詳細リンク(外部サイトへ)
カリキュラム
- 教育内容の体系化とその充実?
-
 ●取り組みの内容看護学部の目的は、「生命の尊厳と人権を尊重し擁護する倫理観を培うとともに、その人がその人らしく生きられるようなヒューマンケアを提供し、保健・医療・福祉を総合的に捉え、社会の多様なニーズに対応し、地域社会および国際社会に貢献しうる質の高い実践能力のある看護専門職者を育成すること」です。
●取り組みの内容看護学部の目的は、「生命の尊厳と人権を尊重し擁護する倫理観を培うとともに、その人がその人らしく生きられるようなヒューマンケアを提供し、保健・医療・福祉を総合的に捉え、社会の多様なニーズに対応し、地域社会および国際社会に貢献しうる質の高い実践能力のある看護専門職者を育成すること」です。
この目的を達成するために本学部では少人数の参加型授業を中心として、「一般教養」「看護実践の基盤」「看護の発展」にカリキュラムを体系化し、「ヒューマンケアリング」の精神を身につけた看護師を養成しています。
- 教養・リベラルアーツ教育?
-
 ●取り組みの内容本学部では、カリキュラムポリシーに「人文・社会・自然に関する諸科学を基盤として、豊かな人間性と国際的な視野・教養を深める」と定義し、初年次における教養教育の充実を図っています。
●取り組みの内容本学部では、カリキュラムポリシーに「人文・社会・自然に関する諸科学を基盤として、豊かな人間性と国際的な視野・教養を深める」と定義し、初年次における教養教育の充実を図っています。
とりわけ、「教養ゼミナール」は、1年生の必修科目と設定し、大学において主体的に学ぶこと、探求することの楽しさを見いだすことを目的にしています。すなわち、本の読み方、まとめ方(レジュメの作り方)、発表の仕方、討論の仕方などです。この教養ゼミナールをはじめとする教養科目群の履修を通じて、本学部では看護の全体像を理解できる人材の養成を実施しています。
教育方法
- アクティブラーニング?
-
 ●取り組みの内容本学部では、少人数の参加型授業に力点を置いております。実習を通して経験した事柄についてグループ・ワークを実施し発表する授業や、グループのメンバーとの討論や発表等を通じて、論理的な思考力や表現力を培う授業など、多様な授業を通じて主体的に学ぶ態度を習得します。
●取り組みの内容本学部では、少人数の参加型授業に力点を置いております。実習を通して経験した事柄についてグループ・ワークを実施し発表する授業や、グループのメンバーとの討論や発表等を通じて、論理的な思考力や表現力を培う授業など、多様な授業を通じて主体的に学ぶ態度を習得します。
また、ハード面においては「アクティブ・ラーニングルーム」や学生ホールに設置した開放型の「プレゼンテーションスペース」を利用した学生の自主的な〈学び〉を促進するなど、学習環境の充実にも力をいれております。
- 課題解決型学習(PBL)?
-
 ●取り組みの内容本学部では、看護師養成を担っている学部の性格からも、課題解決型の学びを重視しています。例えば「地域アセスメント」では、地域看護計画の立案を主題としており、住民とのパートナーシップのもと、統計データや保健施策などから地域をアセスメントし、根拠に基づく診断・健康課題を把握するとともに1次予防、2次予防、3次予防活動の計画立案演習を実施しています。このような演習をはじめ、様々なグループワークを通じて学生の課題解決能力を育んでいます。
●取り組みの内容本学部では、看護師養成を担っている学部の性格からも、課題解決型の学びを重視しています。例えば「地域アセスメント」では、地域看護計画の立案を主題としており、住民とのパートナーシップのもと、統計データや保健施策などから地域をアセスメントし、根拠に基づく診断・健康課題を把握するとともに1次予防、2次予防、3次予防活動の計画立案演習を実施しています。このような演習をはじめ、様々なグループワークを通じて学生の課題解決能力を育んでいます。
- 少人数教育?
-
 ●取り組みの内容本学部では、少人数の参加型授業に力点を置いております。教養ゼミナールや卒業研究等では、少人数による授業を通して「自学力」を身につけることに主眼をおいて教育を実施しております。また教員が「アカデミック・アドバイザー」となり、数人の学生を担任するとともに、学生の一番の理解者として、大学での学びや学生生活などを全般にわたってサポートし、学生の力を最大限引き出せるよう学びを支え、自立して学ぶ力「自学力」を身につけるよう支援しております。
●取り組みの内容本学部では、少人数の参加型授業に力点を置いております。教養ゼミナールや卒業研究等では、少人数による授業を通して「自学力」を身につけることに主眼をおいて教育を実施しております。また教員が「アカデミック・アドバイザー」となり、数人の学生を担任するとともに、学生の一番の理解者として、大学での学びや学生生活などを全般にわたってサポートし、学生の力を最大限引き出せるよう学びを支え、自立して学ぶ力「自学力」を身につけるよう支援しております。
学びの支援
- 学びの組織的な支援?
-
 ●取り組みの内容学修支援及び授業支援については、教員及び職員で構成される学生委員会が中心となり、学生支援課、教務課、キャリア開発課等の関係各課及び各学部学科と連携をとりながら行っています。
●取り組みの内容学修支援及び授業支援については、教員及び職員で構成される学生委員会が中心となり、学生支援課、教務課、キャリア開発課等の関係各課及び各学部学科と連携をとりながら行っています。
具体的には、履修指導から学修の進め方、さらには成績・単位取得に関する指導・支援、図書館での蔵書検索や他大学等の図書館を利用する相互利用等の方法の指導を行うレポート及び論文作成等の支援を行っています。また、学士課程では、専任教員が学生一人ひとりを担当し、主に履修指導・進路指導・休学及び退学に関する指導等を行うアカデミック・アドバイザー制度を設けており、中途退学者及び留年者への対応も行っています。学修及び授業支援に対する学生の意見等を汲み上げる仕組みとして、現在、学生による授業評価アンケートを全学で実施しており、アンケート実施後、アンケートの集計結果を各教員に配布し、学修及び授業支援のために役立てています。
- 学修成果のフィードバック?
-
 ●取り組みの内容本学の各学部において、主に専門職を養成していることから、国家試験や教員採用試験の合格を重視しています。
●取り組みの内容本学の各学部において、主に専門職を養成していることから、国家試験や教員採用試験の合格を重視しています。
- 初年次教育?
-
 ●取り組みの内容本学部では、初年次において「教養ゼミナール」を設定し、初年次におけるドロップアウトを防止するとともに、大学において主体的に学ぶこと、探求することの楽しさを見いだすことを目的として初年次教育を実施しています。すなわち、本の読み方、まとめ方(レジュメの作り方)、発表の仕方、討論の仕方など、学び方を学び、大学生としての基盤づくりにつとめています。
●取り組みの内容本学部では、初年次において「教養ゼミナール」を設定し、初年次におけるドロップアウトを防止するとともに、大学において主体的に学ぶこと、探求することの楽しさを見いだすことを目的として初年次教育を実施しています。すなわち、本の読み方、まとめ方(レジュメの作り方)、発表の仕方、討論の仕方など、学び方を学び、大学生としての基盤づくりにつとめています。
- 中途退学防止?
-
 ●取り組みの内容本学では、専任教員が「アカデミック・アドバイザー」として、学生や保護者からの様々な相談に乗り、適時に適切な助言を行う制度を設けています。
●取り組みの内容本学では、専任教員が「アカデミック・アドバイザー」として、学生や保護者からの様々な相談に乗り、適時に適切な助言を行う制度を設けています。
アカデミック・アドバイザーは、退学に係る相談など学籍異動に直接関連する相談のほか、履修、生活面、進路・就職、資格取得などの助言を行い、学生生活を送る上での不安感や負担感を軽減します。
事務職員においては、アカデミック・アドバイザーが上記の相談・助言を行う際、所属部署の業務特性に応じた学生サポートを行い、教職協働で学生をサポートしています。
また、学生生活のなかで起こる心理的・精神的な悩みや問題の解決や、学修上や学生生活の上で支援が必要な学生が安心して安定的に学ぶことができるよう適切な支援を行う「学生相談支援室」を設置しています。学生相談支援室は、家庭の経済的な課題、奨学金やアルバイト、履修、下宿生活など、幅広い相談にも対応しています。
アカデミック・アドバイザー、事務職員、学生相談支援室は緊密に連携し、必要な対応を行っています。
以上のように、本学では様々な制度や組織的な枠組みを利用して、学生の中途退学防止に取り組んでいます。 - 入学前教育?
-
 ●取り組みの内容専願入試合格者を対象に、入学前教育として、看護を学ぶ前に整理しておくべき基礎知識の定着を図るための学習、課題図書を読み自分の考え方をまとめる学習、社会的事象への関心を深める学習を行っています。また、入学前に教員や在学生、合格者同士の交流を図る機会としてスクーリングを実施しています。
●取り組みの内容専願入試合格者を対象に、入学前教育として、看護を学ぶ前に整理しておくべき基礎知識の定着を図るための学習、課題図書を読み自分の考え方をまとめる学習、社会的事象への関心を深める学習を行っています。また、入学前に教員や在学生、合格者同士の交流を図る機会としてスクーリングを実施しています。
- 特色ある教育施設・設備の整備?
-
 ●取り組みの内容学内には質と量の両面を備えた実習環境を整備し、高度な学びを展開
●取り組みの内容学内には質と量の両面を備えた実習環境を整備し、高度な学びを展開
1年次から基礎的な看護技術を学ぶため活用する第1実習室、在宅でのケアを学ぶ設備も充実した第2実習室、母性看護、小児看護を学ぶ第3実習室。実習室はすべて講義スペースを併設しており、座学と演習を組み合わせた授業を行います。また、3つの実習室に加え、子どもや成人の高機能シミュレータや模擬カルテシステムを導入し、より多くの症例を取り扱えるシミュレーションルームを整備しています。録画や記録を見ながら振り返り学習ができるようにICT機器も備え、現場に近い学習環境を整えています。
また、看護学部には、看護技術を修得するために効果的なさまざまな器具などが豊富にあります。 - 学生アンケートの活用?
-
 ●取り組みの内容本学では、学生の現況(通学・居住環境、経済状況、アルバイトの状況、課外活動、ボランティア活動の参加状況、1日あたりの学習時間)、学生の意見・要望を把握し、学生への各種サービスの向上、授業改善や大学・学部の運営に反映させるため、学生アンケート、学生による授業評価アンケート、大学構内での聞き取りアンケートなどを実施しています。
●取り組みの内容本学では、学生の現況(通学・居住環境、経済状況、アルバイトの状況、課外活動、ボランティア活動の参加状況、1日あたりの学習時間)、学生の意見・要望を把握し、学生への各種サービスの向上、授業改善や大学・学部の運営に反映させるため、学生アンケート、学生による授業評価アンケート、大学構内での聞き取りアンケートなどを実施しています。
これらのアンケート以外にも、学内4箇所に意見箱「ボイス」を設置しています。これは、学生が履修・授業、学生生活、就職・進路支援、課外活動、施設・設備などに関する意見・要望を大学に伝えるための自由記述式アンケートです。原則、毎週1度開封し、投函された内容を学内メールで全教職員に配信します。その後、それぞれの意見・要望の内容を所掌する部門が対応(回答)内容を起案し、これを翌週の開封時に掲示(学生への回答)しています。この「ボイス」によって改善がなされた、学生の要望が実現した主なケースとしては、授業内容の改善、学生用荷物保管ロッカーの設置、食堂のメニュー改善(内容・価格・食数)、トレーニング施設の拡充・機器類の充実、スクールバスの増便などがあります。
- キャリア教育?
-
 ●取り組みの内容本学部では、1年次より科目として「看護キャリア形成」を開講し、キャリア教育の概念や看護職としての職業観を学び、学生生活、そして卒業後に向けた計画を学生自身が立案し、自らのキャリア形成に向けた教育を実施しています。
●取り組みの内容本学部では、1年次より科目として「看護キャリア形成」を開講し、キャリア教育の概念や看護職としての職業観を学び、学生生活、そして卒業後に向けた計画を学生自身が立案し、自らのキャリア形成に向けた教育を実施しています。
- 資格取得(国家資格受験資格)?
-
 ●取り組みの内容本学部では、2年次より国家試験対策模擬試験を実施するとともに、3年次・4年次では
●取り組みの内容本学部では、2年次より国家試験対策模擬試験を実施するとともに、3年次・4年次では
模擬試験に加え、国家試験対策講座を夏期・秋期・冬期に実施しています。
また、国家試験対策テキストの助成販売等を実施するなど、学生の資格取得を強力にサポートしています。
学修についての評価
- 成績評価の厳格な運用?
-
 ●取り組みの内容単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準については「関西福祉大学学則」「関西福祉大学看護学部履修規程」に基づいて行っています。
●取り組みの内容単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準については「関西福祉大学学則」「関西福祉大学看護学部履修規程」に基づいて行っています。
授業科目の成績評価は、試験、レポート、発表内容、授業への参加度、出席状況等、多元的な基準を設定しています。いずれの評価方法を採用するかは、授業の形態、目的などが各々の科目により異なるため、各科目担当教員が適切に評価し、成績を付与しています。科目ごとの評価基準については、学生ハンドブック及び本学ホームページに掲載しているシラバスの「単位認定基準」に明示しています。また、付与された成績評価について、学生が自己の学修状況を踏まえ疑義のある場合は、所定の手続きを経て、科目担当者に成績の確認をすることもできます。 - 学修成果のフィードバック?
-
 ●取り組みの内容本学の各学部において、主に専門職を養成していることから、国家試験や教員採用試験の合格を重視しています。
●取り組みの内容本学の各学部において、主に専門職を養成していることから、国家試験や教員採用試験の合格を重視しています。
×
『教育内容の体系化とその充実』とは?
教育の目的や成果を明確に設定し、その達成のため、各授業間の関連性を明確にするなど、体系的な学びを可能にすることで、教育内容の一層の充実を図る取り組み。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『教養・リベラルアーツ教育』とは?
幅広い分野の教養などを身につけ、専門知識に偏らない汎用的能力を育成するために大学・短期大学で行われる教育。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『アクティブラーニング』とは?
一方的に講義を聴くスタイルの授業ではなく、学生が積極的に学修に参加することを取り入れ、能動的(アクティブ)な学びを促すことで、知識をしっかり定着させることを目的とした学習方法。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『課題解決型学習(PBL)』とは?
プロジェクト活動を通じ、学生が自主的・自律的に課題を発見・解決する過程において、それまでに得た知識を実践的に活用することや、より学びを深くすることなどを目的とした学習方法。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『少人数教育』とは?
学習効果を高めるために、1人の教員が教える学生の数を少なくして授業を行う学習方法。
×
『学びの組織的な支援』とは?
学校側が組織的かつ恒常的に学びに対するサポート体制を用意し、授業に対する学生の不安を解消するなどの学びに対する様々な支援をすることで、より学習効果を高める取り組み。
×
『学修成果のフィードバック』とは?
授業や講義などを通して学生が学んだ知識や技術や成績などの「学修成果」を、可視化するなどして学生にわかりやすく還元することで、学生自らの学びへの姿勢を支援する取り組み。
×
『初年次教育』とは?
大学や短期大学の新入生を対象に、高校までの学びから、能動的な大学・短期大学での学びにスムーズに移行するための基本的なスキルなどを身につける教育プログラム。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『中途退学防止』とは?
学びに対する意欲の減少などを理由に修業期間の途中で学校を退学しようとする学生に対して、学びのサポートを行うことで、教育の問題解決を図り、学びの環境を改善し、中途退学を防ぐ取り組み。
×
『入学前教育』とは?
入学予定者(主にAO入試や各種推薦入試などで、早期に入学が決定した入学予定者)に対して、入学後の学びの準備や学習意欲の維持などのために、入学前に行う教育。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『特色ある教育施設・設備の整備』とは?
特別な校舎や教室、実習室などの教育施設や教室等にある機器などの設備を整備し活用することで、教育内容やプログラムの充実などに活かす取り組み。
×
『学生アンケートの活用』とは?
新入生や在学している学生に対し、大学の授業やカリキュラム、学修状況などについてアンケートを行い、その結果を分析・活用して、教育方法やプログラムの改善などに活かす取り組み。
×
『キャリア教育』とは?
大学や短期大学の学修プログラムの一環として、カリキュラムに社会人・職業人として必要な能力などを身に付けるための科目等を組み入れ、学生のキャリア形成計画や目標設定を支援する教育。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『資格取得(国家資格受験資格)』とは?
カリキュラムの整備や授業内容の工夫などを行い、学生が正課の授業を受けることで国家資格試験を受験し、合格することを目的に支援する取り組み。
×
『成績評価の厳格な運用』とは?
明確な成績評価の基準を定めて厳格に運用して、単位取得や進級などを判定することで、教育の「質の保証」を実現する取り組み。
×
『学修成果のフィードバック』とは?
授業や講義などを通して学生が学んだ知識や技術、成績などの「学修成果」を活用し、学生の学びの振り返りを促すことで、学びの定着を図ることを目的とした取り組み。