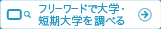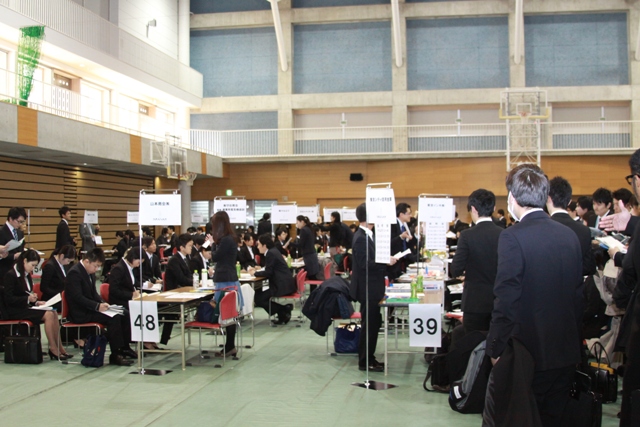大東文化大学
大東文化大学
法学部

外国人教員
- 外国人教員雇用・派遣受入?
-
 ●取り組みの内容法学部では、専任教員2名および非常勤講師3名の外国人教員を雇用しています。
●取り組みの内容法学部では、専任教員2名および非常勤講師3名の外国人教員を雇用しています。
外国人留学生受入
- 外国人留学生受入?
-
 ●取り組みの内容「アジアから世界へ:広く世界に開かれ、多文化が共生する国際性豊かなキャンパスの創造」を国際交流の大きなヴィジョンとし、国際連携ネットワークの構築、多文化理解教育キャンパスの創造という二つの側面から、国際化を推進しています。特に、国際性豊かなキャンパスを創成するために、受入れ留学生の拡大に取り組んでいます。
●取り組みの内容「アジアから世界へ:広く世界に開かれ、多文化が共生する国際性豊かなキャンパスの創造」を国際交流の大きなヴィジョンとし、国際連携ネットワークの構築、多文化理解教育キャンパスの創造という二つの側面から、国際化を推進しています。特に、国際性豊かなキャンパスを創成するために、受入れ留学生の拡大に取り組んでいます。
留学支援
- 海外留学、スタディ・アブロード?
-
 ●取り組みの内容法律学科と政治学科は4月から6月にかけて奨学金留学生の選考を行います。定員は法律学科は2名、政治学科は1名です。英語圏に留学するケースがほとんどですが、毎年留学生を送り出しています。また、帰国後は留学中に取得した単位を本学での卒業単位として認定する場合があります。短期英語研修は2月と8月に国際交流センター主催の研修があります。帰国後は留学中に取得した単位を本学での卒業単位として認定する場合があります。
●取り組みの内容法律学科と政治学科は4月から6月にかけて奨学金留学生の選考を行います。定員は法律学科は2名、政治学科は1名です。英語圏に留学するケースがほとんどですが、毎年留学生を送り出しています。また、帰国後は留学中に取得した単位を本学での卒業単位として認定する場合があります。短期英語研修は2月と8月に国際交流センター主催の研修があります。帰国後は留学中に取得した単位を本学での卒業単位として認定する場合があります。
外国人教員
- 職別
-
法学部の外国人職員数は表のとおりです。
男 女 計 学長 0 0 0 副学長 0 0 0 教授 1 0 1 准教授 1 0 1 講師 0 0 0 助教 0 0 0 助手 0 0 0 計 2 0 2
外国人留学生
- 学年別
-
法学部の外国人留学生数は表のとおりです。
男 女 計 1年 3 6 9 2年 4 3 7 3年 2 1 3 4年 2 1 3 計 11 11 22
連携活動
- 学校間連携?
-

- 高大連携プログラム?
-

- 地域連携?
-
 ●取り組みの内容法学部は、カリキュラムの中に東松山市役所と板橋区役所におけるインターンシップを入れています。また2015年度からの新カリキュラムでは地域政策総合研究を導入します。大学院においてはすでに自治体職員によるオムニバス授業が実施されています。2014年度は地方自治論の授業において自治体職員による講義が2回開催されました。
●取り組みの内容法学部は、カリキュラムの中に東松山市役所と板橋区役所におけるインターンシップを入れています。また2015年度からの新カリキュラムでは地域政策総合研究を導入します。大学院においてはすでに自治体職員によるオムニバス授業が実施されています。2014年度は地方自治論の授業において自治体職員による講義が2回開催されました。
研究においては、自治体との共同研究や各種審議会への参画がなされ、社会に貢献しています。
生涯教育
- 科目等履修制度?
-
 ●取り組みの内容大東文化大学では、科目等履修制度を設けています。科目等履修制度とは、本大学の学生以外の者が特定の授業科目について聴講できる制度のことであり、1又は複数の授業科目について履修を願い出ることができます。原則として、入学の時期は学年の始めとなりますが、学年の後学期に開講する授業科目のみを履修するときは、後学期の始めに入学することも可能です。
●取り組みの内容大東文化大学では、科目等履修制度を設けています。科目等履修制度とは、本大学の学生以外の者が特定の授業科目について聴講できる制度のことであり、1又は複数の授業科目について履修を願い出ることができます。原則として、入学の時期は学年の始めとなりますが、学年の後学期に開講する授業科目のみを履修するときは、後学期の始めに入学することも可能です。
教職課程科目を履修するなど、この科目等履修制度を利用して教員免許資格取得を目指している学生も多くいます。 - 社会人教育?
-

- 生涯学習?
-

社会貢献
- ボランティア活動?
-

×
『外国人教員雇用・派遣受入』とは?
外国人教員を雇用したり、外国の学校と協定などを結んで派遣してもらった外国人教員を受け入れて、教育や研究活動をさせる取り組み。
×
『外国人留学生受入』とは?
国際交流の活性化や教育の活性化を図ることを目的として、制度的に海外からの留学生を日本の大学・短期大学等に受け入れる取り組み。
×
『海外留学、スタディ・アブロード』とは?
日本の学生が海外の学校で学ぶときに、短期間のプログラムから1学期や1年間以上の長期プログラムの留学制度を設定するなどして、大学等として留学を支援する取り組み。
×
『学校間連携』とは?
主に高等教育機関(大学、短期大学、高等専門学校、専門学校など)同士がより良い教育や充実した研究活動をすることを目的に連携協力する取り組み。
×
『高大連携プログラム』とは?
高校と大学の協力により、高校生が大学の学びを体感し、学びに対する意欲を向上させるため、大学の授業への参加や、大学教員の高校での出張講義などの教育プログラムを行う取り組み。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『地域連携』とは?
大学や短期大学が地域社会のニーズに応え、地域と積極的に関わることで、地域の活性化などに貢献し、地域の各市町村などと連携する取り組み。
×
『科目等履修制度』とは?
社会人などのその学校や学部などには在籍していない者に対し、特定の授業科目の履修を認め、正規の学生と同様に授業や試験を行い、単位を授与する制度。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『社会人教育』とは?
社会人を対象とした新たな知識や技術の修得や学び直しに対して、カリキュラムや授業の配慮をするなど学びを支援し、推進することで大学を活性化させることを目的とした取り組み。
×
『生涯学習』とは?
人が生涯にわたり学びや学習の活動を続けていく生涯学習について、大学や短期大学が学びの場や機会を提供するなどの取り組み。
×
『ボランティア活動』とは?
学生が自発的に行うボランティア活動に対して、大学や短期大学が活動の支援や単位認定などをすることにより、学生生活が活性化することを目的とした取り組み。
大東文化大学からのお知らせ