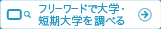兵庫県(所在地都道府県)/大学院研究科(部門種別)

関西学院大学
関西学院大学

関西学院大学
関西学院大学
商学研究科(博士)
特色
- 高度な専門性と豊かな人間性を備えた研究者の養成を目指す
-
従来、博士課程修了者は、高等教育機関・研究所等における教員あるいは研究者として活躍することが主流でした。しかし、近年の経済社会の変革と進展のスピードは著しく、企業等の組織運営にあってもテクノロジーの急速な進歩や社会変革に対応する能力が問われています。そこで要求されるのは経験と勘ではなく、高度の論理的思考能力と分析力です。従って、組織運営を深く洞察する能力を有する人材が必要になると考えられており、社会科学 、とくに商学に深く精通した理論的基盤のある高度専門家の育成が重要と考えられます。
商学研究科では、「研究者」の概念をこれまでのように高等教育機関等の教員、研究者に限定せず、組織運営上の開発・分析能力を備えた人材をも研究者と捉え、その活動のスタートとなる課程博士の学位取得を教育目的として位置づけます。入学段階から一人ひとりの院生に「博士論文指導委員会」を設けての複数指導体制をとり、博士学位取得までを一貫して指導する責任を明確にした教育研究制度をとっています。3年の課程内での博士学位取得、遅くとも後期課程進学後5年以内の博士学位取得を目指しています。詳細リンク(外部サイトへ)●特色の目的学びの質の向上研究活動
本研究科の目的
- 目的
-
経営、会計、マーケティング、ファイナンス、ビジネス情報、国際ビジネスの6分野において、スクールモットーである“Mastery for Service”(奉仕のための練達)を具現化するために「組織運営に関して高い分析力と深い洞察力を有する研究者や専門職業人」を輩出します。詳細リンク(外部サイトへ)
- 3つの方針
-
●ディプロマポリシーディプロマポリシーについては、商学研究科ウェブサイト内、「商学研究科案内」のページで公開していますので、ご確認ください。詳細リンク(外部サイトへ)●カリキュラムポリシーカリキュラムポリシーについては、商学研究科ウェブサイト内、「商学研究科案内」のページで公開していますので、ご確認ください。詳細リンク(外部サイトへ)●アドミッションポリシーアドミッションポリシーについては、商学研究科ウェブサイト内、「商学研究科案内」のページで公開していますので、ご確認ください。詳細リンク(外部サイトへ)
更新情報
学部・学科情報
- 文学部
- 経済学部
- 法学部
- 商学部
- 神学部
- 社会学部
- 総合政策学部
- 人間福祉学部
- 教育学部
- 国際学部
- 工学部
- 生命環境学部
- 建築学部
- 理学部
- 理工学部
- 文学研究科(修士)
- 法学研究科(修士)
- 経済学研究科(修士)
- 神学研究科(修士)
- 商学研究科(修士)
- 文学研究科(博士)
- 神学研究科(博士)
- 法学研究科(博士)
- 経済学研究科(博士)
- 社会学研究科(修士)
- 社会学研究科(博士)
- 商学研究科(博士)
- 理工学研究科(修士)
- 理工学研究科(博士)
- 総合政策研究科(修士)
- 言語コミュニケーション文化研究科(修士)
- 総合政策研究科(博士)
- 言語コミュニケーション文化研究科(博士)
- 司法研究科(専門職)
- 経営戦略研究科(専門職)
- 人間福祉研究科(修士)
- 人間福祉研究科(博士)
- 経営戦略研究科(博士)
- 教育学研究科(博士)
- 教育学研究科(修士)
- 国際学研究科(博士)
- 国際学研究科(修士)